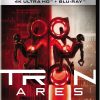Contents
はじめに:プレデターの余韻
昨年(2025年)11月に公開され、映画界に静かな衝撃を与えた『プレデター:バッドランド(Predator: Badlands)』の余韻がいまだに消えない。
ダン・トラクテンバーグ監督は、前作『プレイ(Prey)』でシリーズを「原点回帰」させて蘇らせた。だからこそ、我々は油断していた。「次はどう来る? 侍か? 現代戦か?」と。 しかし、彼が提示したのは、そのどれでもなかった。
『バッドランド』は、SFアクションではない。あれは、「異種間の魂の交錯」を描いた、極めて静謐な西部劇だった。 なぜこの映画が、我々のようなインディーズ映画屋の心臓をこれほどまでに抉るのか。そして、なぜ世界は再びこの醜い宇宙人に恋をしたのか。 公開から2ヶ月が経過した今、冷静な視点(と少しの熱狂)でその正体を分析する。
第1章:舞台装置の発明 —— 「隠れられない」という恐怖
1.1. ジャングルから荒野へ
初代『プレデター』の面白さは「ジャングル」にあった。見えない敵、木々のざわめき。 しかし、本作の舞台はタイトル通り「バッドランド(荒地)」。隠れる木もなければ、逃げ込む洞窟も少ない、乾いた大地だ。
ここでトラクテンバーグ監督が行った発明は、「視界は開けているのに、逃げ場がない」という逆説的なサスペンスだ。 VFX視点で見れば、これは非常に賢い。複雑な植物のシミュレーション(『アバター』がやっているようなこと)を捨て、荒涼とした背景美術と、埃っぽい大気感(アトモスフィア)だけで画を持たせている。
これは、低予算映画を作る我々にとって最大のヒントだ。「豪華なセット」を作るのではなく、「何もない場所」を舞台にし、その「なさ」を恐怖や孤独の演出に転化する。引き算の美学がそこにある。
1.2. テクノロジーの無力化
広大な荒野において、プレデターの光学迷彩は逆に目立つ瞬間がある(砂埃の歪みなど)。 本作は、プレデターの「強さ」をハイテク装備に依存させなかった。むしろ、装備が故障し、傷ついた状態で、いかに「狩人の本能」だけで戦うかを描いた。 ハイテク装備を剥ぎ取られたプレデターの姿は、まるで『マッドマックス』の放浪者のようであり、そこに初めて「個としてのキャラクター」が宿った。
第2章:エル・ファニングという「鏡」
2.1. 絶叫しないヒロイン
主演のエル・ファニング。彼女のキャスティングが発表された時、多くの人が首を傾げた。「シュワルツェネッガーの代わりが、あの華奢なエル?」と。 しかし、蓋を開けてみれば、彼女は戦士ではなかった。彼女は「理解者」だった。
劇中、彼女はプレデターと対峙しても、悲鳴を上げない。ただ、その異形の瞳をじっと見つめ返す。 彼女が演じたのは、社会から疎外されたアウトサイダーだ。だからこそ、地球外から来た孤独な狩人(プレデター)と、奇妙なシンパシーで繋がってしまう。
2.2. 「ストックホルム症候群」的バディもの
この映画の革新性は、中盤から「実質的なバディ・ムービー(相棒もの)」に変貌した点だ。 共通の敵(例えば、プレデターを軍事利用しようとする民間軍事会社など)に対し、言葉の通じない二人が背中合わせになる。 そこには恋愛感情はない。しかし、種族を超えた「戦士だけが知る共鳴」があった。ラストシーン、夕陽の荒野で交わされる視線のやり取りは、どんなラブロマンスよりも切なかった。
第3章:着ぐるみ(スーツ)への偏愛
3.1. 「そこにいる」という重み
CG全盛の時代に、本作は徹底して「プラクティカル・エフェクト(実写特撮)」にこだわった。 プレデターの皮膚の質感、乾いた泥、飛び散る体液。これらは、現場でスーツアクターが演じているからこそ出る「重み」だ。
我々『温泉シャーク』チームも特撮にこだわるが、それはノスタルジーだけではない。「実在感(プレゼンス)」は、観客の生理的反応に直結するからだ。 AIで生成したモンスターは綺麗だが、「臭い」がしない。トラクテンバーグ監督は、画面から「獣臭さ」と「鉄錆の匂い」を漂わせることに成功した。
3.2. ガジェットのギミック
また、プレデターの新武器のギミックも素晴らしかった。 ハイテクなレーザーではなく、より原始的で、痛々しい物理攻撃の数々。アナログな罠。 「制限がある中で工夫する」という描写は、そのままインディーズ映画制作の精神とリンクする。観客は、圧倒的な強さよりも、知恵と工夫で困難を乗り越える姿(たとえそれが怪物であっても)にカタルシスを感じるのだ。
第4章:IPのリサイクル戦略としての勝因
4.1. ジャンルの「越境」
ディズニー(20世紀スタジオ)は、プレデターというIPを「ただのSFアクション」として扱わなかった。
-
『プレイ』= ネイティブ・アメリカンの成長譚
-
『バッドランド』= 荒野の逃避行(ロードムービー)
ジャンルを「ズラす」ことで、同じキャラクターを使っても全く新しい客層(ドラマ好き、西部劇好き)を取り込んだ。 これは、サメ映画が「パニック」から「コメディ」「ファンタジー」へと越境し続けるのと似ている。IPの寿命を延ばす鍵は、「器(ジャンル)の載せ替え」にある。
4.2. 監督作家性の尊重
大手のフランチャイズ映画でありながら、監督の「作家性」を殺さなかったことも勝因だ。 トラクテンバーグの得意とする「閉鎖空間(今回は精神的な閉鎖性)での心理戦」を、ブロックバスターの規模でやらせた。 「IPのルール」よりも「監督のビジョン」を優先する。この英断がなければ、本作は凡百の続編に成り下がっていただろう。
結論:これは「怪獣映画」の未来である
『プレデター:バッドランド』は教えてくれた。 モンスター映画において、怪物はただの「障害物」ではない。彼らもまた、物語を背負う「主人公」になり得るのだと。
ナヴィのような美しいアバターでなくてもいい。醜悪な顔をしたプレデターであっても、その背中に「哀愁」と「生きる意志」を背負わせれば、観客は涙を流す。 これは、我々がこれから作る『温泉シャーク』の続編や、新たな怪獣映画において、目指すべき頂のひとつだ。
派手な爆発も、安易なジャンプスケア(びっくり演出)もいらない。 必要なのは、荒野に一人立つ孤独なシルエットと、それを切り取る覚悟のあるカメラだけだ。
![プレデター:バッドランド 4K UHD + ブルーレイ セット(スチールブック仕様) [Blu-ray]](https://gotoatami.com/wp-content/uploads/2026/01/61wHh2BqbL._AC_-292x300.jpg)
![プレデター:バッドランド ブルーレイ + DVD セット [Blu-ray]](https://gotoatami.com/wp-content/uploads/2026/01/81FU8jp6beL._AC_SL1500_-242x300.jpg)