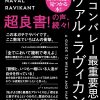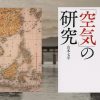Contents
1.はじめに
ホラーというジャンルは映画史を通じて常に人気を博してきました。その中でも“ファウンド・フッテージ(Found Footage)”や“POV撮影(Point of View)”と呼ばれる手法は、ドキュメンタリー風のリアルタイム映像でありながらフィクション作品として成立している独特のスタイルを持ち、観客に強烈な没入感と恐怖感を与えてきました。
この手法は、1999年に公開された「ブレア・ウィッチ・プロジェクト(The Blair Witch Project)」によって一躍メジャーな存在となり、その後多くのホラー作品に取り入れられてきました。一方、2007年にスペインで公開された「REC」は、狭いアパート内における感染パニックと不気味な宗教的背景を絶妙なバランスで融合し、ホラー映画の新たな流れを決定づけた秀作として知られています。
さらに日本に目を向けると、2017年公開の「カメラを止めるな!」は、低予算ながら“ワンカット風”の撮影と巧妙なメタ構造を組み合わせ、爆発的なヒットを記録しました。表面的には“ゾンビ映画”らしい企画の体裁をとりながらも、そこにこめられた映画愛や物語構成の妙が大きな話題を呼んだのは記憶に新しいところです。
本稿では、これら3つの作品を軸に、それぞれがどのように“ファウンド・フッテージ”や“POV的手法”を使っているかを整理しながら、「REC」がいかにしてホラー映画の歴史に特別な地位を確立しているのかを考察していきます。
2.「REC」とは何か —— スペイン産ホラーの新潮流
2-1.概要と製作の背景
「REC」は2007年にスペインで公開されたホラー映画で、監督はジャウマ・バラゲロ(Jaume Balagueró)とパコ・プラサ(Paco Plaza)の共同監督。主演はマヌエラ・ヴェラスコ(Manuela Velasco)で、彼女が演じるTVリポーターのアンヘラが、ある古いアパートで取材中に奇怪な事件に巻き込まれるというストーリーです。
本作のタイトルである“REC”はビデオカメラの録画状態を示す“REC”ランプからきており、カメラが回り続けるという行為そのものが物語のドキュメンタリーテイストを強化する重要なモチーフとなっています。公開と同時にスペイン国内で大ヒットを記録し、その後世界各国に輸出され、日本でも熱狂的なホラーファンを中心に人気を博しました。さらにハリウッドでリメイク版「Quarantine」(2008年)も製作されるなど、短期間で国際的な注目を集めた作品でもあります。
2-2.スペインホラーの系譜と「REC」
スペインはギレルモ・デル・トロ(Guillermo del Toro)が監督した「デビルズ・バックボーン」や「パンズ・ラビリンス」の製作に影響を与えた国でもあり、独特の“オカルト性”や“幻想性”の強いホラー文化を培ってきた土壌があります。欧米の巨大スタジオの影響が比較的少ないことから、個性的で大胆なホラー作品が生まれやすいとも言われています。
ジャウマ・バラゲロは「ダークネス」や「ザ・スリーピング」などの作品で、すでにスペインホラー界の新鋭として注目を集めていました。一方のパコ・プラサもホラー畑で活躍しており、2人がタッグを組んだことで独自の“密室感染パニック+超自然的恐怖”を描き出す「REC」のスタイルが確立します。作品内で描かれるのは、伝統的なゾンビ映画やウイルス感染映画に通じるものだけでなく、スペイン特有のカトリック的寓意が深く関係している点が注目されます。
2-3.物語のあらすじ(ネタバレ最小限の概要)
アンヘラは、深夜に消防署を取材するTVレポーター。彼女の番組は「深夜の消防24時」的なリアリティ・ショーを想起させる作りで、消防士の日常に密着して視聴者の興味を引きつけようとしています。そんななか、アパートで奇妙な老女が暴れるという通報が入り、アンヘラとカメラマン、そして消防士たちが現場へ急行。ところが、アパートに足を踏み入れた途端、謎の感染症が蔓延し始め、住民たちが次々に凶暴化。さらに外部からはアパートが封鎖され、脱出不能の状況へと追い詰められていきます。
舞台はアパートの内部にほぼ限定され、カメラの視界だけが映画の視界。物語が進むほどに、なぜこのアパートが感染源になったのか、その背後にある悪魔的・宗教的な根拠は何か、といった要素が浮かび上がります。これが単なるパニックホラーではなく、怪異やオカルト色の強い作品へと展開していく大きな魅力の一つとなっています。
2-4.「REC」の特徴的な恐怖演出
「REC」における最大のポイントは、カメラが常に回り続けるという演出です。POV視点の手ブレ感や閉塞的なアパートという舞台は、観客を登場人物と同じ立場に置き、息苦しい臨場感を作り出します。また、感染や憑依といったテーマを扱っているため、生理的恐怖と超常的恐怖の境界があいまいに混ざり合い、視覚的にも精神的にも強いインパクトを与えます。
さらに、登場人物たちの視点がメディアの取材カメラに設定されている点も重要です。テレビという公共の場に向けた“ライブ感”のある映像と、アパート内部という私的な空間の不気味さが絶妙にコントラストを生み出し、観客は「自分がいま実際にこの状況を目撃しているのではないか」という錯覚に陥りやすくなります。こうした演出手法こそが、「REC」を強烈なファウンド・フッテージ型ホラーとして確立した要因と言えるでしょう。
3.「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」——“フェイクドキュメンタリー”の衝撃
3-1.公開当時の社会的インパクト
「ブレア・ウィッチ・プロジェクト(The Blair Witch Project)」は、1999年に公開され、一大ムーブメントを巻き起こした作品として知られています。監督はダニエル・マイリック(Daniel Myrick)とエドゥアルド・サンチェス(Eduardo Sánchez)。わずか6万ドルほどの超低予算で制作されたにもかかわらず、全世界で2億ドル以上の興行収入を稼ぎ出したことでも有名です。当時はインターネットが一般化しはじめた時期で、口コミの力を最大限に活かしたマーケティング戦略が功を奏しました。「これは本当に起きた事件を元にしたドキュメンタリー映像だ」という“フェイクドキュメンタリー”感が人々の好奇心を煽り、社会現象にまで発展したのです。
3-2.ストーリー概要と演出
物語は、魔女の伝説が残る森にドキュメンタリーを撮りに行った3人の学生が消息を絶つ、という設定。その後、彼らが残した映像が発見され、そこに何が映っていたのか、という体裁で映画が進行します。実際に劇中の映像は、出演者自らが手持ちのカメラで撮影したため、極度に手ぶれが多く、映像は粗く、不安定。そのリアル感が視聴者に“本物かもしれない”という疑念を抱かせる強力なフックになりました。
3-3.ジャンルとしての“ファウンド・フッテージ”確立
「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」は、“ファウンド・フッテージ”をメインの視点として展開する映画の先駆者として世界的に認識されるようになります。もちろん「カニバル・ホロコースト」など、1980年代以前にも類似の形式を取った作品は存在しましたが、これほど大きく市場にインパクトを与え、商業的成功を収めたのは「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」が初めてでした。
その後、ホラー映画だけでなくSF映画やコメディ映画など、多ジャンルにもファウンド・フッテージの波が広がり、2000年代後半には「パラノーマル・アクティビティ」シリーズなどが続々とヒット。映画制作の新たなフォーマットとして定着するきっかけを作った点で、ホラー史に残る重要作品と言えます。
4.「カメラを止めるな!」——メタ構造と映画愛が融合した日本発の快作
4-1.作品概要と驚異的な成功
「カメラを止めるな!」は、2017年に上田慎一郎監督によって製作された日本映画です。通称「カメ止め」と呼ばれ、公開当初はわずか2館のみの超小規模スタートでしたが、口コミで評判が広がり、最終的には全国的なロングランヒットを成し遂げました。作品のテーマは一見“ゾンビ映画”の撮影現場を舞台としたホラーコメディのように見えますが、実際には映画制作の裏側を描いたメタ構造であり、さまざまな仕掛けが盛り込まれています。
4-2.ワンカット“風”撮影とフェイクドキュメンタリー的演出
「カメ止め」の冒頭約37分は、あたかもノーカットで撮影されたかのように見える長回しシーンで構成されています。俳優たちがゾンビに襲われながらも撮影を続ける姿は、観る者に“これは本当にドキュメンタリー? それともフィクション?”と混乱を与える仕掛けとなっています。実際には後半でその舞台裏が次第に明かされていき、「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」や「REC」と同じように“カメラが回っている”という設定自体がストーリーに組み込まれているのです。
4-3.メタ映画としての楽しみ方
「カメ止め」は、映画の後半でそれまで観てきたワンカット映像がどのように作られたのかを明かす“二重構造”が大きな魅力になっています。ここに登場する登場人物たちは、劇中劇の中でゾンビ映画を撮っているキャストでもあり、実際には映画を作っている人々という二重の立場にある。観客はこのプロセスを同時に見届けることで、単なるホラーコメディにとどまらず、映画を撮る側の苦労や情熱を共有する体験が得られます。
4-4.「REC」との共通点と相違点
「REC」との共通点は、“カメラを止めずに回し続ける”という状況設定を通じて、登場人物と観客を強い緊張状態に置くことにあります。ただ、「REC」が純粋なホラー映画としての恐怖演出に特化しているのに対し、「カメ止め」はホラー的演出を逆手に取り、コメディ・メタ・ヒューマンドラマへと展開させている点が大きく異なります。ですから、両者を並べて観ることで、ファウンド・フッテージ的手法がいかに多様な表現の可能性を持っているかがわかるでしょう。
5.“ファウンド・フッテージ”という形式の魅力と恐怖
「REC」「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」「カメラを止めるな!」に共通するキーワードとしては、“ファウンド・フッテージ”あるいは“POV視点”という要素が挙げられます。これらはいずれも「観客がカメラの向こう側にいる」というリアルタイム感を重視し、登場人物の声や息づかい、さらには偶然映り込むかもしれない何か得体の知れないものまで含めて、大きな臨場感を生み出します。
5-1.“視点”の力学
通常の映画撮影では客観的視点(第三者視点)が中心となり、観客は“カメラ”という目を通じてストーリーを観察する立場になります。しかし、ファウンド・フッテージ型では登場人物が手持ちのカメラを回しているため、視点が主観的、かつ不安定です。観客はまるで自分自身がカメラマンになったかのような錯覚を覚え、登場人物と共に“いま起きていること”に巻き込まれているという感覚を味わいます。
5-2.観客の没入感と恐怖
ホラーの場合、こうした没入感が恐怖体験をより増幅します。わざと画面を暗くしたり揺らしたりすることで、視界が制限され、何が起こっているのか見えにくい。その“不安”こそがホラーの根幹であり、さらに「REC」のように舞台が密室(アパート内部)に限定されている場合、音や声の響きが生々しく、逃げ場のない恐怖が強調されます。
5-3.フェイクドキュメンタリーとの境界
ファウンド・フッテージ型の映画は、しばしば“フェイクドキュメンタリー”と混同されがちです。実際に両者の境界線は曖昧で、物語の体裁として“これは実際の映像です”という体を取ることも多いです。「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」のマーケティング戦略のように、その“フェイク”を売りにすることも大きな効果を生みます。一方で「カメラを止めるな!」のようにメタ構造を取り入れながらも、明らかにフィクションとして提示しつつ、あえて“ドキュメンタリー風”に見せる場合もあるわけです。
この形式のポイントは、観客が「これはフィクションだ」と頭では理解していても、その視覚的・聴覚的なリアル感、目撃感が心理的に本物と疑わぬような恐怖を誘発するという点にあります。とくにホラーにおいては、見えない何かが“あえて見えにくく”映ることで、観客が自らの想像力で最悪の事態をイメージしてしまうわけです。
6.「REC」のストーリー構造・演出の特徴
「REC」は約78分と比較的短い上映時間ですが、その中に凝縮された緊張感と恐怖演出は特筆に値します。その構造と演出上の主な特徴をより掘り下げてみます。
6-1.実況リポートという枠組み
冒頭でアンヘラがテレビ番組の収録をしている映像が入り、我々は“彼女の番組”を視聴しているかのように導入されます。しかし、その日常的な取材の雰囲気が徐々に崩壊し、アパートの閉鎖と感染パニックへとつながる流れが非常にスピーディー。序盤に設定された“深夜の消防署リポート”というごく普通のシチュエーションが、逆にこの後に待ち受ける地獄絵図との落差を強調します。
6-2.密室劇としての要素
舞台となるアパートは決して広くありません。階段、廊下、各部屋のインテリア、老朽化した造りなど、スペインの古い建築物独特の趣がある一方、それが逃げ場の少ない構造を作り出し、一度混乱が始まればもはやどうにもならない、という閉塞感を生んでいます。さらに外部からの隔離措置(バリケードや特殊部隊の突入など)が物語に緊張感を与え、観客は登場人物と同じく「閉じ込められた」という絶望を追体験させられます。
6-3.感染ホラーと悪魔的オカルトの融合
「REC」は最初、感染パニックホラーのように見えます。しかし終盤になると、実はこれが単なるウイルス感染ではなく、悪魔や悪霊的な存在が関与しているかもしれない、ということが示唆されていきます。特にラストに登場する“最上階”の部屋には、ある神父の日記や奇妙な資料が残されており、そこからカトリックにおける悪魔憑きなどが暗に連想されるのです。この展開が、「ゾンビ映画」でもあり「オカルト映画」でもある二重の恐怖をもたらし、作品世界に奥行きを与えています。
6-4.演出面の工夫
映像はほとんどカメラマンの撮る映像のみで構成されるため、画面切り替えが少なく、常に手ブレや被写体の見切れを伴います。そこにリアルタイムで起こる悲鳴、銃声、血飛沫、慌てふためく人々の様子が重なり合っていく。観客はそこで起こっている出来事を“自分の身に起こること”として感じやすくなるため、心理的な負荷は非常に高くなります。暗闇に切り替わる赤外線モードの演出なども含め、視界が利かない中でうごめく“何か”がいつ襲ってくるかわからない恐怖は、まさにこの手法ならではといえます。
6-5.台詞と情報の提示
「REC」では、次々と登場人物が恐怖に巻き込まれていくため、観客に与えられる情報も断片的。何が原因で、いつからどのように感染が始まったのかは、住民や消防士、警官、さらに外部の防疫チームなどの言動から間接的に推測するしかありません。こうした情報の希少性が観客の焦燥感をさらに煽り、最後までスクリーンから目が離せない構造が作り上げられています。
7.「ブレア・ウィッチ」「カメ止め」との比較
7-1.舞台設定と狭さ
- 「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」は森という広大な空間にもかかわらず、カメラが捉える範囲は極端に制限され、まるで暗闇がすぐそばまで迫っているかのような息苦しさがありました。一方、「REC」は閉鎖的なアパートという“本当に狭い”密室空間であり、その分、恐怖の襲来がワンテンポ早く、逃げ道のなさを強調している点でより直接的な恐怖を生み出しています。
- 「カメラを止めるな!」も主に廃墟のような施設が舞台となりますが、実際には長回し撮影の裏側を見せる別の空間も存在し、“舞台裏”自体が作品のもう一つの舞台となっています。
7-2.物語の進行スタイル
- 「ブレア・ウィッチ」はドキュメンタリー撮影が徐々に悲惨な状況へと転落していくのに対し、「REC」は消防士の取材から一瞬にしてホラーへ転落するスピード感が際立ちます。
- 「カメ止め」の場合、最初のワンカット部分がいわば“ホラー映画”を演じているパートであり、後半にその裏側を種明かしすることでコメディやドラマとしての側面が強くなる。ストーリーの進む方向性が大きく転換するのが特徴です。
7-3.演出意図とテーマ
- 「REC」は感染・悪魔憑きというダブルの恐怖を描くことで、現実的パニックとオカルトホラーが融合したかたちになっています。
- 「ブレア・ウィッチ」は魔女伝説をめぐる伝承を背景に、人間の根源的な恐怖(暗闇、孤立、不明)を描き、“未知への不安”を強調。
- 「カメ止め」はホラーの形式を借りながら、どちらかと言えば“映画作りの熱意”や“チームワーク”をテーマにしており、観客が最後に得る感情は感動や爽快感に近いものです。
7-4.残酷描写やゴア表現
- 「REC」はゾンビ的な襲撃シーンや血まみれの住民など、グロテスクなビジュアルが前面に出ます。モンスターホラー的要素が強いとも言えます。
- 「ブレア・ウィッチ」は、画面に明確なモンスターや流血がほとんど映らず、音響と視覚の制限で恐怖を煽る手法がメインです。
- 「カメ止め」はゾンビメイクや流血シーンがあるものの、あくまでも“撮影小道具”としての要素が大きく、ホラー的にはコメディ寄りの演出が多いです。
このように三作品はそれぞれ共通点を持ちつつ、目指す恐怖の方向性やテーマ性が大きく異なるのがわかります。「REC」はその中でも“ホラーのど真ん中”を突きつつ、カメラ視点による臨場感、感染パニックという社会的恐怖、そして悪魔的オカルトという超常的恐怖を兼ね備えた“欲張り”な作品として際立ちます。
8.「REC」シリーズ全体に見る展開と解釈の広がり
「REC」は1作目の大ヒットを受け、その後続編や派生作品が作られ、シリーズ化していきます。以下では簡単に各作品の方向性を整理します。
8-1.「REC 2」(2009年)
1作目の直接的な続編。アパートが封鎖された状態から特殊部隊と医師(神父)が内部に突入し、事件の真相に迫ります。ここでは宗教的な悪魔憑きの設定がより明確に描かれ、ウイルス感染と悪魔的存在が密接に絡み合っていることが確認されます。アクション要素も増し、POVスタイルも引き続き維持されました。
8-2.「REC/レック 3 ジェネシス」(2012年)
パコ・プラサが単独で監督。舞台が結婚式場へと移り、“アパート外”の感染拡大が描かれます。本作はシリーズの中でやや毛色が違い、コメディ要素も含まれ、POV形式から普通の撮影方式へ途中で切り替わるという実験的要素が取り入れられました。賛否両論もありましたが、監督自身は意図的に様式を変える試みをしたと語っています。
8-3.「REC/レック 4 ワールドエンド」(2014年)
ジャウマ・バラゲロが単独で監督。舞台は洋上の隔離船で、シリーズの“完結編”として位置づけられました。1作目の主人公アンヘラ・ヴィダルが再び登場し、感染や悪魔憑きの真相に迫ります。作品としてはアクションホラー色が強まり、ファウンド・フッテージのスタイルも薄れています。
このように、シリーズが進むにしたがって作品の方向性は大きく揺らぎ、特に「REC 3」以降は必ずしもファウンド・フッテージを中心とした演出にはこだわっていない点が注目されます。ただ、シリーズを通じて“悪魔的感染”やアンヘラというキャラクターが一貫して物語を牽引していることから、1作目で示唆された世界観が拡張されていく形で解釈の余地が広がっていると言えるでしょう。
9.「REC」がもたらした影響と“ファウンド・フッテージ”の現在
9-1.2000年代後半のファウンド・フッテージ・ブーム
「REC」が2007年に公開された後、2009年頃からはファウンド・フッテージ形式のホラー作品が世界的に増加しました。「パラノーマル・アクティビティ」シリーズ(2007年初作、広く公開は2009年以降)、「クローバーフィールド HAKAISHA」(2008年)、「アポロ18」(2011年)など、低予算でも工夫次第で大きな興行収入を得られることが実証され、“POV撮影”は一時期のトレンドとして確立します。なかでも「REC」は欧州発の同手法のホラー成功例として代表的な地位を確立しました。
9-2.ホラー以外のジャンルへの展開
ファウンド・フッテージはホラーと相性が良いとされる一方、ドキュメンタリー風のリアルさから、SFや戦争映画、さらにはティーン向けのドラマにも応用が進みました。たとえば「クロニクル」(2012年)では超能力を得た高校生たちの視点で物語が進むという形でファウンド・フッテージが採用されています。“低予算でもアイデア次第でリアリティを出せる”という点が最大の利点といえます。
9-3.“ファウンド・フッテージ”の強みと限界
ファウンド・フッテージは効果的に使えば観客の没入感を高める一方、カメラの動きを制限しすぎるとストーリーが見えにくくなる、映画としての視覚的な演出に制約がかかる、といった弱点もあります。さらに手ブレや暗闇が多い映像は3Dや4Kといった映像技術の進歩に馴染みにくく、しばしば観客が“酔って”しまうという物理的な問題も生じます。
「REC」も続編では徐々にファウンド・フッテージ一辺倒ではなくなり、通常のカメラワークを併用するケースが増えています。こうした変化は、ファウンド・フッテージという手法自体が作品のコンセプトに最適化されているかどうかが重要であることを示しています。つまり、無闇にこの手法を使っても成功しないのです。逆に言えば「REC」は、その最適化に成功したからこそ、あれほど強烈な恐怖体験を生み出せたとも言えます。
9-4.「カメラを止めるな!」とファウンド・フッテージの融合
日本での事例として「カメラを止めるな!」は、ファウンド・フッテージ的な主観映像と、映画制作の“舞台裏”を見せるコメディとを融合させた稀有な成功例です。本作はホラーでありながらも笑いに満ちており、さらに映画づくりの“リアルな苦労”を観客に追体験させるという実験的な楽しさもあります。こうした柔軟な発想でファウンド・フッテージを取り入れる例が増えることで、この手法のジャンル横断的な可能性がより広がっていると言えます。
9-5.リアルタイム配信やSNS時代との親和性
現代はYouTubeやTikTok、さらにはライブ配信が浸透しており、誰もが手軽に“自撮り”や“ドキュメンタリー風”動画を公開できる時代です。ファウンド・フッテージが当初持っていた革新性(手ぶれや素人撮影の生々しさ)は、もはや日常の風景の一部となりました。そのため、近年のホラー作品では単に手持ちカメラ視点を使うだけでは新鮮味が薄れ、さらに一捻りした演出が求められるようになっています。
「REC」が登場した2007年はまだSNSが今ほど一般化しておらず、POVスタイルが新鮮かつリアルに感じられた時代でした。現代の視点から見れば、逆に“ノスタルジック”なドキュメンタリー手法とも言えますが、「REC」の持つ強烈な臨場感と脚本の巧みさは、いまなお多くのホラーファンを惹きつけています。
10.おわりに
総括すると、「REC」は“ファウンド・フッテージ”や“POV撮影”の恐怖演出を極めた作品の一つとして、ホラー史上に強い印象を残しました。そこには「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」が築いた“フェイクドキュメンタリー”の要素、「カメラを止めるな!」が後に提示した“撮影される側のドラマ”などと共鳴する側面があります。ただし「REC」がとりわけ際立っているのは、“感染ホラー”と“オカルトホラー”を融合させ、さらにメディア取材という設定を通じて“撮影し続けること”そのものを恐怖の源泉として描いている点にあります。
小さなアパートの暗闇と狭い階段。消毒液の匂いや血の匂いが漂いそうな息苦しい空間。外界から完全に遮断されたまま暴走する感染被害。そしてラストで待ち受ける、単なるウイルスでは説明のつかない邪悪なる存在——短い上映時間にもかかわらず、これほど多層的な恐怖を詰め込むことに成功した「REC」は、“ファウンド・フッテージ”が持つポテンシャルを最大限に活かした作品と言っても過言ではありません。
「カメラを止めるな!」や「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」と比較すると、より直接的で苛烈なホラー表現を求める観客には「REC」が刺さるでしょう。逆に映画制作の裏側やメタ構造を楽しみたい人は「カメ止め」に強く惹かれ、不可解な怪異や正体不明の森の恐怖に魅力を感じる人は「ブレア・ウィッチ」に惹かれるかもしれません。しかし、それぞれの作品が共通しているのは、“カメラ”というモチーフが恐怖や興奮、驚きを生み出す上で中心的な役割を担っているという点です。
ファウンド・フッテージの手法は今後さらに進化し、SNSやVR、さらにはインタラクティブなメディア表現とも結びついて、新しい映画体験を生み出していく可能性があります。「REC」からもうすぐ20年近くが経過しようとしている今も、その持つ生々しさや恐怖演出は色褪せません。もしまだ鑑賞されていない方がいれば、「ブレア・ウィッチ」と「カメ止め」とあわせて観ることで、ファウンド・フッテージという映画表現の多様性と底知れぬパワーを存分に味わうことができるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。本記事で「REC」という作品に興味を持ち、ファウンド・フッテージの世界へより深く踏み込んでいただければ幸いです。あなたの次なるホラー体験が、より刺激的で忘れがたいものになることを願っています。
![映画REC/レック [Blu-ray]](https://gotoatami.com/wp-content/uploads/2025/02/51hOnusMY4L._AC_-240x300.jpg)
![The [Rec] Collection [Blu-ray]](https://gotoatami.com/wp-content/uploads/2025/02/714OXPxLHUL._AC_SL1500_-229x300.jpg)