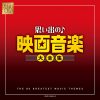Contents
1. はじめに
いまやスマートフォンでコンテンツを視聴することは当たり前となり、TikTokやInstagram Reels、YouTube Shortsといったプラットフォームを通じて「縦動画」が一般的な映像フォーマットとして定着しつつあります。数年前までは、「動画=横長(16:9)」という認識がごく当たり前でした。しかし、近年では縦動画が圧倒的に増加し、特に若年層を中心に当たり前のものとして受容されるようになっています。
この文章では、「縦動画の流行」が単なる一時的な流行や新しい撮影技術の誕生にとどまらず、人類の歴史を振り返ったときにどのような意味を持ち得るのか――すなわち「人類史の流れ」における位置づけについて、多角的な観点から考えたいと思います。たとえば、脳科学や認知科学の領域では、人間の視野や注意配分の仕組みが縦動画に合致するのかどうか、あるいは社会学の側面では、誰もが映像制作・発信を簡単に行えるようになった「メディアの民主化」の観点から縦動画の普及をどう評価できるか、などが論点として挙げられます。
また、映画史・映像史の観点で言えば、昔のサイレント映画や4:3テレビ放送の歴史的変遷を経て、映画館の大画面で活用されたシネマスコープ(シネスコ)の横長比率が標準とされてきた時代が長く続きました。その潮流を見直し、改めて「縦長の映像表現が最適化される現象」には、どのような社会的・文化的背景があるのかを検討する必要があります。
本考察では、学術的知見や専門家による論説を交えつつ、縦動画がもたらす多層的なインパクトを掘り下げてみましょう。
2. 縦動画の登場背景と大衆化
まずは、縦動画がどのように登場し大衆化したのかを簡単に振り返ります。一般的には、スマートフォンが普及し始めた2000年代後半~2010年代にかけて、動画や写真の撮影が手軽に行えるようになったことで、ユーザーの「撮影のしかた」に変化が生まれました。スマートフォンは片手で持って操作することが多いため、自然に「縦向き」のまま撮影をするユーザーが増えたのです。
当初は、縦向きの動画をYouTubeやテレビなど横長のメディアで再生しようとすると画面両端に黒帯が生じてしまい、視聴しにくいという批判もありました。しかし、TikTokやInstagramといったSNSプラットフォームが、初めから「縦画面に特化」したUIを採用し始めると、その不便さは逆に横向き動画に感じられるようになります。フルスクリーン化して、縦のままスワイプして次へ次へと進む体験は、横向きの動画をわざわざ全画面表示し、端末を横向きに回転させる手間を省くものとして支持を集めました。
こうして、縦動画は単に「撮影時の持ち方の都合」から生まれた偶然の産物ではなく、ユーザーの操作感やプラットフォーム設計といった要素が複合的に絡み合って誕生し、大衆化していったと考えられます。ここではまだ「人類史」という大きなスケールの話には至りませんが、少なくともテクノロジーの進化とユーザーの利用スタイルが合致し、縦動画が自然に受け入れられる環境が整いつつあったことは間違いないでしょう。
3. 進化論的視点:人間の視野と身体的制約
3-1. 水平方向の視野が広い「地平線仮説」
生物人類学や進化心理学の議論のなかには、いわゆる「地平線仮説」(horizon hypothesis) という考え方があります。これは、人類の祖先が広大なサバンナ環境で生活していた際、捕食者や獲物を見つけるために「水平に広い視野」が有利だったという仮説です。哺乳類のなかでも、特に霊長類は前方に両目が向いた双眼視を獲得し、距離感を立体的に把握する能力を発達させました。しかし同時に、人間は横方向の動きを察知する必要が高かったとも考えられています。
映画やテレビの画面比率が長い間「横長(ワイドスクリーン)」を採用してきたのは、このような人間の「水平方向への認知的な慣れ」や「自然な視野」を意識していたためだとも言われます(David Bordwell & Kristin Thompson, Film Art: An Introduction, McGraw-Hill)。実際、映画館のスクリーンは広い横長の空間を満たすことで没入感を高めやすく、両端の視界に動きがあれば人間は注意を引かれやすいという特徴があるため、物語の演出にも利用されてきました。
3-2. スマホを「縦」で持つ身体的理由
しかし、スマートフォンは大画面の映像とは異なる身体的制約をもたらします。人間の手の形状を考えると、片手でスマホを操作する際には縦長を維持したほうが安定しやすい。特に親指だけで画面を操作する場合、縦のまま持つとホームボタンや画面上部へのアクセスが容易になります。さらに、SNSやウェブサイトのスクロール動作も縦方向が基本です。これは指を上下に動かすのが最小限の移動で済むからであり、横向きよりも疲労感が少ないという利点があると指摘されています。
認知科学者のスティーブン・コスリン(Stephen M. Kosslyn)や進化心理学者のスティーブン・ピンカー(Steven Pinker)らの議論では、人間は基本的に「モード切り替え」せずに情報を得られる環境を好む傾向があると言われます。スマホの画面をいちいち横向きにするよりも、最初から縦向きで撮影・視聴が完結するほうが、身体的ストレスが少ないのです。こうした進化論的・身体的な背景が、縦動画の視聴環境を「自然なもの」と感じさせる要因になっている可能性は大いにあるでしょう。
4. 社会学的視点:メディア史と縦動画の必然
4-1. 映画・テレビの横長化の歴史
映像メディアの歴史をざっと振り返ると、その多くが横長フォーマットの映像を採用してきました。古いテレビ放送の標準であった4:3から、映画館でのアナモルフィックレンズを用いたシネマスコープ(2.35:1や2.39:1)へ、さらに一般家庭のテレビも16:9というワイドスクリーンへ移行しました。これは、映像技術の進化だけでなく、大衆の映像体験を「より没入的に」「より豊かに」したいという欲求が背景にあります。
横方向への拡張は、人間が左右の視野を広く捉えることに適応している点と親和性が高く、またスクリーンに映し出される情報量を増やすための有効な手段とされてきました(John Belton, Widescreen Cinema, Harvard University Press)。加えて、映画産業の発展期における「他社との差別化戦略」としてもワイドスクリーン化が促進され、より大きく、より広いスクリーンが「魅力的な映画体験」と結びついたのです。
4-2. 個人メディアの台頭とフォーマットの変化
一方で、情報通信技術が爆発的に普及した21世紀は、「個人メディアの時代」と言われます。YouTube、ニコニコ動画、Instagram、TikTok、Facebookなど、多種多様なプラットフォームが登場し、誰もが「発信者」になれる社会が到来しました。かつては映像制作には高額な機材と専門知識が必要でしたが、スマートフォン1台あればHD、さらには4K画質の動画まで撮影できるようになったことは、映像のフォーマットやスタイルを大きく揺さぶっています。
社会学者のマニュエル・カステル(Manuel Castells)は、ネットワーク社会において情報が「水平に流通」するようになると、既存のメディア構造やパワーバランスが変わると指摘しました (The Rise of the Network Society, Wiley-Blackwell)。縦動画の隆盛は、まさにその「水平化」の逆説的な帰結でもあると考えられます。横長=テレビや映画のプロ仕様、縦長=スマホで誰でも撮る個人仕様、といったイメージの変化が新たな文化を作り上げたのです。
また、SNS上での動画コンテンツは「大量かつ高速」に消費される傾向があります。1本あたり数秒から数十秒といった短尺の動画が氾濫し、ユーザーはスワイプやタップでテンポよく次へ次へと移動します。この消費形態とユーザーのリズム感に合致しているのが縦動画というフォーマットであることは間違いないでしょう。
5. 脳科学・認知科学的視点:情報処理と「短尺」の魅力
5-1. 縦動画と視覚的注意の集中
人間の脳は視覚情報を処理する際、まず「中心視野」に最も注意を払います。縦動画の場合、画面の中央に被写体や重要な情報を配置しやすく、ユーザーも注目すべきポイントを見失いにくいというメリットがあります。横長の映像では左右に情報が分散されるため、注意が拡散しやすいとされますが、縦動画では「上下方向」のみでフレームが閉じられ、かつスマホを握る手と視線の移動がほぼ直線的に繋がるため、注目すべき領域が自ずと限られてくるわけです。
心理学者のダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)は「注意と意識のリソースは有限である」という前提に基づき、情報を効率的に処理する仕組みを脳は常に探していると述べています (Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux)。縦動画は、スクリーンの視野そのものがコンパクトで、加えて上下移動のスクロールですぐに新たな刺激を得られる構造を持つため、脳にとって「疲れにくい」あるいは「飽きにくい」形態だと考えられます。
5-2. 短尺動画とドーパミン報酬サイクル
脳科学の研究によれば、人間は「新しい情報」を得ると快感を感じやすく、次なる新情報を求める欲求(探索行動)を高めるドーパミン報酬システムを持っています。縦動画プラットフォームであるTikTokやInstagram Reelsは、1本1本の動画が非常に短く、次へスワイプするだけですぐに新しいコンテンツを視聴できるという設計になっています。
これはギャンブルやSNSの「いいね」などと同様に、報酬予測と報酬の獲得が不規則な間隔でやってくるスキナー箱的な仕組みに近いと言われます(B. F. Skinner, The Behavior of Organisms)。ユーザーは常に「次の動画」を期待し、飽きることなく延々とスクロールを続けてしまうのです。縦動画が脳の「報酬システム」を刺激しやすい形態であることは、現代人の生活スタイルを大きく変えつつあります。
6. 縦動画と「メディアの民主化」
6-1. プロとアマチュアの境界崩壊
かつて映像制作は撮影機材のコストや編集技術の敷居が高く、プロの映像制作者とアマチュアの境界は明確でした。しかし、スマホの普及によって、少なくとも「撮影」という行為自体は多くの人にとって「日常」の一部となりました。YouTubeの台頭によって、個人が映像を配信し、場合によっては広告収益を得ることも珍しくありません。TikTokやInstagram Reelsの時代になると、さらに短尺化され、字幕やエフェクトもアプリ内で簡単に施せるようになり、編集技術のハードルすら大幅に下がっています。
こうした流れは「メディアの民主化」と呼ばれることがあります。横長の映像がプロの象徴(映画やTV番組)として受容されてきたのに対し、縦動画はスマホという個人デバイスからの発信がメインストリームとなったことによって、プロとアマの境界を一気に曖昧にしてしまいました。ソーシャルメディア研究の分野では、縦動画は「視聴者との距離が近い」フォーマットだと評されます。たとえばLive配信で縦動画を使うと、視聴者とのチャット欄が同一画面にスムーズに収まり、モバイル端末での視聴体験を損なわないといった長所があります。
6-2. 縦動画の「身体感覚」
興味深いのは、縦動画が「個人の視点そのもの」を強調しやすいという点です。横長のフレームは、ある程度「第三者視点」「俯瞰視点」を想起させますが、縦動画はスマホを手に持って自撮りする際にも自然であり、撮影者の存在感や視点が濃密に反映されやすいフォーマットです。近年注目される「Vertical Cinema」も、一種のアート表現として映像作家の間に広がりつつあり、「縦の画面でこそ表現できる身体性」や「重力と垂直の関係」をテーマにする作品も生まれています。
美術家・映像作家のヒト・シュタイエル(Hito Steyerl)は、現代の映像消費を分析する中で「垂直」への注目を呼び掛けています。これは監視カメラ、ドローン映像、スマホ撮影、縦スクリーンなど、あらゆる映像が「垂直軸の再編」によって新たな意味や権力構造を生んでいるという問題提起です。シュタイエルの論考によれば、縦動画は単に個人の発信ツールではなく、私たちの視野や空間認識そのものを組み替える可能性を含んでいるのです。
7. 人類史の流れから見る縦動画の意味
7-1. 情報伝達の歴史:より速く、より短く、より直感的に
人類史を大きく俯瞰すると、情報伝達の手段は文字から始まり、やがて印刷技術の発明により書籍や新聞が普及し、それがラジオ、テレビ、インターネットへと発展してきました。映像の歴史だけ見ても、サイレント映画からトーキー(音声付与)、白黒からカラー、フィルムからデジタルへと絶えず進化を遂げています。そして最近の傾向としては「より短尺、より刺激的、より簡便」なコンテンツが好まれるようになり、人々の生活リズムやライフスタイルに合致していると分析されます。
メディア研究者のレフ・マノヴィッチ(Lev Manovich)は、デジタルメディアは「モジュール化と変換の自由度」を高めることで、ユーザーの関与を促すと指摘します (The Language of New Media, MIT Press)。縦動画の爆発的普及は、この「変換の自由度」が極限まで高まった状態、つまり誰でも撮影・編集・配信できるインフラが整い、なおかつユーザー自身が「短い時間のスナップショット」を好む文化へ移行した表れともいえるでしょう。
7-2. 「瞬間消費の文化」と縦動画
現代は情報過多の社会であり、一日に受け取るコンテンツの量は歴史上例を見ないほど膨大になっています。SNSのタイムラインやおすすめフィードは「新しい情報」で常に満たされ、ユーザーは「次、次、次」と絶え間なく更新されるコンテンツを求めます。おもしろい動画であっても30秒ほど視聴して興味を失えば、すぐにスワイプして次の動画へ移動するような行動様式が広く見られます。
こうした「瞬間消費」の文化は批判的に見れば「注意力の散漫化」を招きますが、別の視点からは「瞬発的な創造性」や「瞬間的な情報伝達」の可能性を開いたとも評価できます。縦動画はまさにその「瞬間消費」に特化したフォーマットであり、サバンナ時代の視覚特性から離れた新たな視覚体験を生み出しているのかもしれません。脳科学・進化論的にはまだ歴史の浅い現象なので確定的には言えない部分も大きいですが、この「情報の瞬間消費と縦動画の親和性」は注目に値するでしょう。
8. 今後の展望:AI、メタバース、そして縦or横の行方
8-1. AI生成コンテンツとの融合
近年はAI(人工知能)によるコンテンツ生成がめざましく発展しています。画像生成AIや文章生成AIが一般化し、動画生成AIも徐々に登場しています。ユーザーがテキストを入力すれば数秒で動画が生成されるような時代が到来すれば、縦横のフォーマットがどのように選択されるかも大きく変わってくるでしょう。たとえば、TikTokやInstagramなど縦動画が優位なプラットフォーム向けに自動的に動画を生成・編集してくれるサービスが普及すれば、縦フォーマットはさらに強固な地位を築く可能性があります。
一方で、横長の高解像度動画を作りたいという需要は映画館やホームシアター、テレビ放送など依然として存在します。プロ向け制作ツールは当面は横長(16:9ないしはシネマスコープ)のフォーマットを標準として残すでしょう。この「プロ仕様」か「個人向け」かという軸で、縦と横がこれからも併存する形は続くと思われます。
8-2. メタバース空間における映像体験
将来のインターネットはメタバースへと進化するとも言われます。3D空間やVR/AR技術の発展に伴い、視点が固定された映像の概念そのものがアップデートされる可能性があります。メタバースでは、ユーザーはアバターとしてバーチャル空間を歩き回り、自由な視点でコンテンツを体験します。この時、従来の縦横の画面比率という概念がどこまで意味を持つのかは未知数です。
しかし、今のところスマートフォンは世界的に見ても圧倒的な普及率を誇るデバイスであり、メタバース空間においても「スマホから参加する」というスタイルは重要であると考えられます。そうすると、スマホユーザー向けにインタフェースを最適化する際、縦の映像ウィンドウを使うことが依然として有力な選択肢になるかもしれません。メタバースが普及してもなお、人間の身体とデバイスの相性は縦向きが自然かもしれないのです。
8-3. 縦と横の「区別自体」の再考
そもそも映画史の初期には、横長・縦長を絶対的に区別する概念がまだ固まっていなかったとも言われます。黎明期の映写機やフィルムフォーマットはさまざまな仕様が混在していましたが、商業的な理由や鑑賞環境の標準化によって徐々に「横長」が主流化しました。現代においてもSNSの仕様やデバイス特性が変化すれば、いずれ新たな比率が主流になるかもしれません。縦横という二元論の枠を超え、正方形や円形、あるいは折りたたみスマホ向けの可変比率など、将来的には多様な映像表現が模索されるでしょう。
9. 結論:縦動画は人類史における新たな座標点
縦動画の流行は一時的なブームというよりは、人類史における「情報消費の形態が変化する必然的な流れ」の一部だと考えられます。進化論的観点からは、元々人間の視野は横方向に広いと言われるものの、スマホという携帯性・操作性の要請が新たな映像フォーマットを後押ししました。社会学的観点からは、メディアの大衆化と誰もが簡単に映像発信をできる社会構造の変化が、縦動画を「個人のメディア」に位置づけています。脳科学的には、縦動画は注意の集中やドーパミン報酬サイクルを刺激しやすい仕様であり、現代人が「中毒化」しやすいプラットフォームを成立させました。
さらに歴史的に見れば、メディアの進化は常に「より早く、より手軽に、より多くの人へ情報を伝える」方向を志向してきました。その帰結として登場した縦動画は、まさに「個人レベルの発信」が「瞬間消費」と組み合わさった象徴的なメディア形態と言えます。こうした流れはAIやメタバースへの移行によって、今後さらに変化し続けるでしょう。
ここで述べた考察を総合すると、縦動画という現象は「縦か横か」という単純な対比を超えた、人間の身体感覚や認知機能、メディアの民主化、社会の情報消費スタイルなどを包括的に示唆する重要なトピックです。将来的には「縦動画」という言葉自体が消え、単に「動画」と呼ばれるようになるのかもしれませんが、それが訪れるまでは縦動画は人類史に刻まれる新たな座標点であり続けるでしょう。
10. 参考文献・関連文献・専門家の見解
- David Bordwell & Kristin Thompson, Film Art: An Introduction, McGraw-Hill.
- 映画のフレーミングやワイドスクリーンの歴史についての基礎的な解説。
- John Belton, Widescreen Cinema, Harvard University Press.
- 映画におけるワイドスクリーン化の技術的・歴史的展開を分析した名著。
- Lev Manovich, The Language of New Media, MIT Press.
- デジタルメディアにおける「モジュール化」と「変換の自由度」を理論的にまとめた古典的研究。
- Manuel Castells, The Rise of the Network Society, Wiley-Blackwell.
- ネットワーク社会とメディア構造の変革、個人が情報発信主体になるプロセスを論じた大著。
- Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux.
- ヒトの認知システムや注意資源の有限性などを扱い、縦動画がどのように「意識の切り替え」を誘発するかのヒントとなる。
- B. F. Skinner, The Behavior of Organisms.
- 行動主義心理学の古典。ドーパミン報酬サイクルとの関連でスキナー箱の仕組みを参照できる。
- Stephen Pinker, How the Mind Works, W. W. Norton & Company.
- 進化心理学的な視点でヒトの認知や行動様式を考察。スマホ操作の身体感覚と照らし合わせる際に示唆がある。
- Hito Steyerl, “In Defense of the Poor Image,” e-flux journal (2009).
- デジタル時代の映像の質や垂直性などを問題提起する美術家・映像作家による論考。
- Ann Friedberg, The Virtual Window: From Alberti to Microsoft, MIT Press.
- 「窓」としてのスクリーン概念を歴史的に振り返る。縦横比の変化も含む映像フレームの意味を探るのに参考になる。
これらの文献や論考では、必ずしも「縦動画」に直接言及しているわけではありません。しかし、映像のアスペクト比やメディア史、ネットワーク社会における情報発信の姿を論じる上で、示唆に富む議論や概念が多く含まれています。縦動画の流行を、人類史のなかで起こり得る必然的な文化・技術・認知の交錯点として捉えるためにも、こうした幅広い領域の研究成果を総合して考えることが重要でしょう。