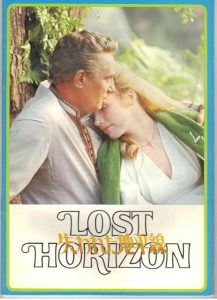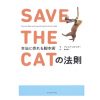Contents
はじめに
1973年にアメリカで公開されたミュージカル映画『失われた地平線』(原題: Lost Horizon)は、作家ジェームズ・ヒルトン(James Hilton)の同名小説と、1937年の同作を映画化したフランク・キャプラ監督作品のリメイク版として位置づけられています。ただし、この1973年版は“ミュージカル”という大きな付加価値を加えた点が大きな特徴であり、単なるリメイクには留まらない試みとして世に送り出されました。しかしながら、この作品はアメリカ国内で酷評され、興行的にも失敗に終わり、現在に至るまであまり語られることがない「隠れた大作」または「失敗作」として扱われることも多いようです。日本においてはさらにマイナーで、知名度が極端に低いとも言われています。
本記事では、そんな1973年版ミュージカル映画『失われた地平線』にスポットライトを当て、作品の概要や見どころ、そしてなぜ日本で広く知られることなく埋もれてしまったのか、といった背景について徹底的に考察していきます。さらに、ほかのバージョン(1937年版や小説)との比較要素、ミュージカルとしての楽曲面、製作時のアメリカ映画産業の事情などにも触れることで、多角的な視点から本作の魅力と問題点を掘り下げてみたいと思います。
作品の基本情報
- タイトル(日本語):失われた地平線
- タイトル(原題):Lost Horizon
- 公開年:1973年
- 監督:チャールズ・ジャロット(Charles Jarrott)
- 原作:ジェームズ・ヒルトン(James Hilton)「失われた地平線」
- 脚本:ラリー・クレイマー(Larry Kramer)
- 音楽:バート・バカラック(Burt Bacharach)
- 作詞:ハル・デヴィッド(Hal David)
- 主な出演者:
- ピーター・フィンチ(Peter Finch) … ロバート・コンウェイ(Richard Conway)
- リヴ・ウルマン(Liv Ullmann) … キャサリン(Catherine)
- サリー・ケラーマン(Sally Kellerman) … サリー(Sally Hughes)
- マイケル・ヨーク(Michael York) … ジョージ・コンウェイ(George Conway)
- ジョージ・ケネディ(George Kennedy) … サム・コーネリアス(Sam Cornelius)
- ボビー・ヴァン(Bobby Van) … ハリー(Harry Lovett)
- ジョン・ギールグッド(John Gielgud) … 高僧(Chang) ほか
製作はコロンビア映画(Columbia Pictures)が手がけ、当初は「壮大なロケーションと豪華な音楽で“新たな名作ミュージカル”を生み出す」という意気込みがあったとされています。しかし公開後は、アメリカ本国では批評家の反応も芳しくなく、興行的にも振るわなかったという経緯があります。
原作・1937年版との関連
● 原作小説について ジェームズ・ヒルトンの小説『失われた地平線』(Lost Horizon)は、1933年にイギリスで出版され、謎めいた理想郷“シャングリラ”という単語を世界に広めた作品として知られています。高山に囲まれたユートピアに迷い込んだ一団が、そこでの生活と理想との間で葛藤する物語は、ヒルトンの美しい筆致によって描かれ、世界的なベストセラーとなりました。
● 1937年版映画(フランク・キャプラ監督) 1937年には名匠フランク・キャプラ監督による同名映画が制作され、こちらは大きな成功を収めました。キャプラらしいヒューマニズムが織り込まれつつ、素晴らしいロケーションと精巧なセットデザインで、当時としては高い評価を得ています。のちにいくつものバージョンが再編集されるなどフィルムの散逸もありましたが、1937年版は「幻の名作」と呼ばれるほどにファンの間では根強い人気を持ち続けています。
● 1973年版でのミュージカル化 こうした背景を踏まえると、1973年版は「オリジナルの魅力+ミュージカル要素」という組み合わせで新たな可能性を探った作品といえます。しかし、その“音楽”という最も特徴的な要素がむしろ賛否の分かれどころになったとも言われます。フランク・キャプラ版をこよなく愛するファンからは、原作・映画の神秘性を薄める行為と見なされ、クラシックなロマンを台無しにしているという手厳しい批判もあったのです。ストーリー概要
ストーリーの大枠は原作・1937年版と同様、イギリスの外交官ロバート・コンウェイとその仲間たちが、チベット奥地(映画版の設定ではアジアの辺境の地)に墜落した飛行機から奇跡的に生き延び、不思議な理想郷“シャングリラ”に導かれるというものです。そこは美しい自然環境と、どこか時が止まったかのような独自の文化が広がる秘境。人々は穏やかに暮らし、加齢の速度が遅いとも噂される不思議な土地です。
ロバートはその地で様々な体験をしながら、「シャングリラが世界にとって何を意味するのか」「人間が本来求めるべき幸せとは何か」という根源的な問いに向き合います。一方で、同行していたメンバーたちは、それぞれが現実世界への未練や、ここでの生活へ疑いを抱くものもおり、作品としては理想郷をめぐる葛藤を中心にドラマが展開されていきます。
ミュージカル要素と楽曲
1973年版最大の特徴はミュージカル化された点にあり、バート・バカラックのメロディとハル・デヴィッドの歌詞が全面的に作品を彩ります。バカラックとデヴィッドのコンビは多くのヒット曲を世に送り出しており、例えばディオンヌ・ワーウィックなどのポップスで馴染み深い名コンビとして知られています。そのため、音楽的には一定の評価をする声もある一方で、映画全体のトーンや演技とミュージカルナンバーが乖離しているという批判も根強いようです。
特に、映画前半から中盤にかけて挿入されるミュージカルシーンは、舞台的な演出ではなく広大なロケーションを背景に撮影されているため、必ずしも「舞台ミュージカルのような一体感」が得られない部分がありました。批評家たちは「ミュージカルシーンが説得力に欠ける」「キャラクターの感情の盛り上がりと音楽が噛み合っていない」などと酷評し、バカラック=デヴィッドの楽曲自体を否定するわけではないものの、映画の中での使われ方が適切でなかったという評価もあったのです。
キャストの魅力と演技
● ピーター・フィンチ ロバート・コンウェイを演じるピーター・フィンチは、当時すでに名優として評価されており、後に映画『ネットワーク』(1976年)でアカデミー主演男優賞を受賞するなど、演技力には定評のある俳優です。本作においても、ロバート・コンウェイが抱える内面の葛藤や、人間味あふれる優しさを表現している点は見応えがあります。一方で、ミュージカルに不慣れな点もあり、歌唱シーンのぎこちなさなどは批判の的となりました。
● リヴ・ウルマン リヴ・ウルマンはイングマール・ベルイマン作品で知られる北欧を代表する女優であり、繊細な演技が評価されていました。本作ではシャングリラで出会う女性キャラクター「キャサリン」を演じ、穏やかな雰囲気をもってロバートたちを迎え入れます。その優しく包み込むような存在感は、シャングリラの持つ優美さと神秘性を体現しているともいえます。ただし、やはり本職のミュージカル女優ではないため、歌唱部分については「本人の魅力を最大限に引き出せていない」といった意見もあります。
● サリー・ケラーマン、ジョージ・ケネディ、マイケル・ヨーク ほか サリー・ケラーマンは『M★A★S★H』(1970年)での活躍で注目を浴びていた時期で、コメディ寄りの役柄もこなせる女優として多才さが評価されていました。ジョージ・ケネディは『キャラバン』や『大空港』シリーズなどでお馴染みの個性的なバイプレイヤーであり、マイケル・ヨークは『キャバレー』(1972年)などで評価を得ていた若手スターでした。こうした多彩な顔ぶれが一同に集結している点は豪華ですが、全員が「ミュージカルに慣れている」というわけではなかったため、作品全体の統一感に課題を残した側面もあったようです。
なぜ失敗とされるのか
- 時代背景とのミスマッチ 1970年代初頭は、アメリカ映画界においても社会の変革期でした。1960年代後半からニュー・シネマの台頭や若年層向けの現実的で過激な作品が注目を浴びるようになり、古き良きハリウッド的な大作ミュージカルはすでに斜陽の時代に入っていました。『サウンド・オブ・ミュージック』(1965年)の大成功はあったものの、70年代は社会派映画やベトナム戦争を背景にした作品、そして新しい形態の娯楽映画が脚光を浴びており、観客が「理想郷でのミュージカル」に魅力を強く感じにくい時代でもありました。
- 原作・1937年版ファンからの拒絶反応 前述のとおり、フランク・キャプラ版に思い入れのあるファンは多く、作品の持つ哲学的要素や神秘性を壊してしまうと感じる人々もいました。むしろ、キャプラ版の改良版やオリジナル復元版を望む声は根強く、本作が代替するどころか「蛇足」とみなされるケースもあったようです。
- ミュージカルとしての完成度への批判 バカラック&デヴィッドの楽曲が名曲であったとしても、「映画の中での演出」としては不発であったという意見が多く見られます。また主要キャストの多くがミュージカル経験をあまり積んでいなかったこと、演出の面でミュージカルとしての一体感を生み出す手腕が不足していたことも、評価を下げる要因となりました。
- 製作費に見合わない興行収益 コロンビア映画は本作にかなりの資金を投下したとされ、当時としても大作扱いでした。しかし、興行収益が振るわず、大きな赤字を計上したことから“失敗作”のレッテルを貼られ、アメリカ映画史上でも不名誉な評価が与えられてしまいます。
日本での知名度の低さ
- 劇場公開の扱いが小規模または不透明 日本国内では、『失われた地平線』1973年版が大々的に公開されたという記録があまり見当たりません。公開当時の宣伝規模が小さかったこと、あるいは二次的にテレビ放映やビデオスルーで出回った可能性があるものの、決定的な話題性を欠いてしまったと言われます。そもそもアメリカ国内での評価も芳しくなかったため、配給会社も大々的に売り出すことに慎重になったのかもしれません。
- 日本におけるミュージカル映画の人気傾向 1970年代の日本でミュージカル映画がまったく人気がなかったわけではありませんが、欧米と比べると「圧倒的な大ヒット」になる例は限られていました。さらに、当時は『サウンド・オブ・ミュージック』や『ウェスト・サイド物語』などの名作がすでに日本でも広く浸透しており、それらに匹敵するほどの話題性が得られなかった可能性が高いです。
- 情報不足・ソフト流通の難しさ ビデオ、DVD、ブルーレイなどのメディアでのリリース状況も極めて限られていたと考えられます。アメリカ国内でもソフトの流通が限られていた時期もあり、字幕版を含め日本市場に公式に流通した回数が少ないとされます。そのため、日本の映画ファンの間でもこの作品に触れる機会自体が非常に限られ、結果として知名度が低いまま埋もれてしまいました。
見どころ・注目ポイント
- 壮大なロケーションと美術セット 本作では、いわゆる「理想郷」としてのシャングリラを構築するために大規模なセットが組まれました。外景は実際のロケ地とスタジオ撮影を組み合わせていますが、雪山に囲まれた寺院風の建物や広々とした庭園、独特の装飾品など、当時のハリウッドのアート・ディレクションが存分に活かされている点は、今見ても豪華で楽しめます。単にCGがなかった時代だからこそ、実物大のセットや美術による迫力は見応えがあります。
- バート・バカラック&ハル・デヴィッドの楽曲 批評家には「映画全体とのミスマッチ」を指摘されたものの、バカラック&デヴィッドのコンビが書き下ろした楽曲自体には独特のメロディやリリカルな歌詞が凝縮されており、個別に取り上げると心地よいポップスとして仕上がっている曲もあります。特に、当時のアメリカン・ポップスを愛するファンからは、このサウンドトラックに一定の評価があるのも事実です。もし本作を鑑賞する機会があれば、ぜひミュージカルナンバーに注目してみてください。
- 豪華キャストの競演 ピーター・フィンチ、リヴ・ウルマン、サリー・ケラーマン、ジョージ・ケネディ、マイケル・ヨークなど、今振り返るとかなりの名優・個性派俳優が集結しています。後々、別の作品で大ヒットを記録したり演技賞を獲得したりする俳優が多いため、彼らが“ミュージカル”という普段とは違うフィールドでどう奮闘しているかを見るのは興味深いポイントでしょう。
- 時代の転換期におけるハリウッド産業の象徴 1970年代前半は、旧来型の大作映画制作が難しくなり、オートゥール型の映画や低予算の反骨精神あふれる作品(いわゆるアメリカン・ニューシネマ)が台頭していく時期でした。そんな中で、本作のような「古き良き大作ミュージカル」の路線を踏襲しようとした試みは、ある種ハリウッドの過渡期を象徴する作品と言えるかもしれません。失敗作と評されはするものの、歴史の一端を知る上では貴重な資料的価値があります。
日本での再評価の可能性
近年、ネット配信サービスなどの普及により、これまでソフト化や上映の機会が限られていた作品が再評価される傾向があります。『失われた地平線』(1973年版)も、今後何らかの形で定期的に上映されたり、映像配信プラットフォームで観られるようになったりすれば、全く新しい世代の観客からユニークな評価を得る可能性があるかもしれません。
とりわけ「バート・バカラックの音楽が好き」「クラシック・ハリウッド映画のセットデザインや衣装を観賞するのが趣味」という映画ファン層にアピールできるポテンシャルは秘めています。作品の評価が「失敗」や「駄作」に偏っているからこそ、逆に掘り起こしてみる面白さは大いにあるでしょう。
埋もれた“野心作”として楽しむ
1973年版の『失われた地平線』は、「大作ミュージカル映画を作ろう」という野心が空回りした面が強く、アメリカ国内外で酷評された経緯は否定できません。そのため、日本では大々的に公開されないまま知名度も低くなり、今に至るまで語られる機会がごく限られてきました。しかし、クラシカルな映画やミュージカルを“再発見”する動きが進む中で、本作の美術や音楽、さらには70年代当時のハリウッドの苦闘などを味わう観点から、今こそ面白い研究材料となる可能性があります。
● ポイントのおさらい
- 原作や1937年版との比較:理想郷シャングリラを描いた名作のミュージカル版という点。
- ミュージカル要素の功罪:バート・バカラック&ハル・デヴィッドの楽曲が魅力的かつ不評の元凶にもなった。
- 豪華なキャスト:ピーター・フィンチやリヴ・ウルマンなど錚々たるメンバーの意外な顔合わせ。
- 時代背景の変化:1970年代のハリウッドは大作ミュージカルが下火となるタイミング。
- 日本での知名度の低さ:公開規模の小ささ、評価不振から来る配給戦略の消極性、ソフト流通の少なさ。
もし今後、この映画を視聴できる機会があるならば、「なぜここまで酷評されたのか」「1970年代のハリウッドが失敗したミュージカルとはどんなものだったのか」という切り口で鑑賞してみると、かえって新鮮な発見があるかもしれません。歴史的に見れば、失敗作と呼ばれた作品だからこそ、その時代の映画産業の考え方や観客の嗜好を映し出す鏡になるのです。
おわりに
同じ原作を基にした1937年版が“名作”として長く愛される一方、1973年版は主にアメリカ国内の批評家や観客から手厳しい評価を受け、日本でもほぼ無名に近い状態で現在に至っています。それでも、当時としては世界的に著名だったアーティスト(バート・バカラック&ハル・デヴィッド)の音楽と、国際的な俳優陣の競演という意欲的な試みが行われた野心作であることは間違いありません。
「失敗作=鑑賞に値しない」というわけでは決してなく、むしろ映画史のトレンドや製作・配給の戦略、観客の嗜好の変化を読み解く上では格好の資料とも言えます。これを機に、本作の存在を知った方がいれば、是非ともその独特な世界観と時代背景を踏まえた上で楽しんでいただければ幸いです。
以上が、1973年公開のミュージカル映画『失われた地平線』に関する考察となります。今後のメディア状況次第では、思わぬかたちで再発掘され、新世代の観客から「実は面白い」「思っていたほど悪くない」という新たな評価を得る可能性も十分あります。「幻のミュージカル映画」として、ひそかにファンの心をつかむ日が来るかもしれません。
※本記事はアメリカの公開当時のレビューや興行成績、製作者・出演者のコメントなど、複数のウェブ上の資料を参考にしつつ執筆しました。情報の正確性には細心の注意を払っていますが、時期やソースにより多少の異同がある場合もあります。