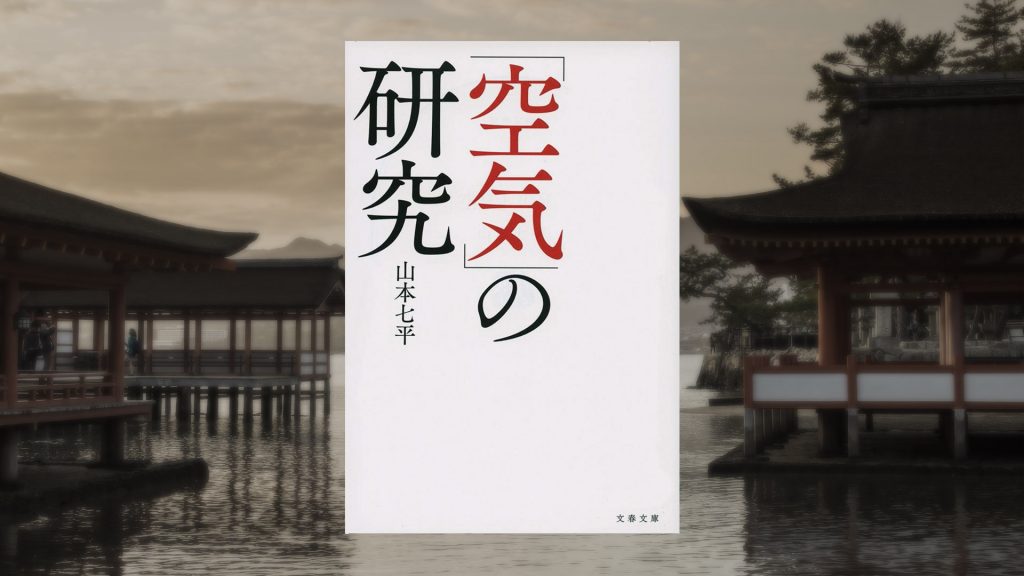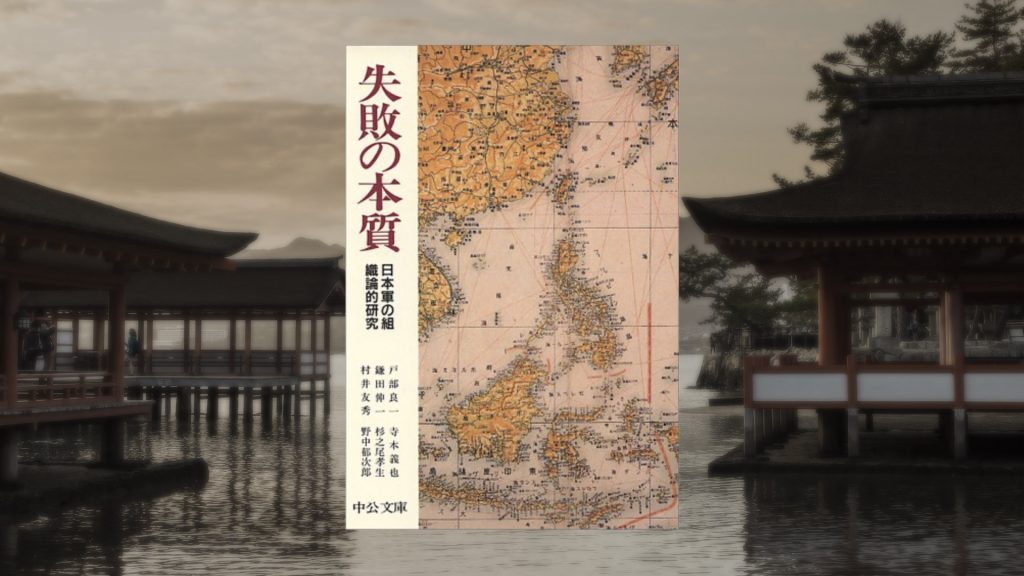Contents
第1章:はじめに――日本社会と「空気」「失敗」の関係
私たちが日本に暮らす中で、ときに説明がつかないほど強力に働く暗黙の「空気」というものがある。山本七平の『空気の研究』は、この現象を体系的に捉え直し、あらためて「私たちは何に流されているのか」「なぜ多数意見や空気に流されるのか」を解き明かしてくれる貴重な書である。
一方、『失敗の本質』は、第二次世界大戦における旧日本軍の組織的失敗を分析し、その根底にあった文化的・組織的要因を提示する。そこから導かれるのは、日本社会の意思決定や情報共有のあり方、その特徴と限界である。
現代においても、これらは決して過去の遺物ではない。むしろ日本社会の特徴は「空気による強力な集団同調」と「失敗の分析不足や曖昧化」によって継続的に形作られている面がある。映画制作の現場、あるいは他のさまざまな職場やプロジェクトチームでも、集団内の「空気」の存在や失敗の検証不足は大いに見られる。本稿では、映画製作に携わる視点から、これらの書籍が示す本質をどう捉え、どう仕事や社会に活かすかを考えてみたい。
第2章:『空気の研究』から見える日本社会――「空気」とは何か
- 「空気」の定義
山本七平が指摘する「空気」とは、必ずしも論理的・合理的ではないが、集団が共有する雰囲気や心理的圧力を指す。誰も明文化していないのに、自然と「こうするのが当たり前」「ここで反対するのは空気を読まない」という空気が生まれ、個人の発言や行動を左右する。日本語の日常会話でも「空気を読む」「KY(空気が読めない)」といったフレーズが一般化しているように、我々はこの概念を肌感覚でよく知っている。だが、その正体を深く考えることは少ない。 - 空気のもたらす効果――ポジティブとネガティブ
「空気」は一概にネガティブなものではない。映画制作でも、撮影現場が「よい空気」に包まれると、キャストやスタッフ同士のコミュニケーションがスムーズになり、チームとして一体感を得やすくなる。一方で、「空気」の負の側面は、論理的な検証や議論が妨げられたり、反対意見が封殺されたりする点にある。特に大勢の予算や利害が絡むプロジェクトでは、空気を優先させて根本的な問題を後回しにしてしまいがちだ。 - 空気に支配されるリスク――思考停止と責任回避
空気に流されると、個人や組織が思考停止に陥りやすい。とりわけ日本社会には「事を荒立てたくない」という心理が強く作用する場合が多く、明らかな問題点があっても空気を壊すほうがリスクだと考えてしまう。その結果、根本的な解決策を提案せず、「まあ、いまはこのままでいいか」という方向に流れてしまう可能性がある。また、空気による決定では責任の所在も曖昧になりやすい。「みんながそう言っていたから」という集団的思考で、結果的に誰も責任を負わない、あるいはよくわからない形でプロジェクトが迷走することがある。 - 映画制作と空気――意思決定のジレンマ
映画制作の現場を例にとってみると、脚本・監督・プロデューサー・撮影・照明・美術・衣装・俳優…と、多岐にわたる専門家が集まり、ひとつの作品を創造していく。その中で、予算やスケジュールの都合、あるいはスポンサー企業からの要請などが絡み合い、「現場の空気」がどちらの方向に向かうかが極めて重要になる。たとえば撮影現場で、誰もが薄々問題を感じていても、「ここで撮り直しを提案するのは空気を乱すかもしれない」と感じて言い出せないまま撮影が進行し、後になって「やはりあの場面、撮り直ししておけばよかった」という後悔が生まれるケースは珍しくない。
しかし、その「空気」をうまく制御できれば、逆にチーム全体を好循環へと導くことも可能だ。良好な空気をつくりながらも、問題提起がしやすい環境を保つ——これはリーダーシップを発揮するうえで特に重要であり、映画プロデューサーとしても意識すべき視点である。
第3章:『失敗の本質』から見る日本社会の組織文化――失敗をどう捉えるか
- 旧日本軍の失敗例から学ぶ組織論
『失敗の本質』では、太平洋戦争での旧日本軍の事例を詳細に分析し、日本的組織にありがちな問題点を浮き彫りにしている。たとえば、以下のような特徴が指摘される。
- 目的・戦略よりも、現場の「気合い」や「精神論」に頼りがち
- 失敗から学ぶ仕組み(フィードバック機能)が弱い
- 上下関係や空気による圧力で建設的な議論が行われにくい
- 大局観を欠いて場当たり的に対処し、全体の整合性が取れない
これらは極端な軍事組織の失敗として語られる一方で、現代の日本企業、プロジェクトチーム、そして映画制作の現場にも形を変えて存在する。プロジェクトの初期に十分な戦略やコンセプトメイキングを行わず、とにかく「やってみる」「頑張る」という勢いだけで始めた結果、問題が噴出したときに十分な軌道修正ができず、「失敗」という形で表面化することはよくある。
- 失敗を振り返る文化の欠如
『失敗の本質』で指摘されるもうひとつの重要な論点は、「なぜ失敗したのか」を正面から分析する作業が希薄であるということだ。日本社会では、ミスや失敗はなるべく隠したいものとされる傾向が強い。責任追及が行き過ぎてしまうリスクもあるため、組織として体系的に失敗を振り返り、学びに変える文化が根付きにくい。一度の失敗で「もう二度とチャレンジはしたくない」と萎縮し、結果としてイノベーションも生まれにくくなる。映画製作においても、作品の失敗を公に総括する場はあまり多くはない。興行成績や批評が芳しくなかった場合に、メンバーで集まって「どこが失敗だったのか」「次にどう活かすのか」を納得いくまで議論するケースは決して多くない。多忙な現場やスケジュールの後ろ倒しなどの理由もあるが、どこかで失敗を「忘れたい」心理が働いているのも事実だ。 - 「失敗」を取り扱う技術――リスクテイクと学習
イノベーションを起こすにはリスクテイクが必要である、とよく言われる。映画作りの現場でも新しい試みは大きなリスクを伴う場合が多い。しかし「失敗を恐れていては前に進めない」という教訓は、おそらく世界どこでも同じである。だが日本では、この「失敗したらどうなるのか」という感情的な重圧が組織や個人の判断に大きくのしかかりやすい。『失敗の本質』を読むと、単に「頑張れ」ではなく、戦略的にリスクを減らしながら挑戦を可能にする体制づくりや、失敗が起きたときに正面から原因を探り再発防止につなげるノウハウがいかに欠けているかを実感する。
映画制作の例でいえば、例えばある作品で新しい映像技術を試したときに十分な検証時間がなかったため失敗したのなら、その失敗を活かして次回は撮影前にテストを重ねるシステムをつくり、コストとスケジュールを考慮した計画を立てるなど、具体的な学習が必要だ。ところが「あの企画はダメだった」くらいのざっくりとした総括にとどまってしまうと、根本の問題が共有されないまま次の企画へと移行してしまう。その繰り返しが組織の成長を妨げる。
第4章:映画製作者の視点――組織やチーム運営への応用
- クリエイティブな現場こそ「空気」と「失敗」に敏感であるべき
映画制作は一見華やかに映るが、多くのリスクと複雑な作業工程が絡んでいる。脚本開発やプリプロダクションの段階から、さまざまな部署と意見をすり合わせねばならないし、実際の撮影に入ってからも想定外のトラブルが起こりやすい。だからこそ、「空気」の問題を意識し、どうすればチーム内にポジティブな連帯感をつくりつつ、同時に反論や違和感を言いやすい雰囲気を担保できるかを考える必要がある。
また、クリエイティブな分野ほど、失敗や試行錯誤がイノベーションの源泉になりうる。通常のビジネス以上に斬新な表現を模索する過程では、「これは本当にうまくいくのか?」という未知の要素が多分に存在する。そこに挑むためには、失敗を前向きに捉え、学習の糧にするメンタリティや仕組みが欠かせない。 - 意思決定プロセスの改善――リーダーシップとチームワーク
映画のプロデューサーや監督は、組織全体のリーダーとなる立場にある。『空気の研究』が指摘するように、ただ場の空気に流されるのではなく、あるいは逆に自分の意志を一方的に押し付けるのでもなく、多様な意見を引き出しながら最終的な意思決定へと導く力が重要だ。そのためには、事前の議論の場やコンセプトメイキング、脚本読み合わせの段階で敢えて異なる視点や反対意見を求める仕組みを導入するのも有効である。
「失敗の本質」的な観点でいえば、撮影後や作品公開後にこそきちんとした振り返りの場を設けることも不可欠だ。現場のスタッフ一人ひとりが、プロセスの中でどんな問題やハードルに直面したのかを共有し合い、次の作品への改善点を積み上げる。その繰り返しがあってこそ、組織は成長する。 - 情報共有と透明性の確保
映画制作のプロセスでは、予算管理からキャスティング交渉、脚本の修正など、日々大量の情報が生まれる。情報量が多いほど、組織内でのコミュニケーション不全や情報の偏在化が起きやすくなる。そうしたときに、リーダーシップを持つ者が積極的に情報を整理し、チームのメンバーに分け隔てなく発信する姿勢があるかどうかが大きな差を生む。
空気による同調圧力が強まるのは、しばしば情報が不十分な状態だ。誰もが情報不足のために「よく分からないが、なんとなくこうすべきじゃないか」という推測で動いてしまう。あるいは「リーダーがなんとかするだろう」と勝手に期待し、実態がわからぬまま空気が醸成される。だからこそ透明性を確保することで、空気の暴走を防ぎ、建設的な議論が成り立つ。
第5章:日本社会を豊かにするために――「空気」と「失敗」の活かし方
- 空気を完全に否定しない
『空気の研究』を読めばわかるように、空気は日本社会の中で長い歴史を通じて培われてきた文化的現象である。全員がまったく遠慮なく意見を言い合う、欧米型のダイレクトなコミュニケーションにただ寄せるだけでは、日本独自の強みである「察する力」「調和」を失ってしまう可能性がある。
つまり「空気」はそのまま社会を悪くする要因ではなく、うまく使いこなせばチームワークを高める効果もある。大切なのは、必要なときにあえて空気を壊してでも議論する勇気を持ち、空気と論理をうまくバランスさせることだ。 - 失敗をタブー視しない――学びのプロセスの共有
『失敗の本質』が示唆する通り、失敗から学ぶ仕組みをいかに組織や社会に根付かせるかは急務である。とりわけ日本社会では、結果的な敗北や不調を過剰に恐れる傾向が強い。そのため「失敗が許される文化」を創るための具体的な施策が求められる。たとえば、ものづくりやプロジェクト管理の現場では、失敗報告会やポストモーテム会議を定期的に開催し、成果ではなくプロセスを評価する仕組みをつくる。映画製作のプロデューサーとしては、公開後の舞台挨拶やファンミーティング、あるいは内部での振り返り会において、単に成果を祝うだけでなく「この部分は撮影中にトラブルがあった」「そこから何を学んだのか」という物語を共有することで、スタッフや観客にも新しい視点を与えることができる。 - 柔軟な思考と異文化へのオープンマインド
日本が今後、国際的な競争や文化交流の中で豊かさを保つためには、より多様な価値観との接触が不可欠だ。映画産業でも、海外との共同制作や海外マーケットへの作品輸出はますます増えていく。その際、「日本的な空気や失敗観」と「海外のダイレクトなコミュニケーションやリスクテイク文化」の差異を理解し、双方の強みを生かせる柔軟性が求められる。
ある場面では日本の「空気を読む力」が人間関係をスムーズにし、別の場面では欧米型の「忌憚なくモノを言う」マインドが問題解決を加速させる、というように状況に合わせて最適解を探っていく。映画制作はそもそも多国籍なチームで作業することも多いので、組織運営としても世界標準のコミュニケーションスキルを身につけつつ、日本的な強みをアピールするバランスが重要だ。 - 教育と若い世代へのアプローチ
社会を豊かにするには、やはり次世代を担う若者へのアプローチが欠かせない。学校教育の場や家庭環境で、空気にまかせて意見を潰すのではなく、のびのびと発言できる風土を育むことが必要だ。また、失敗を恐れずに挑戦する姿勢を育むために、教育の場で失敗に対する前向きな評価をもっと普及させる試みも考えられる。
例えば映画制作に興味を持つ若い人に対しても、撮影・編集・脚本などを自由に試し、失敗を重ねて学べるワークショップやコミュニティが増えるとよい。そうした小さな現場での体験が、将来の日本の文化産業や映画産業の活性化につながっていくはずだ。
第6章:仕事をするうえでの心構え――個人レベルでできること
- 自己検証と組織内での対話
日常の中で「今、自分は空気に流されていないか?」と自問してみるのは、意外に大きな効果がある。たとえば会議の場で、みんなが同じ方向を向いているときに、「本当にこれでいいのか?」と疑問を持つだけで空気は変わることがある。もちろんそれを言い出すには勇気がいるが、そこから生まれる建設的な議論が組織を健全な方向へ導く可能性も高い。
また、失敗したときにも個人レベルで振り返りを行い、整理した内容をチームに共有することは、前向きな文化を育む第一歩となる。ここで重要なのは「誰が悪いのか」を探すのではなく、「何が問題で、どうすれば次はうまくいくのか」をみんなで検討する姿勢だ。 - 持続的な学習とオープンなコミュニケーション
映画制作の現場では、技術革新やトレンドの変化が激しい。CGやVFXの進歩、デジタル配信の普及、SNSの存在など、刻々と変わる環境の中で常に新しい知識と経験を吸収し続ける必要がある。ここで空気に流されて保守的になるのではなく、積極的に学び続ける姿勢がプロフェッショナルには欠かせない。また、知識や情報を共有してくれる仲間とのオープンなコミュニケーションが、失敗のリスクを抑制しつつ新たな挑戦を可能にしてくれる。
仕事の場面では、たとえば毎日のように小さなフィードバックミーティングを行い、「今日は何がうまくいって、何がうまくいかなかったか」をライトに共有するだけでも、空気と失敗に関するリテラシーが自然と高まっていくはずだ。 - リーダーシップを持つ人の役割
監督やプロデューサーなど、組織を率いる立場の人は空気の影響を強く理解しつつ、それを良い方向へ導く責務がある。具体的には以下のようなアクションが考えられる。
- 会議やブレストの際に「反対意見を歓迎する」姿勢を明確に打ち出す。
- 発言の少ないメンバーに意図的に声をかけ、意見を引き出す。
- 失敗やミスが出たときに罰ではなく学習のチャンスとして捉えるフローを可視化する。
- 全員がプロセスを共有できるよう、ドキュメント化や情報整理を徹底する。
こうした小さな積み重ねが組織の風土を変え、長期的にみて作品の質や生産性を高めることにつながる。
第7章:日本を今後豊かにするための具体的アクション
- 文化産業の更なる国際化・産業化
日本の映画は国内市場を中心に回る部分が大きいが、世界では配信プラットフォームが劇的に成長している。そこに挑むためには、空気にとらわれず国際市場に向けた企画を立案し、失敗を恐れず実践してみる行動力が求められる。日本オリジナルの感性を強みにしつつ、海外とも連携しながら作品をつくることで、新しいマーケットを開拓できる。
国際的なコラボレーションの場では、当然コミュニケーションスタイルが異なるチームメンバーが混在するため、空気に関する前提が通じなくなるケースも多い。しかし、それこそが学習と成長の好機である。他国の映画人と共同制作を行う中で「日本はなぜそうするのか?」と問われることが増え、結果的に自国の文化的背景を説明する力が養われる。これは映画制作のみならず、他の領域でも大いに活かせるだろう。 - 地域活性化と映画の力
映画は総合芸術であると同時に、大衆に広く影響を与えるメディアでもある。地方自治体がフィルムコミッションを設立してロケ誘致を盛んに行うなど、地域を映画で盛り上げる取り組みは各地で行われている。こうした活動を成功させるうえでも、地域の空気をどう調整し、外部からの意見・アイデアをどう取り込み、失敗を恐れずアクションを起こすかが問われる。
たとえばある地方で、観光を活性化したいという思惑と映画制作の企画が噛み合わず、結果的に中途半端な作品となり失敗したケースがある一方で、地域が主体的にアイデアを出し、映画制作者と対話しながら新しいロケ地の魅力を発信して成功している例もある。失敗から学び続け、協力してよりよい作品を世に送り出す姿勢を忘れないことが、地域の豊かさにも直結する。 - 教育・企業研修への組織論の導入
『空気の研究』『失敗の本質』に書かれているような組織論的視点は、ビジネス研修や学校教育でも生かせる。特に企業研修では、チームビルディングの手法として「実際の失敗例を分析し、それをどう乗り越えるか」を考えるワークショップを取り入れたり、ミニ映画制作プロジェクトを試してみたりするのも面白いだろう。
映画制作のプロセスは、まさに短期間でチームを結成し、役割を分担し、クリエイティブな成果物を完成させるという、集団作業の縮図といえる。そこには自然と「空気」と「失敗」が発生する。参加者同士でその体験を振り返り、どうすればより良い作品づくりができたのかを検証することで、組織論を体得することが可能になる。 - 新しいリーダーシップ像の追求
日本の組織では、まだまだ縦割りのヒエラルキーが強かったり、上位者の意向を忖度する文化が根強かったりする。これを変えるためには、リーダーシップ像そのものを更新していく必要がある。空気に流されるだけでなく、失敗の責任を過剰に個人へ押し付けるのでもなく、チームの総力を引き出すための「ファシリテーター型リーダー」の普及が望ましい。
たとえば、映画のプロデューサーは上意下達型の「命令するボス」ではなく、関わるすべてのスタッフ・キャストの才能を見極めて適材適所に配置し、彼らが全力を発揮できる環境を整える「プロジェクトの調整者」としての力が求められる。これは多様性が前提となる現代社会の組織全般にも通じる姿勢だろう。
第8章:結論――「空気」と「失敗」を超えて未来へ
『空気の研究』は日本社会に深く根付く暗黙の同調圧力を浮き彫りにし、『失敗の本質』は軍事組織の失敗事例を通じて日本的組織の弱点を浮かび上がらせた。両書はどちらも数十年前に出版されたにもかかわらず、現代の私たちにとっても極めて示唆に富む。その理由は、「空気」や「失敗」への姿勢が今なお大きく変革されていないからだろう。
しかし、これらの書籍から学べる本質は単なる悲観ではない。空気をコントロールし、失敗を学習に変えられれば、日本社会には大きな可能性がある。調和と協調の文化を活かしながら、新しい発想や表現を取り入れ、組織としての柔軟性を確保できるようになれば、映画制作の世界でも、さらには他のあらゆる産業や社会領域でも大きな変革を起こせるはずだ。
仕事をする上でも、個人レベルで「本当にこれは正しいのか?」「空気に流されていないか?」「失敗を糧にできているか?」と問い続ける姿勢こそが求められる。映画製作者としては、撮影現場の空気に目を配るだけでなく、その空気に埋もれそうな意見を拾い上げ、新しい挑戦を促す役割を担う。さらに、作品が完成して興行収入や批評が出そろった後も、「うまくいった点」「いかなかった点」を丁寧に分析し、次の作品に活かす。それは映画という世界だけでなく、日本社会のあらゆる現場で目指すべき姿ではないだろうか。
最終的に、日本がこれからも豊かであり続けるには、無意識に組織や社会を縛る空気を意識的に変えていくこと、そして失敗を恐れず挑戦し、その結果を学びに変える文化を根付かせることが重要だ。私たち一人ひとりが、現場でこれを実践し、広げていくことで、日本の未来に一筋の光が差す。その道のりにおいて、『空気の研究』と『失敗の本質』は強力な指針となってくれるだろう。
おわりに
以上、映画製作者としての視点を絡めつつ、『空気の研究』と『失敗の本質』から得られる教訓を、仕事上の心構えや日本社会の今後の豊かさにどう繋げるかを論じた。両書はともに、日本独特の文化と組織のあり方を見つめ直すための絶好の手がかりである。ここで挙げた考え方や具体的アクションは、映画という狭い業界にとどまらず、日本社会全体を前向きに変革するヒントになり得る。
映画製作の現場では、創造性と協調性の両方が求められるため、「空気」も「失敗」も日常的に遭遇するテーマである。だからこそ、クリエイティブな仕事の現場がまずは率先して変わり、学んだことを社会全体に還元していければ大きなインパクトが期待できる。私たちがそれぞれの場で主体的に考え、小さな実践を積み重ねることが、やがて大きな流れを生み出すはずだ。