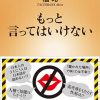Contents
若きクリエーターの皆さんへ
映画界に昔から根強く存在するある言葉について、私の視点を交えながら掘り下げてみたいと思います。それは「映画がヒットしたら監督の手柄、失敗したらプロデューサーの責任」。おそらく映画の現場をかじったことがある人なら、一度は耳にしたことがあるフレーズではないでしょうか。この言葉、何気なく使われたりしますが、実は映画の産業システムや制作現場の力関係、そして私たちクリエイターの生き方に深くかかわる要素が詰まっているんです。

監督の役割とは何か?
まず、この言葉が示すように、映画が成功したとき「監督の手柄」だと評価されるのはなぜでしょうか。確かに映画づくりの上で、監督は最も強いクリエイティブな影響力を持つ存在です。脚本の段階からアイデアを形にし、撮影現場ではキャストやスタッフに具体的な演出方針を示す。俳優の演技指導や、撮影の構図、照明の雰囲気、音楽の使い方など、作品全体を統括するアーティスティックな指揮官が監督です。
ここで映画史を少しひも解いてみましょう。かつてハリウッドがスタジオシステムでガチガチに固められていた1930年代から1940年代にかけては、映画づくりの最終決定権はむしろスタジオ側(=プロデューサーや経営陣)にありました。監督は大量生産システムの一部であり、まるで工場ラインの管理者のように扱われていた面があったのです。ところが、1950年代以降からヨーロッパを中心に台頭した「作家主義(オーターミ theory)」の影響で、監督が映画の芸術的・創造的主導権を握る「作者」であるという見方が強まります。フランソワ・トリュフォーやジャン=リュック・ゴダールらが活躍したヌーヴェルヴァーグでは特に、監督個人の作家性が作品の魅力の要とされ、そこからハリウッドも監督のブランド力を押し出すマーケティングが一般化していきました。
こうして現代では、映画が評価されるとき、監督の名声が前面に押し出されるのが自然なことになりました。興行的に大ヒットした作品は「○○監督の最新作」として語られる一方、賞レースでも監督の名前が目立つ。こうした流れの延長上に、「映画がヒットしたら監督の手柄」という言葉が納得感を伴って受け入れられているわけです。
プロデューサーの責任とは何か?
一方で、映画がコケたら「プロデューサーの責任だ」と言われる理由は何でしょうか。プロデューサーは映画の資金調達、企画の立案、スタッフ・キャストのブッキング、スケジュール管理、予算管理、そして配給や宣伝との連携など、幅広い業務を担います。簡単に言えば、映画制作の「総合プロジェクトマネージャー」のような存在です。監督というアーティスティックな舵取りがいる一方で、プロデューサーは主にビジネス面や制作進行を担い、最終的には興行成績というビジネス的な“結果”にも責任を負います。
ハリウッド黄金時代のスタジオシステムにおいては、プロデューサーが絶対的な権限を持っていました。作品の企画を決定し、監督を雇い、脚本家をアサインし、ときには編集の最終判断すらプロデューサーが下す。そうした体制では、もし映画が思ったように利益を生まなければ、スタジオ(=プロデューサー陣)が批判の矢面に立つわけです。そしてこの構図はいまも多かれ少なかれ続いている。
加えて、世間の人々が映画の損益を判断するときに目安とするのは、監督名や俳優のスター性よりも、まず「興行収入や配給の規模」。そこにはプロデューサーや配給会社のマーケティング戦略や資金繰りが大きく影響します。「映画ビジネスは投資」であるという側面を切り離せない以上、出資者や興行主からすれば「うまく回収できなかった=プロデューサーが責任を負う」構造がわかりやすいともいえます。
しかしながら、プロデューサーが全体をコントロールしようとしても、制作の過程では様々なクリエイティブ上の問題や予期せぬアクシデントが起きるもの。天候不順、俳優のスケジュール変更、脚本の書き直しなど、何かと想定外の事態が常に起こります。それを乗り越えて映画を完成させる過程で、プロデューサーは「最終的な責任者」のような立ち位置に立たざるを得ない。それが時に酷だという見方もあるけれど、それでも「責任を取る」ことでプロデューサーという職能がはじめて報われる、と言えるのかもしれません。
映画という産業システムの中で
ここであらためて、映画産業全体という視点で考えてみましょう。映画は「作家性の発露」であると同時に、「多額の資金やスタッフが動く大規模プロジェクト」です。監督は作品の芸術的な方向性を担い、プロデューサーは全体の進行やビジネス面を担う。ただし、この両者の区別は必ずしも明確ではありません。監督が自分でプロデュースもこなす場合もあれば、プロデューサーがクリエイティブに深く介入する場合もあるのです。
映画史を見渡してみると、実は監督とプロデューサーの境界が曖昧な事例は少なくありません。とりわけインディペンデント映画の分野では、予算が限られているためにプロデューサーが複数の役割を兼務することが当たり前になりがちです。監督と共同で脚本開発をするプロデューサーや、逆に監督自身が製作費を集めに奔走し、プロデューサーとしての機能を担うケースも普通にあります。
そのため、本来はチームプレイであるはずの映画づくりが、この業界における「作家主義」や「スター制度」の都合で、どうしても「監督が表に立つのが当然」「失敗したら資金面を管理していたプロデューサーに責任がいく」という構図になりやすいのです。これはある意味で、人々が「映画」という作品を作る主体をイメージするとき、まず監督のビジョンや監督の名前を想起しやすいからでもあるでしょう。
クリエイターへの方々へ
では、これから映画業界に飛び込もうとしている若いクリエイターの方たちは、この「ヒットしたら監督の手柄、失敗したらプロデューサーの責任」という言葉をどう受け止めればいいのでしょうか。ここからはインディペンデント映画のプロデューサーとしての私見を交えてお話しします。
- 役割を明確に把握する
まず大切なのは、「監督はこう、プロデューサーはこう」という役割の基本をきちんと理解すること。インディペンデントの現場ではいろいろ兼務することが多いため、境界が曖昧になりがちです。しかし作品をより良いものにするためには、結局だれが最終決定権を持っているのか、何に責任を持つのかをはっきりしておくことが重要です。とくに「お金」をどこから持ってくるのか、その使い道はどうするのか、そうした現実的なプロセスは作品を完成までこぎつけるうえで決定的に重要です。このあたり、学生時代の自主制作だとあまり意識しないかもしれませんが、商業ベースで映画を作る際には必須の意識になります。 - 失敗と成功の両面を見据える
「映画がヒットしたら監督の手柄、失敗したらプロデューサーの責任」という言葉に象徴されるように、作品の成功・失敗はあっという間に周囲からレッテルを貼られてしまいます。けれども、その一面的な評価に振り回されるのではなく、失敗なら失敗で学ぶことが必ずあるし、成功でも満足しすぎると次回に落とし穴が待っているかもしれない。若いクリエイターの方には、とにかく「失敗を恐れないこと」を伝えたいです。なぜなら、映画づくりは常に未知との戦いですし、その未知に飛び込む熱量こそが新しい映像表現を生み出す原動力になるからです。 - 作家性とビジネスのバランスを理解する
現代ではSNSやクラウドファンディングなど、個人でも作品を広くアピールできる手段が増えました。そういった時代だからこそ、監督=クリエイターが自身でプロデューサー的な役割を担う機会も増えてきます。自分の作品をつくり、世に出すためには、お金の流れやプロモーション方法についても学ぶ必要があるでしょう。これは決して「自分の作家性を薄める」ことではありません。むしろ、自分が本当に作りたい世界観を実現するために、ビジネス面から映画を操縦するスキルを身に付けることは大きなアドバンテージになります。 - チームをリスペクトする姿勢
映画づくりはとにかく「チーム戦」です。監督とプロデューサー以外にも、脚本家、撮影監督、美術、照明、録音、編集、俳優、音楽、VFX、メイクなど、膨大なセクションと人々が関わっています。どのポジションも欠けては作品にならないし、全員が力を合わせることで初めて「映画」という総合芸術が形になるのです。若いクリエイターほど自分のやりたいことに集中しがちですが、現場を円滑に回すには、一人ひとりの役割をリスペクトすることが重要。結果として「成功」「失敗」という評価がくだされるときも、チーム全体でそれを受け止めて次に進む姿勢があると、より豊かな作品づくりができるようになると思います。 - インディペンデント映画の強みを活かす
予算や宣伝規模でメジャーに到底及ばないインディペンデント映画は、逆に言えばプロデューサーの存在がとても重要です。限られた資金と人材をどう有効に使うか、効率的なスケジュール管理とマーケティングプランをどう組むかが成果を左右します。ここでプロデューサーが情熱的かつ柔軟に動けると、監督のビジョンを最大限に支えることができます。若いクリエイターの方も、自身の作家性を貫きたいなら、いずれ自分で資金を集めたり、作品を売り込んだりするプロデュース的な能力が求められるでしょう。それは「監督の手柄」「プロデューサーの責任」という古い構図から飛び出し、自分たちで新しい仕組みを作り上げる一歩になるかもしれません。
映画史から見た監督・プロデューサー像の変遷
少し映画史に戻ってみると、ハワード・ヒューズのように大金持ちが自ら映画会社を所有してプロデューサーとなり、かなり大胆な企画を通して監督や脚本家を振り回すということもありました。オーソン・ウェルズは『市民ケーン』で製作・脚本・監督・主演を兼ね、「映画の天才」の異名をとりましたが、プロデューサーとしてのヒューズなど資金提供者との葛藤は常にあったといわれます。スタジオ主導が強かった時代にあって、監督や俳優には独自の創造性を発揮する余地が限られ、プロデューサー権限がとにかく大きかったわけです。
そこから時代が移り変わり、いわゆる「New Hollywood」と呼ばれる1960年代末から1970年代のアメリカ映画界では、フランシス・フォード・コッポラやマーティン・スコセッシ、スティーヴン・スピルバーグら、監督主導の革新的な作品が次々と世に出ました。プロデューサーというよりも監督の作家性が目立ちやすい時代となり、その流れは今なお続いているといえます。
しかし近年ではマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)のように、プロデューサー(マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギなど)が巨大なフランチャイズを一貫して統括し、複数の監督を起用しながらもブランド全体を成功に導くという「プロデューサー・ドリブン」なモデルも確立しています。「映画がヒットしたら監督の手柄、失敗したらプロデューサーの責任」という古典的な構図はありつつも、実はプロデューサーが長期的なビジョンを描き、それによって巨大ビジネスを回しているという実情もあるのです。
こうした歴史を俯瞰してみると、「監督がヒットの顔、プロデューサーが責任を取る存在」という単純な図式だけでは捉えきれない複雑さが見えてきます。と同時に、この複雑さこそが映画という産業の魅力でもあり、若いクリエイターたちが参入する余地のある広大なフィールドであると感じます。
言葉の意味を自分なりに再解釈する
結局のところ、「映画がヒットしたら監督の手柄、失敗したらプロデューサーの責任」という言葉は、監督とプロデューサーそれぞれの歴史的・文化的な役割を端的に示す、ある種の“業界ジョーク”でもあります。が、その背後には、芸術とビジネスが表裏一体となった映画の本質が隠れていると言えます。
ヒットすれば監督が注目を浴びる。その注目が次のプロジェクトへの追い風になる。一方で失敗すれば、プロデューサーが投資家や配給会社に頭を下げることになる。そんな現実を皮肉混じりに語っているのがこの言葉です。
しかし私は、インディペンデント映画の現場で日々苦労しながらも、自分自身が「責任を引き受ける覚悟」をすることで、映画づくりの自由度が高まるのを感じています。失敗したら責任を取る。それは怖いことでもあるけれど、逆に言えば「自分の信じる作品を押し通す」チャンスを得られるということでもあるのです。監督や他のクリエイターと喧々諤々の議論をしながら、自分が責任者として決断する。そのプロセスでこそ、制作陣全員の創造力が高まり、現場がガラリと変わる瞬間があります。
若いクリエイターの方には、ぜひこの言葉を一度受け止めた上で、「じゃあ自分はどういう映画を作りたいのか」「どんな責任なら負えるのか」を深く考えてみてほしいと思います。監督を目指す人も、プロデューサー的な視点を学んでおくことで、作品の舵取りだけでなくビジネスの海図まで見通せるクリエイターになれる。プロデューサー志望の人も、映画の芸術面に対する感性を磨いておけば、予算配分やキャストの選択一つとっても、より総合的に判断できるはずです。
最後に強調したいのは、映画づくりとは本来、監督とプロデューサーはもちろん、脚本家や撮影監督、美術スタッフ、俳優、編集技師、サウンドデザイナーなど多くの人が力を合わせる総合芸術であるということ。たまたま表に見えるのが監督であり、資金面で責任を負うのがプロデューサーだというだけで、本質的には全員が成功にも失敗にも関わっているのだと思います。
これから映画を目指すみなさんには、そんな「映画はチームで作る」という原点を忘れずに、ヒットというわかりやすい成果だけにとらわれず、それぞれの役割を越境しながら学び合ってほしいと思います。最終的に名声は監督のものになりやすいかもしれません。失敗の痛みはプロデューサーがより大きく引き受けるかもしれません。でも、それを越えて「自分が本当に撮りたい映画」「観客に届けたい体験」を形にするために、多様な才能が集まり、議論し合い、苦悩しながら一つの作品を完成させる。その尊さこそが映画づくりの醍醐味なのではないでしょうか。
ヒットと失敗という極端な二面に惑わされることなく、ぜひ「誰のために、何のために映画を作るのか」を忘れずにいてほしいと切に願っています。私自身、まだまだ未熟で、毎回「これで大丈夫か……?」と頭を抱えながら、いろんな現場を乗り越えてきました。でも、その度に思うのは、「映画は複数の人間がかかわる生き物」だということ。そして「誰かが責任を引き受けるからこそ、クリエイティブが思い切り羽ばたける」ということです。監督とプロデューサーの役割分担に捉われすぎず、お互いが尊敬し合い、時には補い合いながら歩んでいく。そこからしか生まれない映画が、きっとあるはずです。