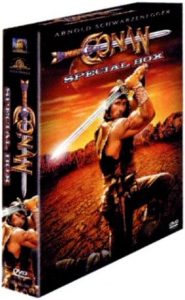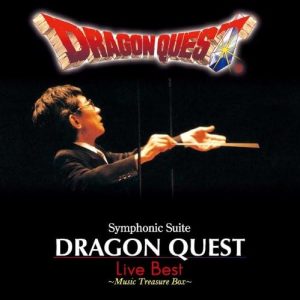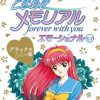Contents
【はじめに:ドラゴンクエストとは何か?】
日本の家庭用RPGの代表的存在として、1986年にエニックス(現スクウェア・エニックス)から発売された『ドラゴンクエスト』。ゲームデザインは堀井雄二、音楽はすぎやまこういち、キャラクターデザインは鳥山明が担当し、日本のRPG史だけでなくコンピュータゲーム史においても重要な転換点となった作品である。本作は、発売直後から瞬く間に大ヒットし、「国民的ゲーム」という評価を獲得すると同時に、RPGというジャンルを日本国内で確立させ、広める大きな原動力となった。
しかしなぜ、1986年という時期に日本市場でRPGが定着し、しかも『ドラゴンクエスト』がその旗振り役になったのか。その背景を探るためには、日本の家庭用ゲーム機(とりわけファミリーコンピュータ)の普及や、それ以前のパソコンゲーム文化、さらには海外RPGからの影響といった外的要因が不可欠である。また、それらの外的要因だけでなく、日本社会や文化、そして制作者たちのゲームデザイン思想がどう絡み合って結実したのかを考察することも重要だ。
本稿では、まず当時の日本のゲーム産業の状況や文化的土壌を整理し、それから『ドラゴンクエスト』が登場するまでにあった世界的なファンタジー文学やハリウッド映画、テーブルトークRPG(以下、TRPG)の流れを再確認する。そこに加え、日本人がもともと親しんできた「成長物語」や「順番に考える遊び(将棋・囲碁・麻雀など)」との結びつきがどう作用したのかを探りつつ、最後に堀井雄二ら制作者がどのように海外RPGの難解さを日本向けに再構築したかを論じることで、「ドラゴンクエストが1986年に日本で生まれる必然」を総合的に示したい。
第1章:日本の家庭用ゲームとパソコンゲームの発展
1-1. ファミリーコンピュータの普及と家庭用ゲーム文化の成熟
1983年に任天堂から発売されたファミリーコンピュータ(以下、ファミコン)は、日本の一般家庭におけるゲーム文化の大きな転換点であった。ファミコンの登場以前にもテレビゲーム機やパソコンゲームは存在していたものの、どちらかといえばマニア層や一部の愛好家だけが熱中するものであった。しかし、ファミコンは比較的手頃な価格と扱いやすさ、そして『スーパーマリオブラザーズ』(1985年)などの大ヒットソフトによって、子どもから大人まで幅広い層へと一気に普及した。
この普及によって、「ゲーム機を家庭に置く」というスタイルが当たり前になり、ゲーム市場そのものが数百万人という巨大な需要を抱えることになった。こうした市場の拡大とユーザー層の多様化は、RPGのように多少入り組んだシステムを持つジャンルを受け入れる土壌を生み出した。つまり、一度アクションゲームでゲーム機に慣れ親しんだユーザーたちが、新しいジャンルへと興味を広げていけるだけの市場規模と文化的素地が整ったわけである。
1-2. パソコンゲーム市場の存在と海外RPGの流入
一方で、ファミコンが一般家庭に普及する以前から、1980年代前半には日本のパソコン市場が徐々に拡大していた。シャープのX1やNECのPC-8801、富士通のFM-7などが代表的な機種として登場し、特にプログラミングやゲームを楽しむ層が形成されていた。
このパソコンゲームの世界では、すでに海外RPGの名作である『ウィザードリィ』(1981年)や『ウルティマ』(1981年)といったタイトルが輸入され、一部のゲーム愛好家の間で大きな人気を博していた。これらの作品はいずれも英語ベースで、高度なコンピュータRPGの原形を示すものであったが、その分「英語の壁」や「複雑なシステム」という要素があり、決して誰もが手を出せるものではなかった。
堀井雄二自身、パソコンゲームや海外RPGから多大な影響を受けており、とりわけ『ウィザードリィ』のダンジョン探索や『ウルティマ』のオープンワールド的要素からヒントを得ていたことが知られている。しかし当時、それらはあくまでも**“コア”なファン**のためのジャンルであり、一般層が大々的に楽しむにはハードルが高かったのである。
こうした「海外RPGの存在」「パソコンゲーマーというマニア層の下地」があったことで、日本のゲーム制作者はRPGジャンルに可能性を見出しつつも、「どうすれば日本人に合った形で提供できるのか?」という課題を認識するようになった。『ドラゴンクエスト』は、まさに「海外RPGを日本風にアレンジし、ファミコンで遊びやすく作り直す」という方向性で開発された作品である。
第2章:日本人の物語観・文化背景とRPGの親和性
2-1. 「冒険」と「成長」の物語を好む日本文化
日本の昔話や伝統的な物語には、主人公が修行や試練を経て成長し、仲間と協力して大きな目標を成し遂げる筋立てが数多く存在する。たとえば『桃太郎』や『一寸法師』は、弱く小さな存在が仲間と共に成長し、大きな敵を倒す典型例だ。アニメやマンガの分野でも、『宇宙戦艦ヤマト』や『機動戦士ガンダム』など、困難な状況を乗り越えながら主人公たちが力をつけていく物語は多くのファンを獲得してきた。
RPGの醍醐味はまさに**「主人公がレベルアップし、冒険を通じて強くなる」**という部分にある。つまり、RPGは「成長物語」という日本で長く受け継がれてきた物語構造と自然に合致していたのだ。アクション性よりもストーリー体験やキャラクターの成長が主軸になるため、「物語の中で主人公と一体化して成長する」感覚は日本のプレイヤーの心を強く捉えた。
2-2. コマンド式バトルの受容と将棋・囲碁の文化
『ドラゴンクエスト』が採用した**「コマンド式のターン制バトル」は、当時の海外RPGと比べるとアクション性が薄いと見られがちだが、実はこれこそが日本のプレイヤーにとって親和性が高い要素だったといわれる。なぜなら、日本には将棋・囲碁・麻雀など「順番を待って考える」**遊びが古くから根付いていたからだ。
アクションゲームが苦手な人でもコマンド入力形式なら落ち着いて判断できるし、また思考力や戦略性を楽しめる。そのうえ、当時のファミコンの性能を考えるとリアルタイム処理で複数の敵味方が動くシステムは難しく、コマンド式バトルは技術的にも実現しやすかった。結果的に、このシステムが**「じっくり遊べるRPGを家庭で体験する」**という新鮮な魅力をユーザーに提供したのである。
2-3. 「努力すれば報われる」価値観とレベルアップ要素
1980年代の日本社会は、高度経済成長を経てバブル景気に近づいていた時代でもあり、「努力や我慢が報われる」という価値観が広く共有されていたと言われる。RPGにおける経験値とレベルアップの仕組みは、その価値観と非常に相性が良い。「コツコツ戦闘を重ねればレベルが上がり、強大な敵を倒せるようになる」という流れは、受験勉強や部活動、企業での昇進競争などにも通じる考え方であり、日本のプレイヤーにとって抵抗が少なかった。
第3章:外的要因の再確認――ファンタジー文学・ハリウッド映画・TRPG
3-1. ファンタジー文学の金字塔『指輪物語』とその波及
RPGの世界観といえば、西洋ファンタジーをベースにした**「剣と魔法の世界」を想起することが多い。ここには、イギリスの作家J.R.R.トールキンによる『指輪物語』**の影響が大きく関わっている。同作は北欧神話やケルト神話を下敷きにしつつ、壮大な世界構築と小さなホビットが大きな運命を背負うという物語を融合させることで、現代ファンタジー文学の代表例となった。
『指輪物語』や、その前作である『ホビットの冒険』はアメリカで爆発的な人気を得て、1970年代には多くのファンタジー作品が生み出される土壌となった。これらの作品がアメリカのゲームシーンにも影響を与え、その延長線上で生まれたのがテーブルトークRPG(TRPG)の代表作『ダンジョンズ&ドラゴンズ(D&D)』である。
3-2. 『ダンジョンズ&ドラゴンズ』とRPGの原型
1974年に初版が発行された『D&D』は、プレイヤーたちがダンジョンマスターの指示のもと、自分のキャラクターを動かし、ファンタジー世界で冒険をするテーブルトークRPGであった。ここで確立された**「経験値」「レベルアップ」「職業(クラス)」「魔法」「モンスターのデータ集」**などの概念は、後にコンピュータRPG全般に受け継がれる基本フォーマットとなった。
『ドラゴンクエスト』においても、「戦士」「僧侶」「魔法使い」といった職業や、モンスター図鑑的な要素、宝箱やダンジョン探索などは、まさにD&D的なエッセンスを取り入れつつ日本向けに遊びやすく再構築したものと考えられる。堀井雄二が「海外RPGをプレイして受けた衝撃を、自分なりに日本のユーザーに届けたい」と考えたことが、『ドラゴンクエスト』の原動力の一つでもあった。
3-3. ハリウッド映画のヒーロー譚
ゲームだけでなく、当時のハリウッド映画もまた日本の制作者やプレイヤーに大きな影響を与えていた。とりわけ1977年の『スター・ウォーズ』は「英雄の旅(Hero’s Journey)」という物語構造をSFの世界に取り込み、大衆に大ヒットした作品として知られる。普通の青年ルークがジェダイとして成長し、銀河帝国に挑むストーリーは、まさに古今東西の「英雄の旅」を踏襲したものである。
もう一つ、1982年公開の『コナン・ザ・グレート』は「剣と魔法の世界観」を映像的に体現し、ファンタジーアクション映画としても注目を集めた。こうしたハリウッドの冒険活劇が放映されることで、日本の視聴者にも「ファンタジー世界での冒険」に対するイメージが根付き、それがRPGの受容へとつながる背景にもなった。日本の子どもたちや若い世代は、映画やアニメでヒーローが成長しながら強敵を倒していく物語に強く惹かれており、そのエッセンスを自分たちで体験できるゲームとしてRPGを歓迎したのである。
第4章:堀井雄二・鳥山明・すぎやまこういち――才能の結集
4-1. 堀井雄二の「誰にでも遊べるRPG」へのこだわり
堀井雄二は、それまで日本国内で主流だったパソコン向けRPGの複雑さに対して、**「より多くの人が楽しめるようにシンプルにしたい」**という意識を持っていた。『ウィザードリィ』や『ウルティマ』が提示した自由度や奥深さは素晴らしいが、同時に「英語表記」「複雑なコマンド」「容赦ない難易度」という障壁があり、日本の一般家庭には向きにくい側面があった。
そこで堀井は、次のような方針を打ち出したという。
- ストーリーを明快にする
- 「勇者が魔王を倒す」という分かりやすい筋立て
- ゲームシステムを簡素化
- コマンドの種類を最小限にまとめる。「たたかう」「じゅもん」「どうぐ」「にげる」といった単純明快な選択肢
- インターフェースの日本語化と親切設計
- 英語コマンドや複雑な操作を廃し、平易な日本語で表示
- 復活の呪文(パスワード)システム
- セーブ機能の乏しいファミコンでも、長い冒険を継続できる仕組み
こうして「初めてRPGを遊ぶ人でも取っ付きやすく、それでいて冒険感と成長感を味わえる」形が出来上がった。これはまさに「日本のユーザーがRPGに求めるもの」を的確に突き止め、それを技術的制約と照らし合わせて無理なく実装した成功例だといえる。
4-2. 鳥山明が描いた魅力的な世界観とキャラクター
ファミコン初期のゲームにおけるグラフィックは、まだドット絵が荒く、キャラクター表現は限られていた。しかし、鳥山明によるパッケージイラストやモンスター原画は、そんな技術的制約を飛び越えてユーザーに強烈なインパクトを与える。鳥山はすでに『Dr.スランプ』や『ドラゴンボール』で漫画家としての地位を確立しており、コミカルかつ親しみやすいキャラクターデザインは多くのファンを惹きつけた。
「スライム」など、いまや国民的キャラクターといっても過言ではないモンスターを生み出したのも鳥山明のセンスによるところが大きい。従来のファンタジー作品ではドラゴンやゴブリン、スケルトンなど西洋由来のモンスターが多かったが、『ドラゴンクエスト』はそのイメージを鳥山流に再解釈し、ポップかつ愛嬌のあるデザインへと昇華した。これにより「RPG=おどろおどろしい世界」というイメージが覆され、子どもから大人まで広く楽しめる作品になったのである。
4-3. すぎやまこういちの壮大な音楽とゲーム音楽観の変革
もう一人忘れてはならないのが、作曲家であるすぎやまこういちの存在だ。当時のファミコンゲーム音楽は、限られた音源の中で短いループ曲を流すのが主流であり、「BGMはあくまでも雰囲気作り」程度の位置づけだった。しかし、すぎやまはクラシックやオーケストラを研究し尽くした経験をもとに、ゲーム音楽をシンフォニックに構築しようと試みた。
ファミコン音源はわずか3和音(+ノイズチャンネル)しか出せないが、その制限の中で序曲やフィールド音楽、戦闘曲などを「ドラマチックに」聴かせるという意欲的な作風を打ち出した。それは、ゲーム音楽が「単なるBGMではなく、作品世界を大きく彩る要素になり得る」ことを証明し、ゲームユーザーの音楽観にも変革をもたらしたといえる。後にオーケストラコンサートが開催されるほど、すぎやまこういちの音楽は『ドラゴンクエスト』の世界観に欠かせない存在になった。
第5章:1986年というタイミングの必然性
5-1. ゲーム文化の成熟と技術的進歩
『ドラゴンクエスト』が世に出た1986年は、ちょうどファミコンの普及が爆発的に進んでいた時期である。『スーパーマリオブラザーズ』(1985年)の大ヒットにより、「ファミコンを持っている家庭」が急増したことで、多くのユーザーが新作ソフトを買い求める下地があった。また、ファミコン本体やソフト開発のノウハウが徐々に蓄積され、RPGのような少し複雑なゲームシステムを実装できる技術的な基盤も整ってきていた。
5-2. パソコンRPGからのノウハウ吸収
先述したように、『ウィザードリィ』や『ウルティマ』といった海外RPGの存在が、日本の制作者にとって貴重な手本となった。特に堀井雄二を中心とする開発チームは「マニアだけのRPGを、どうしたら一般層にアピールできるか」を常に模索し、ファミコン用に大幅にシステムをアレンジした。これは、パソコンゲームによるコアなゲーマー文化があったからこそ吸収できたノウハウであり、その成果が1986年のタイミングで一気に花開いた形だ。
5-3. 日本的ファンタジーとしての受容
ファンタジー世界を舞台とするRPGは、もともとアメリカ発祥であり、中世ヨーロッパ風の世界観をベースにしている。しかし、『ドラゴンクエスト』は鳥山明のキャラクターイラストや、ひらがなカタカナを多用した日本語表記、そして独特のコミカルさを融合させることで、「日本的ファンタジー」として確立された。これは、日本人が「外来のファンタジー要素」を受容しつつ、自分たちの文化やセンスで再解釈し直すプロセスがうまく機能した一例ともいえる。
1980年代にはすでにアニメや特撮、マンガなどの「オタク文化」がある程度成熟しつつあったことも、ファンタジー世界が受け入れられやすかった要因だ。つまり、ドラゴンや魔法、勇者といった要素は決して馴染みのない異世界のものではなく、子どものころからテレビやマンガを通じて何となく理解していた概念だったのである。
第6章:さらなる視点――神話構造と日本的物語の融合
6-1. 「英雄の旅」の普遍性とプレイヤー体験
神話学者ジョーゼフ・キャンベルが提唱した「英雄の旅」(Hero’s Journey)は、「普通の世界にいた主人公が冒険の呼び声を受け、師匠に導かれながら試練を乗り越えて成長し、最後に世界を救う」という普遍的な物語パターンを示す概念だ。『ドラゴンクエスト』のストーリーラインは、この英雄の旅の典型をなぞっている。
- 主人公は何らかのきっかけで冒険に出る(王様の依頼など)
- 道中で仲間を得るor新たな力を身につける
- 多くのダンジョンやボスを倒して経験を積む
- やがて魔王との最終決戦に臨む
- 勝利ののち、平和を取り戻す
この一連の流れは、プレイヤーがインタラクティブに英雄の旅を体験できるという点で画期的だった。それまで物語は、映画や小説で「受け身」で鑑賞するものが主流だったが、RPGは能動的に「自分が主人公になって物語を進める」という新しいエンターテイメントを提供したのである。
6-2. 日本の古典物語や少年漫画の影響
加えて、日本の古典的な冒険譚や少年漫画にも同様の構造が多く見られたため、日本のユーザーにとっては**「どこか馴染み深いストーリー」**だったと考えられる。実際、『桃太郎』や『一寸法師』も、弱い主人公が武器や仲間を得て鬼や巨大な敵に立ち向かうという構図であり、RPGのダンジョン攻略やレベルアップと通じる側面がある。
少年漫画の文脈でも、『ドラゴンボール』や『北斗の拳』は主人公が強くなる過程や強敵との戦いを描く作品として有名であり、そこに「努力は報われる」「強くなるほど大きな目標を目指せる」という価値観があり、日本人の心情と親和性を持った。『ドラゴンクエスト』のシステムは、まさに数値化された成長をゲームの中心に据えているため、こうした考え方にマッチしやすかったと言えよう。
第7章:もし『ドラゴンクエスト』が存在しなかったら
7-1. 日本のRPG文化の遅れ
仮に1986年に『ドラゴンクエスト』が発売されていなかった場合、日本の家庭用RPG市場は大幅に遅れを取った可能性がある。すでにパソコン向けに一部のユーザーが海外RPGを楽しんでいたが、それが**「国民的なゲームジャンル」**にまで育つには時間がかかったかもしれない。ファミコンによって家庭用ゲーム機が大衆化したタイミングに、わかりやすく遊びやすいRPGが登場したことが、RPG人気の爆発を後押ししたのは疑いようがない事実だ。
7-2. 後続作品への多大な影響
『ドラゴンクエスト』が示したフォーマットは、その後の日本のRPGに多大な影響を与えた。とりわけコマンド式バトル、スライムをはじめとする愛嬌のあるモンスター、そして明快なレベルアップシステムは数多くのRPGに継承された。もしこれがなければ、後にスクウェアの『ファイナルファンタジー』シリーズやその他多くのRPGがどのように誕生していたか、あるいはまったく異なる形で進化していたかは想像に難くない。
第8章:総合考察――「日本的RPG」の完成とドラゴンクエスト
ここまで見てきたように、『ドラゴンクエスト』が日本で大きな成功を収めた背景には、以下の要素が複雑に絡み合っている。
-
ゲーム市場の成熟:
- ファミコンの普及とアクションゲームの大ヒットによるユーザー層の拡大
- パソコンRPGの存在と海外名作からの学び
-
日本文化とRPGの相性:
- 成長物語や冒険譚を好む伝統的な物語構造
- 将棋・囲碁文化などターン制やコマンド入力への抵抗感の少なさ
- 「努力が報われる」という価値観とレベルアップシステムの親和性
-
海外ファンタジーやハリウッド映画の影響:
- 『指輪物語』や『ダンジョンズ&ドラゴンズ』からの世界観・システム継承
- 『スター・ウォーズ』に代表される「英雄の旅」の広い認知
- 『コナン・ザ・グレート』などによる剣と魔法のイメージの普及
-
制作者の才能とコンセプト:
- 堀井雄二の「誰にでも遊べるRPG」へのこだわり
- 鳥山明による親しみやすく魅力的なキャラデザイン
- すぎやまこういちの壮大な音楽とゲーム音楽観の変革
そして何より、こうした要因が1986年というタイミングで合流し、ファミコンというプラットフォームで花開いたことが大きい。もしファミコンが普及しきっていない段階や、逆にもっと後の段階であれば、ここまでのインパクトはなかったかもしれない。また、堀井・鳥山・すぎやまというチームが組まれなければ、『ドラゴンクエスト』の魅力は半減していた可能性が高い。まさに絶妙なタイミングと才能の結集が、この「国民的RPG」の誕生を支えたといえよう。
第9章:映画考察・映像制作の視点から――RPGと映像作品の共鳴
本稿は映画考察・映像制作のブログという文脈で掲載されるということなので、最後に映画とRPGの関係についても触れてみたい。
9-1. 映画的手法を取り入れたゲーム演出
RPGは物語を体験するジャンルであるため、近年ではカットシーンや演出に映画的手法を取り入れる作品が増えている。カメラワークやBGMの使い方、画面のフェードイン・フェードアウトといった演出は、映画制作の知見が大きく生きる領域だ。『ドラゴンクエスト』第1作ではファミコンの制約上、映像的な演出は限定的だったが、続編以降やリメイク作品では随所に“映画的な盛り上がり”を演出する試みが見られる。
9-2. 「プレイヤーが主人公」になる物語
映画とゲームの最大の違いは、映画が観客に「受動的に物語を見せる」メディアであるのに対し、ゲームは「プレイヤーが物語を能動的に進める」インタラクティブメディアである点だ。RPGは特に、物語体験がゲームプレイの中心にあるため、プレイヤーは**「自分が主人公である」**感覚を強く味わうことができる。
映画において観客は主人公に感情移入しながらも、ストーリーの展開を直接変えることはできない。しかしRPGでは、プレイヤー自身の選択によってシナリオの進行や結末が変わることもある。そうした意味で、RPGというジャンルは映画的なドラマトゥルギーをベースにしつつ、**「参加型の物語」**を提供するメディアだといえる。
9-3. 映画化・アニメ化への展開
近年、人気ゲーム作品が映画化やアニメ化される例は珍しくない。『ドラゴンクエスト』シリーズも、アニメや映画、さらには舞台化など多様なメディアミックスが行われている。そこでは、ゲームにおける「プレイヤーの選択」が存在しない代わりに、映像としての魅力を高めるための脚本や映像表現の工夫が注目される。RPGで培った壮大な世界観やキャラクターが、映像作品ではどのように解釈され再現されるか――この点にも、今後ますます目が向けられていくだろう。
第10章:結論――ドラゴンクエスト誕生がもたらした日本RPGの未来
まとめとして、『ドラゴンクエスト』の日本登場を支えた背景には、以下の要素が大きく関係していた。
- 家庭用ゲーム市場の拡大(ファミコンの普及)
- 海外RPG(ウィザードリィやウルティマ)の存在と、堀井雄二自身の体験
- 日本人が古くから好んできた成長譚や物語構造、コマンド式への馴染み
- 堀井雄二の「わかりやすさ」への徹底したこだわり
- 鳥山明のキャラクターデザインによる親しみやすさ
- すぎやまこういちの音楽がもたらしたドラマ性の向上
そして、それらが1986年という絶妙のタイミングで合わさり、日本のユーザーにとって理想的な形のRPGが誕生した。それは「自分が勇者となって冒険し、成長して、最後には魔王を倒す」というシンプルでありながら奥深い体験を、多くの家庭で楽しめるようにした革命的出来事だった。そして『ドラゴンクエスト』の成功が、後の『ファイナルファンタジー』など多数のRPGに影響を与え、日本のRPG文化が世界的に高い評価を受ける基盤を作り上げたのである。
その源流をたどっていくと、アメリカ発祥のTRPG『D&D』やファンタジー文学、ハリウッド映画で培われた「英雄の旅」の普遍性がある。しかし、いざ日本で家庭用ゲームとして大衆化するには、日本人の文化的特性(じっくり考える遊びの好み、成長物語の受容、漫画的キャラデザインの親和性)が極めて重要だった。そして何より堀井雄二らの**「日本向けに最適化する」**という意志とセンスが、RPGの敷居をぐっと下げて大衆化に成功したと言えるだろう。
今後、ゲームハードや技術はめまぐるしく進化していくが、『ドラゴンクエスト』が生み出した**「冒険」「成長」「仲間との絆」「親しみやすさと奥深さの両立」というエッセンスは、さまざまな形で後世に受け継がれていくはずだ。ゲームが映像やアニメ、さらにはVRやAR技術と結びついていく未来の中でも、この1986年に花開いた「日本的RPGの原点」**は色褪せることなく、多くのクリエイターやファンにインスピレーションを与え続けるだろう。
【最終的なまとめ】
『ドラゴンクエスト』というRPGが1986年に日本で誕生し、**「国民的ゲーム」**にまで成長した背景は、ファミコン普及によるゲーム市場の活性化、海外RPGやパソコンゲーム文化の下地、日本人が好む成長物語やターン制バトルへの親和性、そして堀井雄二・鳥山明・すぎやまこういちという才能の結集があったからこそ成し得たものだった。それらすべてが複雑に絡み合っていたため、このタイミングで「日本向けに磨き上げられたRPG」が誕生し得たのである。
もし時期が早すぎても、市場が成熟しておらず普及しなかった可能性がある。逆に遅すぎれば、他の作品や技術革新が先行してしまい、これほど強いインパクトは残せなかったかもしれない。そう考えると、『ドラゴンクエスト』の誕生は偶然ではなく必然であり、1986年というタイミングにこそ大きな意味があったと言えよう。
これを映画や映像制作の文脈で捉えるならば、RPGというジャンルは物語演出と視覚・聴覚的演出を総合的に組み合わせる点で、映画やアニメと密接な関係を持つことがわかる。『ドラゴンクエスト』を通じて培われた「遊びながら物語を体験する」メソッドは、現代の映像作品にも大きな影響を与えている。今後も新たなテクノロジーや表現手段と結びつき、さらに進化していくであろうRPGのルーツを理解する上で、『ドラゴンクエスト』の誕生背景を振り返ることは非常に意義深い。
以上のように、『ドラゴンクエスト』が日本独自のゲーム文化とRPGジャンルの成長を牽引する作品として登場した背景には、多面的な要素が含まれている。古今東西のファンタジー文化、日本の伝統的な成長物語観、アメリカのTRPG文化、そして1980年代という社会情勢に根ざした価値観が複合的に機能し、それを見事にまとめ上げた制作者たちのセンスが結実した結果として、「日本的RPG」が確立したのである。
映画的・映像的視点から見ても、**「英雄の旅」**をインタラクティブに体験させる物語構造と、キャッチーなキャラデザインや音楽による演出は、十分にドラマティックな要素を兼ね備えている。まさにゲームという枠を超えて、「日本のエンターテインメント全体」に与えた影響は計り知れないと言えるだろう。