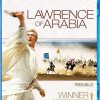映画や映像作品の制作は、多くの人や工程が関わり、そして何より“成果”が非常に不確定なものです。どれだけ良い脚本や優秀なスタッフ、魅力的なキャストを揃えたとしても、必ずしも成功が約束されるわけではありません。興行成績、評価、観客の反応――それらは外部の要因にも左右されるからです。そんな中、制作チームの間で「縁起を担ぐ」方法がひそかに用いられることがあります。
たとえば撮影開始日の選定や撮影開始前の神社での安全祈願、スタッフが持参するお守り、衣装の色や衣装合わせの日取りにこだわるなど、その形はさまざま。こうした縁起担ぎは「結果を良い方へ導くため」のおまじないとして捉えられがちですが、それだけではありません。縁起担ぎを介することでスタッフ間に一体感が生まれ、共通の目的意識や前向きな気持ちを共有できるのです。また、作品作りはどうしても長期的なスケジュールとなるため、節目節目で「縁起」を意識すると、自分たちの活動を再確認したり、チームの士気を高めたりする効果も期待できます。
本記事では、主に「暦を活かす縁起担ぎ」と「現場でのちょっとしたゲン担ぎ」の2軸にわけ、具体的な例を豊富にご紹介します。もし「なんだかちょっと気になるかも」「なんとなく不安を払拭したい」「スケジュールがまだ決まっていない」という映画・映像制作関係者の方がいらっしゃれば、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
Contents
1. 暦を活かす縁起担ぎ
1-1. 大安(たいあん)に始動日やクランクインを設定する
最も一般的に知られた六曜の中で、最も縁起が良いとされるのが「大安」です。六曜とは、暦(主に和暦)の上に付された「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の6種類の吉凶を示す言葉です。大安は文字通り「大いに安し」であり、一日中吉の運勢を持つ日とされています。
-
大安を撮影初日やクランクイン日に設定
よく耳にするのは、「結婚式を大安にする」といった例ですよね。同じように、映画や映像制作においても「初日を大安にすると、全体がうまくいく」と考えるスタッフは少なくありません。撮影隊の集合日やクランクインの日程を大安に設定することで、スムーズな進行とチームワークを願うわけです。
ただし、スケジュールの都合上、必ずしも大安に合わせられるとは限りません。外部ロケの許可日程やキャストのスケジュールなどの兼ね合いで難しい場合も多いでしょう。それでも、もし余裕があるなら、少しだけ意識して大安に設定してみるのもひとつの方法です。 -
大安以外の六曜も意味がある
大安以外でも、たとえば「先勝(せんしょう)」は「先んずれば勝つ」ということで、午後よりも午前中が吉と言われるなど、意味を読み解くことで特定の時間帯に撮影を組むという考え方をするスタッフもいます。実際はスケジュール優先で動くため、細かく合わせるのは現実的に難しいことが多いですが、時間に余裕がある時は検討してみるとちょっと面白いかもしれません。
1-2. 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)を活用する
「一粒万倍日」は、その名の通り「一粒のモミが万倍にも実る」という意味を持つ吉日です。何かを始めたり、大切なものを購入したり、お祝いごとをするのに良いとされる日として広く知られています。カレンダーやインターネットで容易に確認できるので、撮影開始日や新しい機材の導入日を一粒万倍日に合わせる、という縁起担ぎをする方々もいます。
-
機材購入や契約の日に合わせる
一粒万倍日は何かを「始める」ことによって、その行動が将来的に大きく実るとされます。例えば新しい撮影機材や編集ソフトを導入する、ロケ地との最終契約を結ぶ、キャストとの最終的な出演契約を締結する――そういったタイミングを一粒万倍日に合わせることで、「この機材がたくさんの実りをもたらしてくれる」「この契約が成功を生む」という気持ちを持ちやすくなるのです。 -
「逆効果も万倍」説に注意
一方で、「良いことも悪いことも万倍になる」という説もあるため、不注意やネガティブな行動は控えたいもの。撮影中に大きなトラブルを起こすと、後々まで響いてしまうかもしれない――と、戒めの意味でも用いられています。このような意味づけがあるからこそ、スタッフ全員が気を引き締めて現場に臨む、というプラスの効果も期待できるでしょう。
1-3. 寅の日・巳の日・天赦日(てんしゃにち)など、他の吉日の活用
暦には六曜以外にも、さまざまな吉日があります。中でも代表的なものとして挙げられるのが、「寅の日」「巳の日」「天赦日」です。これらをうまく組み合わせることで、さらに縁起を高めようという方も。
-
寅の日
寅の日は「トラが千里往って千里戻る」と言われることから、出ていったお金やモノがすぐに戻ってくるという考え方をされる縁起の良い日とされています。映画制作は資金繰りが大変なことが多いため、資金調達や支払日に寅の日を選ぶという人もいます。 -
巳の日(みのひ)
巳の日は弁財天を祀る日として知られ、お金や芸事のご利益があるとされる吉日です。芸事における成功を願う意味で、キャストの衣装合わせやダンスリハーサル、音楽のレコーディングなど、クリエイティブ要素が強い作業を巳の日に合わせるというのも面白い試みです。 -
天赦日(てんしゃにち)
天赦日は「天がすべてを許す日」と言われ、最上級の吉日として位置付けられています。数ある暦の中でも、年に数回しかない非常に貴重な開運日です。何か大きなプロジェクトをスタートさせる、思い切った決断をする(大幅な脚本の修正など)などに最適と考えられています。
1-4. 大きな神事・行事から着想を得る
映画制作の世界では、神社にお参りして安全祈願をする、というイメージが比較的定着しているかもしれませんが、さらに時期そのものを日本古来の行事や神事に合わせて設定することがあります。たとえば新嘗祭(にいなめさい)や立春、秋分の日など、季節の節目に作品の始動日を合わせることで、“生まれ変わり”や“収穫”を象徴させるわけです。
-
神社での正式参拝・ロケの安全祈願
撮影の安全や作品の成功を祈願し、神社で正式参拝をするチームは少なくありません。特にアクション映画や危険を伴う撮影が多い場合は、「関係者全員が大きな事故なく無事に終了できるように」という願いを込めます。映像制作であれば、ドローン撮影や難易度の高い照明セットなど、安全第一を確認するためのタイミングとしても有用です。 -
お寺や神宮を参拝して御朱印・お守りをいただく
神社以外でも、お寺や神宮など、地域に根付く「力の強い」とされる場所に出向き、御朱印をいただいたり、作品の成功を祈ってお守りを授かったりするスタッフもいます。休憩の合間やロケハンの隙間などに立ち寄ることも可能ですし、オンライン参拝を受け付けている寺社がある昨今では、遠方ロケでも心の拠り所を得られるのがメリットです。
2. 現場で取り入れる「ちょっとした」縁起担ぎ
暦や大安などの大がかりなスケジュール調整以外にも、現場レベルでの小さなゲン担ぎは多数存在します。続いては、撮影現場や制作段階で手軽に行える縁起担ぎの方法をご紹介します。
2-1. 初日の「乾杯(かんぱい)の儀式」
映画やドラマなど長期にわたる撮影に入る前、クランクイン当日の朝や前日の夜にスタッフやキャストが集まって「乾杯」を行う習慣は多く見られます。これは単なる親睦会というより、「ここから作品を一緒に作り上げていく仲間としてのスタートを切る」宣言でもあり、縁起担ぎの一環といえるでしょう。
- ソフトドリンクでもOK
早朝に撮影が始まるなら当然アルコールは避けるべきですが、そこはノンアルコールビールやソフトドリンクで対応可能。大切なのは、チーム全員が一斉にグラスやカップを持ち上げ、気持ちをひとつにすることです。 - 挨拶を兼ねて全スタッフ紹介
特に大規模作品では、誰が誰なのか把握しきれないまま撮影が進んでしまうことがあります。短い時間でもよいので「本作のプロデューサーです」「助監督です」といった自己紹介を兼ねると、結果的にチーム力がアップし、スムーズなコミュニケーションにつながります。
2-2. 「お札」や「お守り」のセットへのお祀り
実際の撮影セットや編集ルームに、お札やお守りをこっそり飾っておくこともあります。多くの場合、目立つ場所ではなく、隅やスタッフだけが分かる場所にそっと置いてあることが多いですが、「一度も大きなトラブルなく撮影を乗り切れたのは、お守りのおかげかも?」と後から話題になるほど、精神的な拠り所になることがあります。
-
必ずしも神社のものだけに限らない
あるスタッフは、海外の教会で手に入れたメダイ(聖人が刻まれたメダル)を持参したり、仏教系のお守りを組み合わせたりと、各自の宗教観や好みに合わせている場合があります。チーム全員で同じものをお祀りする必要はなく、「自分にとってのゲン担ぎ」を個人的に持ち込むだけでも効果は十分です。 -
破魔矢・熊手で“縁起をかき集める”
正月の初詣で手に入れる破魔矢や、酉の市で手に入れる熊手なども、映像制作の現場で縁起物として使われることがあります。熊手は“福をかき集める”という意味を持っているため、興行成績や作品の評価など、いわば「観客の好意をかき集めたい」映画・ドラマ制作にはぴったりとも言えます。
2-3. 衣装や小道具に「色のパワー」を取り入れる
色にはそれぞれ意味やイメージがあり、その力を借りる形で縁起を担ぐこともあります。映像制作の現場では、映像上の色彩設計だけでなく、スタッフが着る服やキャストの衣装に縁起の良い色を取り入れるという方法も。
-
赤色(勝負運・活力)
赤はエネルギーや情熱、活力を象徴するといわれています。大事な撮影の日に赤い小物を身につけたり、監督やプロデューサーが赤いジャケットを羽織ることで「ここぞ」の勝負運を引き寄せようという考え方があります。 -
金色(繁栄・金運)
映画制作では資金調達や予算管理が大きな課題のひとつです。小型の金色グッズを机の上に置いておく、金色のステッカーを機材ケースに貼っておくなど、ほんの少しの工夫で「金運アップ」を狙うスタッフもいます。また、映像の世界観としても金色は派手になりがちですが、「ここぞ」というシーンで金色の衣装やアイテムを登場させるのも、視聴者の印象に残りやすい手段です。 -
緑色(リラックス・安定)
長期スケジュールの映画撮影は、どうしてもスタッフやキャストが疲労を抱えてしまう時期があるものです。緑はヒーリング、リラックスを象徴する色。控室に観葉植物を置くのはもちろん、スタッフが緑の小物を身につけるだけでも、心理的な安らぎをもたらすことが期待できます。
2-4. 言葉選びの注意(忌み言葉を避ける)
映画やテレビの制作現場でも、忌み言葉(いみことば)を気にすることがあります。特に葬儀や不吉なシーンがテーマになる場合は避けにくい言葉も出てきますが、そうした場合でも直接的に言わずに遠回しに表現することも。
-
「終わる」→「上がる」
撮影やロールを回し終えるときに、縁起が悪いとして「終わる」という言葉を避け「上がり」という表現を使うことがあります。聞いたことがある方も多いかもしれませんが、映画・ドラマに限らず、撮影現場では「今日の分はこれで上がり」などの言い方が浸透しています。 -
「カット」→別の指示
「カット」はもちろん監督が撮影ストップを指示する際の基本用語ですが、たとえば縁起を担ぎたい人は意識的に言わず、手振りや「OKです」などの合図に変えることもあるそうです。これはかなり特殊な例ではありますが、「なるべく言わないようにしていたら、不思議と良い成果が出た」と語る人もいます。ただし周囲のスタッフとの共通認識がなければ現場に混乱を招く恐れもあるため、臨機応変が大事です。
2-5. 撮影前の「手締め」で現場を引き締める
日本の伝統的な行事や式典で用いられる「手締め」(手打ち)を、撮影現場で導入することがあります。たとえば、「一同これから集中して大事なシーンを撮るぞ」というときに一本締め、または三本締めを行うなど。
- 一本締め・三本締め
一本締めは「パン!」と一回手を打って終了するスタイル、三本締めは「パン、パン、パン」3回繰り返して締めるスタイル。しっかり声掛けして皆で合わせることで、その場がキュッと引き締まり、集中力が高まります。 - 終業時にも行う
日本舞踊や寄席芸などでも、終業時に手締めをして一日の労をねぎらう風習があります。映画撮影でも最終日、オールアップの瞬間に手締めを取り入れることで、達成感と無事完遂への感謝を明確に共有できます。
3. 縁起担ぎをどう捉え、どう活かすか
こうした縁起担ぎは、ともすれば「非科学的」なものと捉えられがちです。映画制作はあくまでクリエイティブな作業であり、スタッフやキャストの才能や努力、さらにはプロデューサーの交渉力など、現実的かつ論理的な要因が成功を左右するのは間違いありません。しかし、縁起担ぎには「現場の気持ちを一つにまとめる」という重要な効果があります。
- 不安やストレスを軽減する
撮影現場は常に時間と予算、そして突発的なトラブルとの闘いです。縁起担ぎをすることでスタッフは「私たちはちゃんと準備している」「何か大きな力に守られているかもしれない」と感じられ、不安やストレスを和らげる効果が期待できます。 - ポジティブな心理状態を作る
成功をイメージし、ポジティブな状態で作業に入ることは、集中力や創造力を高めることにつながります。縁起担ぎは、その前向きな気持ちを引き起こすトリガーになり得るのです。 - スタッフ間のコミュニケーション促進
「今日は大安だから気合いが入るね」「一粒万倍日だし、新しい機材を試してみよう」など、ちょっとした会話が生まれます。こうしたコミュニケーションが増えると、結果的に連携も取りやすくなり、作品のクオリティアップにも貢献するでしょう。
4. 映画・映像制作に役立つ縁起担ぎQ&A
ここでは、よくある疑問や不安に答える形で、さらに縁起担ぎを深堀りしていきましょう。
Q1. 「忙しい現場で、暦までチェックする余裕がありません…」
A. 全日程を徹底して吉日に合わせる必要はありません。大きなイベント――「クランクイン」「クランクアップ」「重要な契約日」など、節目だけに絞ってチェックしてみるのはいかがでしょうか。近年はスマートフォンのアプリやウェブサイトなどで簡単に六曜や一粒万倍日、天赦日を検索できますので、空き時間にさっと確認してみるだけでも違います。
Q2. 「そもそも迷信っぽいので、スタッフやキャストから反対されないでしょうか?」
A. たしかに、全員が同じ気持ちとは限りません。しかし、「縁起を担ぐ」という行為は、必ずしも押し付けがましくするものではありません。「自分はこういうのを大事にしたいけど、みんなはどう?」という軽い共有程度に留めれば、多くの場合受け入れられやすいでしょう。反対意見があっても、強制しなければ大きなトラブルにはなりにくいはずです。
Q3. 「海外のスタッフも参加している現場ではどう説明すればいいですか?」
A. 「日本の文化のひとつとして縁起担ぎがある」と説明するのがスムーズでしょう。海外にも相応のラッキーチャームやジンクスが存在します。たとえば西洋では「13日の金曜日は不吉」とされるなど、国や地域によって独自の縁起や迷信があるものです。それらと同じように、日本の縁起担ぎを紹介すると興味を示してもらえることが多いですよ。
Q4. 「縁起担ぎをやっても、必ずうまくいくわけではありませんよね?」
A. 残念ながら保証はありません。あくまで縁起担ぎは“補助的な行為”です。ただし、うまくいかなかったとしても、それを縁起担ぎのせいにするよりも「モチベーションアップや現場の結束には役立った」と考えることができます。映画や映像づくりは不確定要素が多い分、何かしらの精神的な支えをもって取り組むか否かで、最終的な成果にも差がつく場合があります。
5. 実践的な取り入れ方の例
ここからは、具体的な実践例をさらに掘り下げます。必ずしも全てを採用する必要はなく、自分たちの制作スタイルや現場に合ったものをピックアップしてください。
-
スケジュール表に六曜や吉日を記載する
- ExcelやGoogleカレンダーに、簡易的に「大安」「一粒万倍日」「寅の日」「天赦日」などを記載しておく。
- その日が吉日であることをスタッフに周知し、ちょっとした心構えを持ってもらう。
-
クランクイン前に神社で安全祈願
- 地元の神社を調べて、正式参拝の申し込みをする。
- お守りやお札をいただき、撮影用の車両や機材に貼っておく。
-
セットの隅に縁起物を置く
- 熊手や破魔矢などを飾り、スタッフに説明しておく。
- レンタルスタジオの場合は持ち運び可能な小さなものを使用すると便利。
-
衣装・小道具で色彩を意識する
- 勝負どころのシーンでキャストに「赤」を取り入れる、金運をアピールしたいなら「金色」モチーフを小道具に添える。
- 美術担当やスタイリストと相談しながら演出に組み込む。
-
クリエイティブチームのミーティングで一度「手締め」
- 新しいアイデアを採用する、脚本に大きな変更を加えるなど、節目の場面で一本締めや三本締めをすると、自然と気持ちが切り替わり、チームのモチベーションが上がる。
-
キャスト・スタッフ個人のゲン担ぎを尊重する
- 役者が大事にしているお守りやラッキーチャームを撮影現場にもたらすことがある。見えるところに置きたい場合はセットや小道具との兼ね合いを考えつつ、なるべく協力する。
6. 縁起担ぎとアート活動の関係性
映画制作だけでなく、アートプロジェクト全般にも縁起担ぎの文化は生きています。美術展のオープニングを吉日に合わせたり、初演奏会を大安に合わせる音楽家もいます。創作活動は多かれ少なかれ「未知への挑戦」であり、その「やってみなければわからない」不安と隣り合わせです。そこで縁起担ぎが果たす心理的効果は非常に大きいのです。
-
独自のジンクスを作るアーティストも
アーティストの中には、自分なりのジンクスや儀式を設定している人が多くいます。「制作前に必ずコーヒーを飲む」「新しい筆を使うときはペン先を3回叩く」など、一見ばかばかしく思えるものでも、それが心身のコンディションを整え、集中力を高めるきっかけになっているなら十分な意味を持ちます。 -
作品テーマとの相乗効果
縁起担ぎを作品テーマやストーリーに反映させることも考えられます。例えば「吉日から始まる恋物語」「神社が重要なロケ地となる作品」「縁起物をモチーフとしたキャラクターデザイン」など、制作の段階で実際に取り入れながら、そのエッセンスを作品自体に取り込むことで、より説得力のある映像表現になる可能性があります。
7. 縁起を担ぐ行為はチームにとっての“心の支え”
本記事では、映画制作や映像制作において活用できる「縁起担ぎ」のさまざまな方法を、暦や習慣の面からご紹介しました。大安や一粒万倍日、寅の日、天赦日といった日本の吉日に注目したり、現場レベルでは衣装・色彩への配慮、初日の乾杯や手締め、神社への安全祈願など、多岐にわたる形があります。
映画の成功を左右するのは、もちろん企画の良さやスタッフの実力、予算、宣伝など数多くの要因が絡み合います。しかし、縁起を担ぐことでチームの結束が強まり、各自が“自分は守られている”“いい方向に物事が動く”と感じられれば、それは大きな原動力になるはずです。特に映画や映像づくりは、思い通りにいかないことも多いチャレンジングな現場ですから、心の支えとなるような要素は積極的に取り入れていく価値があるでしょう。
また、アート活動にも同様のことが言えます。作品が生まれるまでのプロセスで、「なんとなくモチベーションが続かない」「もう少しで完成なのにスランプに陥った」というタイミングこそ、縁起担ぎによるメンタル面のケアやリフレッシュが効果的に働くかもしれません。
もし今後、新しい映像作品や企画を始める際に少し余裕があれば、「ちょっと大安を調べてみよう」「一粒万倍日に何か始めてみるのはどうだろう」といった気軽な気持ちでスケジュールを調整してみるのも面白いはずです。結果だけでなく、過程を楽しむ意味でも、縁起担ぎは時に大きな刺激と安心感を与えてくれるでしょう。
ぜひ皆さんの映画制作・映像制作、あるいはアート活動の中で、一度試してみてはいかがでしょうか。地に足の着いた準備や計画に加え、こうした“ちょっとした非日常”を大切にする姿勢が、創作の世界をより豊かに彩るはずです。