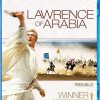Contents
はじめに
ホラー、SF、ファンタジーなど「ファンタスティック系」映画に焦点を当てた映画祭は世界各地に存在し、独自の盛り上がりを見せています。こうした映画祭は大手の国際映画祭とは一線を画し、作家性あふれるジャンル映画を積極的に扱うのが特徴です。日本にも1990年創設のゆうばり国際ファンタスティック映画祭(北海道夕張市)などがありますが、海外にも歴史あるものから新興のもの、ユニークなコンセプトを掲げるものまで様々です。
日本のインディーズ映画制作者に向けて、世界のファンタスティック系映画祭をカテゴリ別に紹介します。知名度の高い主要映画祭、新進気鋭の映画祭、ユニークなコンセプトの映画祭の順に取り上げ、それぞれについて開催地・概要、作品選考の傾向、過去10年以内の日本映画の受賞・ノミネート事例、そして日本の映画制作者にとっての戦略的意義を詳述します。これを参考に、国際舞台への応募戦略や制作意欲を高めていただければ幸いです。
知名度の高い主要ファンタスティック映画祭
まずは、世界的に権威がありジャンル映画ファンにはお馴染みの主要映画祭を紹介します。歴史や規模から見て「三大ファンタスティック映画祭」と称されることもある映画祭を中心に、その特色と日本作品の活躍例を見ていきましょう。
シッチェス・カタロニア国際ファンタスティック映画祭(スペイン)
開催地・概要: スペイン・カタルーニャ州のリゾート地シッチェスで毎年10月頃に開催される、世界最大級のファンタスティック映画祭です。1968年に「国際幻想・ホラー映画週間」として創設され、50年以上の歴史を誇ります。ホラー、SF、ファンタジーからカルト映画まで幅広いジャンル映画を扱い、公式競争部門をはじめアニメーション部門(Animat)、新人監督部門など多彩なプログラムがあります。現在ではモントリオールのファンタジア映画祭、米国テキサス州のファンタスティック・フェストと並んで「世界三大・最大のジャンル映画祭」とみなされています。毎年約10日前後の日程で開催され、世界中の映画ファン・映画人が集う一大イベントです。
選考の特徴・評価される作品傾向: シッチェスは伝統的にヨーロッパにおけるジャンル映画の登竜門であり、世界最先端のホラーやSF作品から auteur色の強い作品まで多様な作品が集まります。いわゆるB級テイストの娯楽作品から芸術性の高い作品まで受け入れる懐の深さが特徴で、巨匠と新鋭を同時にフィーチャーしています。特にアジアの作品には熱心で、「毎年アジアの作品に忠実なラインナップを組んでいる」と自負するほど日本を含むアジアの新作を積極的に招待しています。2015年には日本の新世代ジャンル映画に特別な注目が払われ、園子温監督や塚本晋也監督らの新作が公式上映されました。また長編コンペティションの他に短編やクラシック上映、ゾンビウォーク(仮装パレード)などイベントも充実しており、娯楽性と映画芸術性を両立した映画祭です。
日本映画の活躍例(過去10年): シッチェスでは日本のアニメやホラーがしばしば高く評価されます。たとえば新海誠監督のアニメ映画『君の名は。』(2016)は第49回シッチェス映画祭で長編アニメーション部門最優秀作品賞(Best Animated Feature)に輝きました。実写では佐藤信介監督のSFアクション『いぬやしき』(2018)が公式部門に出品され、同年の観客賞を獲得するなど大きな話題を呼びました。2018年の同映画祭では上田慎一郎監督のインディーズホラーコメディ『カメラを止めるな!』も公式上映され、上映後スタンディングオベーションが起きるほど観客の心を掴み「シッチェスの現象」とまで称されました。園子温監督は2015年に同映画祭の功労賞タイムマシン賞を受賞し、また清水崇監督や三池崇史監督など日本のジャンル映画人がしばしばゲストに招かれています。近年も中田秀夫監督が2023年にタイムマシン賞を受賞するなど、日本とシッチェスの結びつきは強固です。
日本の映画制作者にとっての意義: シッチェスでの上映や受賞は世界のジャンル映画コミュニティから注目を浴びる絶好の機会です。欧州の配給会社や映画メディア関係者も多数参加するため、ここで評判を得ればその後の欧米配給や他国の映画祭招待につながる可能性があります。実際、『カメラを止めるな!』は国内の夕張映画祭での賞をきっかけに劇場公開され大ヒットしましたが、その後シッチェスや他の海外映画祭で絶賛され、リメイク企画や海外配信につながりました。またシッチェスは「メリア・ホテル」の会場に世界中のゲストが泊まり込み、多くの公式・非公式パーティーやネットワーキングの場があることで知られます。日本のインディー監督にとって、憧れのジャンル映画人と交流したり、自身の作品を売り込んだりできる貴重な場となるでしょう。「世界で最も権威あるファンタ映画祭の一つ」という肩書きは宣伝面でも強力で、将来のキャリア形成に大いに役立ちます。
ファンタジア国際映画祭(カナダ)
開催地・概要: カナダ・ケベック州モントリオールで毎年7~8月に開催される北米最大のジャンル映画祭です。1996年に地元の熱狂的映画ファンたちが立ち上げた比較的新しい映画祭ながら、現在では年間観客動員数がモントリオール世界映画祭を上回るほど人気を博しています。当初は主にアジアのカルト映画やアニメを紹介するイベントとして始まりましたが、近年は世界各国のホラー・SF・アクション映画を幅広く扱い、上映作品は長編・短編合わせて毎年300本近くにのぼります。部門としては最優秀作品賞にあたるシュヴァル・ノワール(黒馬賞)部門、新人監督を対象としたニュー・フレッシュ部門、アジア映画賞、観客賞など多彩な賞を設けています。また2012年にはジャンル映画の国際共同製作を支援するマーケット「フロンティアーズ(Frontières)」を創設し、世界のプロデューサー・バイヤーが集まる場として機能しています。
選考の特徴・評価される作品傾向: ファンタジアはもともと香港映画や日本映画に熱心だった経緯から、アジアのジャンル映画に強いプログラミングが特徴です。特に日本のアニメーションや特撮、ホラーに深い理解があり、北米初上映の場となることも多々あります。実際、1998年に中田秀夫監督の『リング』をいち早く北米初上映し、その後のJホラーブーム火付け役となりました。また市川崑監督『犬神家の一族』(1976)の北米初上映を行うなど、日本映画の紹介にも貢献しています。作品傾向としてはエンタメ性と独創性を兼ね備えた作品が高く評価される傾向です。審査員は刺激的で新鮮な表現を求めるため、たとえば過激なゴア表現のホラーからスタイリッシュなサイバー・パンクSF、アニメからミュージカル・ホラーまで、多様なジャンルの優れた作品が受賞します。ファンタジアでは「ホラー映画のレシピを完璧に完成させている」と評価される作品が賞を獲得することもあり、ジャンルのお約束を押さえつつ斬新さがある作品が好まれるようです。
日本映画の活躍例(過去10年): ファンタジアは日本の新作上映が非常に多く、受賞例も枚挙にいとまがありません。直近の例では、下津優太監督のホラー『みなに幸あれ』が2023年のファンタジア映画祭でアジア作品賞に相当する「MIFFアジアン・アワード(最優秀アジア映画賞)」を受賞しています(同賞はアジアのジャンル映画の発掘・応援を目的に設立され、前年は二宮健監督の『真夜中乙女戦争』(2022)が受賞)。2015年には園子温監督の『TAG タグ』が長編部門の最優秀作品賞と最優秀女優賞を受賞、同じく園監督の『ラブ&ピース』は観客賞を獲得しました。また2018年には上田慎一郎監督の『カメラを止めるな!』が新人監督の長編デビュー作に贈られるニュー・フレッシュ部門で特別表彰され、観客からも熱狂的な支持を得ました。さらに2019年の観客賞では、日本映画がアジア長編部門の金銀銅を独占するという快挙も起きています。すなわち金賞:武内英樹監督の『翔んで埼玉』、銀賞:矢口史靖監督の『ダンスウィズミー』、銅賞:藤井道人監督『劇場版ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん』(いずれも2019年)が選ばれました。同年は今石洋之監督のアニメ映画『プロメア』も長編アニメ観客賞を受賞しています。このようにファンタジアの観客は日本映画に熱い支持を送る傾向があり、アクション大作から実験的作品まで幅広く受け入れられていることがわかります。
日本の映画制作者にとっての意義: ファンタジア映画祭は北米市場への登竜門として戦略的価値が高いです。まず、ここで評判になれば英語圏での配給やストリーミング展開への糸口になります。多くの米国配給会社や配信プラットフォーム関係者が参加し、新作をチェックしているため、観客賞や審査員賞の受賞作はその場で買い付けが決まることも珍しくありません。例えば『カメラを止めるな!』はファンタジア上映後、口コミで欧米にも評判が広がり、結果としてリメイク権がフランスで買われ(2022年にミシェル・アザナヴィシウス監督『FINAL CUT』としてリメイク)ています。さらに、フロンティアーズ・マーケットでは企画段階のプロジェクトを国際共同製作につなげる機会があり、日本からも若手プロデューサーが参加しています。ファンタジアは運営スタッフやボランティアとの距離も近く、上映後Q&Aでは熱烈なファンから直接意見をもらえるため、クリエイターにとって刺激となるでしょう。北米最大規模のジャンル映画コミュニティに自作を届けられるという点で、ファンタジアは日本のインディー監督にとって極めて魅力的な舞台です。
ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭(ベルギー)
開催地・概要: ベルギーの首都ブリュッセルで毎年春(3月末〜4月)に開催されるヨーロッパ有数の歴史あるファンタスティック映画祭です。通称「BIFFF(ビッフ)」と呼ばれ、1983年に初開催以来40年以上の伝統を持ちます。スペインのシッチェス、ポルトガルのポルト国際映画祭(ファンタスポルト)と並び「世界三大ファンタスティック映画祭」の一角とされており、国際映画製作者連盟(FIAPF)公認のコンペティティブ映画祭でもあります。会期中は数万人規模の観客が訪れ、特に地元の熱狂的なファンによる観客参加型の熱い雰囲気で知られます。上映中に観客がヤジや歓声を飛ばす独特の文化があり、優秀作品にはグランプリに相当する「ゴールデン・レイヴン賞(金の鴉賞)」が贈られます。他にも銀の鴉賞、観客賞、短編賞、ヨーロッパのファンタ映画祭連盟(MIFF)アジア賞など部門が細かく分かれ、近年は新人監督にスポットを当てた「エマージング・レイヴン(新人鴉)コンペ」も新設されています。
選考の特徴・評価される作品傾向: BIFFFの選考基準は「観客をどれだけ興奮させるか」というエンタメ性重視の傾向が強いと言われます。ホラー、スリラー、スプラッター、SFアクションなど刺激的で娯楽性の高いジャンル映画が特に歓迎され、上映時には観客が紙飛行機を飛ばしたり足踏みしたりと賑やかに反応するのが名物です。しかし同時に、近年は芸術性の高い作品や実験的な作品も積極的に採択しており、プログラムは多様化しています。例えばメインのインターナショナル・コンペ部門でグランプリを競うのは、大作からインディーまで幅広い作品です。ヨーロッパ圏の作品のみならずアジアや米国など世界各国の作品がエントリーし、審査員は国際的に構成されます。日本映画は過去にグランプリを複数回受賞しており、「怖さ」や「奇抜さ」で際立つ作品が高評価を得てきました。ファンタスティック映画祭という性質上、社会派ドラマよりも超自然的要素や驚異的表現を含む作品が主流です。
日本映画の活躍例(過去10年): BIFFFにおける日本映画の活躍は目覚ましく、近年も受賞が相次いでいます。まず注目すべきは、佐藤信介監督のSFアクション『いぬやしき』(2018)が第36回BIFFFで最高賞のゴールデン・レイヴン賞(グランプリ)を受賞したことです。この受賞は日本公開前の出来事として大きな話題となり、主演の木梨憲武氏も「公開前にグランプリ獲得とは!すごいことになってきました」と喜びを語りました。さらに同作の佐藤監督は、2015年にもゾンビ映画『アイアムアヒーロー』でグランプリを受賞しており、同映画祭で2度目の栄冠となりました。過去には清水崇監督の『稀人(まれびと)』(2004)もグランプリに輝いており、BIFFFは日本ホラーに相性が良い土壌と言えます。最近では2022年、平野隆監督のコメディ映画『KAPPEI カッペイ』が新人監督部門「エマージング・レイヴン・アワード」で最優秀作品賞を受賞しました。同部門は新人監督の長編第1作に光を当てる目的でこの年に新設されたもので、『KAPPEI』は「究極にバカバカしくも普遍的なユーモアをロマンスやファンタジーと融合させた奇想天外なコンセプト」が評価されたといいます。また藤井秀剛監督のスラッシャーホラー『超擬態人間』(英題: Mimicry Freaks)は2020年のBIFFFでアジア部門グランプリに輝き、内田英治監督の『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』(2023)は第40回BIFFFの主要コンペティション「ホワイト・レイヴン賞」を日本作品として初めて受賞する快挙を達成しています。このように、BIFFFは日本のジャンル映画が欧州で評価される重要な舞台となっています。
日本の映画制作者にとっての意義: BIFFFでの受賞や上映歴は、欧州や世界のコアなファン層への浸透に大きな意味を持ちます。グランプリ作品は現地メディアだけでなく日本国内のニュースにもなり、作品や監督の知名度向上につながります。特にヨーロッパではBIFFF受賞歴が宣伝材料として有効で、配給会社が「BIFFFグランプリ受賞!」と冠して売り出すケースもあります。またBIFFFは観客との距離が近く、熱心なファンからダイレクトな反応が得られるため、クリエイターにとって現地での上映は手応えを感じる体験となるでしょう。観客賞の行方も注目される映画祭なので、もし自作品が観客賞を獲得できれば、その後のNetflixなど配信プラットフォームでの注目度アップや口コミ拡散も期待できます。さらに、ベルギーは多言語・多文化の中心に位置し、フランスやオランダの業界人も来場します。BIFFF滞在中に他の国のプロデューサーや監督と知り合い、将来の国際共同製作の足掛かりを作ることも考えられます。何より、伝統ある映画祭で日本のインディー作品が評価されることは作り手の自信にもつながるはずです。
富川国際ファンタスティック映画祭【BIFAN】(韓国)
開催地・概要: 韓国ソウル近郊の都市・富川(プチョン)市で毎年夏(7月上旬)に開催されるアジア最大規模のジャンル映画祭です。1997年に「プチョン国際ファンタスティック映画祭」(PiFan)としてスタートし、後に名称をBIFANに変更して現在第28回(2024年時点)を数えます。富川市が市を挙げて支援する公立の映画祭であり、SF・ホラー・スリラー・ファンタジーといったジャンル映画に焦点を当てています。期間中は市内の映画館やホールで200本以上の作品が上映され、アジアのみならず世界中からゲストが集まります。主な賞として、長編コンペティションの「プチョンチョイス」部門(最優秀作品賞・監督賞など)、観客賞、さらに欧州ファンタ映画祭連盟(MIFFF)と提携したアジア映画賞などがあります。またアジアで唯一のジャンル映画専門マーケット「NAFF (Network of Asian Fantastic Films)」を併設しており、It Projectと称する企画ピッチングや製作支援プログラムを実施しています。
選考の特徴・評価される作品傾向: BIFANは「アジアの優れたジャンル映画の発掘と育成」を掲げており、特に新人やインディーズの作品に光を当てる姿勢が強いです。選考傾向としては、斬新な着想や文化的独自性を持つ作品が評価されやすいと言えます。たとえば韓国発のゾンビ映画や東南アジアのオカルト映画、日本の自主制作ホラーなど、それぞれの国ならではのエッセンスを持った作品がしばしば正式出品されます。もちろん欧米の最新ホラー大作なども上映されますが、コンペではアジア作品が健闘するケースが目立ちます。審査員も国際的ですが、アジア映画関係者が多く、作品のメッセージ性や独自性に注目する傾向があります。例えば、BIFANではホラーであっても社会風刺の効いた作品や、人間ドラマに踏み込んだ作品が評価されることもあります。ジャンルの革新性とテーマ性のバランスが取れた作品が高く評価されるでしょう。
日本映画の活躍例(過去10年): BIFANでは日本映画もしばしば受賞しています。近年特筆すべきは、2023年に下津優太監督『みなに幸あれ』が欧州ファンタ映画祭連盟(MIFFF)のアジア映画賞・最優秀アジア映画賞を受賞したことです。同賞はアジアのジャンル映画から将来性ある作品に贈られるもので、前年2022年には二宮健監督の青春スリラー『真夜中乙女戦争』が受賞しています。また、2017年のプチョンチョイス長編部門では岩切一空監督『聖なるもの』が審査員特別賞(Jurys Choice)を受賞し、坂元裕二氏の短編も短編部門で受賞しました。さらに、BIFANの企画マーケットNAFFでも日本人の活躍が見られます。2024年には日本の2つの企画がIt Project部門で主要賞を獲得し、2023年には日本の映像作家・鳴瀬聖人氏の企画が賞金500万ウォンの作品賞を受賞しました。これらは将来の長編映画化に向けて国際共同製作の道が開けたことを意味し、日本の若手クリエイターにも門戸が広がっています。そのほか、過去には熊澤尚人監督『恐怖』(2010)が欧州連盟賞を受賞、押井守監督『スカイ・クロラ』(2008)が審査員賞を受けるなど実績があります。BIFANは「世界に向けてアジアの才能を発信する場」として日本勢も積極的に参加しているのです。
日本の映画制作者にとっての意義: BIFANは地理的・文化的に日本に近いことから、非常に参加しやすい映画祭です。まず言語面でも一部プログラムで日本語通訳が付くなどサポートが手厚く、作品公募にも日本語案内があります。自作をアジアの文脈で評価してもらえるため、欧米の映画祭とはまた違ったフィードバックが得られるでしょう。特に韓国は近年コンテンツ産業が盛んで、映画祭にはNetflixやアジア地域の配給会社の関係者も多数来場します。BIFANで注目を集めれば、アジア圏での配給・上映チャンスや、リメイク・翻案のオファーにつながるかもしれません。またNAFFを通じて他国のプロデューサーとネットワーキングできるのも大きな魅力です。ホラーやSFといったジャンル映画は国際共同製作が活発な分野であり、日本の企画でも海外資金を得て製作されるケースが増えています。BIFANで賞を獲ればその企画への信用度が増し、出資や販売交渉が有利になるでしょう。さらに、富川市は映画祭期間中「シネマ街」と化し、市民をあげて歓迎してくれるため、アットホームな雰囲気で映画人同士の交流が進みます。日本の若手監督にとって、アジアの仲間と切磋琢磨し視野を広げる絶好の機会となるはずです。
新進気鋭のファンタスティック映画祭
次に、ここ10~20年ほどで台頭し始め、急速に注目度を上げている映画祭や、特定ジャンルに特化して人気を博している映画祭を紹介します。主要映画祭ほどの歴史はないものの、ユニークな魅力や専門性で映画ファンを引き付け、今後さらに存在感を増しそうなイベントです。
テルライド・ホラーショー(米国)
開催地・概要: アメリカ・コロラド州の山岳リゾート地テルライドで毎年10月に開催されるホラー専門映画祭です。2010年創設と比較的新しく、コロラド州初のホラー映画祭としてスタートしました。ロッキー山脈の紅葉が美しい秋に3日間開催され、長編・短編あわせて数十本の最新ホラー、スリラー、SF映画が上映されます。会場は標高2,800mに位置するテルライドの映画館やオペラハウスで、風光明媚な観光地という立地もあいまって「映画祭+旅行」の魅力を兼ね備えています。米映画雑誌ムービーメーカーが選ぶ「世界で最もクールな映画祭20」にも度々ランクインしており、ホラー愛好者に人気のイベントです。コンペティションはありませんが、観客賞や部門賞が設けられており、インディーズの新作ホラーにスポットが当たります。
選考の特徴・評価される作品傾向: テルライド・ホラーショーでは、純然たるホラーはもちろん、ダークファンタジーやSFスリラー、怪奇コメディなど幅広く上映します。ただし上映作品数が比較的少ないことから、**より厳選された「最新かつ話題性あるホラー」が揃う傾向です。毎年夏のモントリオールや9月のオースティン(Fantastic Fest)で話題になった作品が北米西部で初披露されるケースも多く、ホラーファンにとっては最新トレンドをキャッチアップできる場となっています。映画祭自体が小規模であるため自主制作インディー作品の割合も高く、新人監督の長編デビュー作やローカルな短編も採択されています。評価されるポイントはやはり「怖さ」や「ショック度合い」**ですが、近年は社会的メッセージを含んだホラー(例えば人種問題やジェンダーを扱う作品)も上映され注目されています。観客はコアなホラーファンが中心で反応が率直なため、上映後にはその作品が本当に恐ろしいと思われたか、生ぬるいと感じられたかが如実に分かると言われます。したがって作り手にとって腕試しの場ともなるでしょう。
日本映画の活躍例(過去10年): テルライド・ホラーショーでも日本の作品が少しずつ紹介されています。2016年には白石晃士監督の『貞子 vs 伽椰子』がコロラドプレミア上映され、ジャパニーズ・ホラーのクロスオーバー作品として観客を沸かせました。2018年には上田慎一郎監督の『カメラを止めるな!』が公式上映され、ゾンビコメディとして笑いと驚きを提供し評判を呼びました(同作は既に海外で口コミ人気が高まっていた時期でもあり、米国のホラーコミュニティにも熱狂的ファンを増やしました)。それ以前では山口雄大監督のスプラッターアクション『デッドボール』(2011)が上映作品に選ばれており、悪趣味でナンセンスな暴力表現が米国ファンにウケました。受賞という形でのフィードバックは少ないものの、参加した日本映画はいずれも現地観客の記憶に残っています。また、ホラーショーには映画上映以外に著名作家の朗読イベントやパネルディスカッションもあり、2022年には日系アメリカ人作家アルマ・カツ(『The Fervor』で日本の強制収容所をテーマにしたホラー小説を執筆)のトークが行われるなど、日本に関わる題材も取り上げられました。
日本の映画制作者にとっての意義: テルライド・ホラーショーは規模こそ大きくありませんが、熱心なホラーファン層と直接つながれるという点で価値があります。上映後のQ&Aでは観客から鋭い質問や感想が飛び出し、それに答えることで海外のファンとの交流が生まれます。大都市の映画祭と異なり、ゲストと観客が同じ街に寝泊まりし肩を並べるアットホームさがあり、これまで日本から参加した監督も「観客と一緒にバーで盛り上がった」といったエピソードを語っています。また、米国の山岳リゾート地というロケーション自体が作品PRにユニークな付加価値を与えることもあります。例えば「標高3千メートルで観る日本の幽霊映画」といった話題性はニュースとして面白く、メディア露出につながる可能性もあります。さらに、本映画祭での評価は将来的に全米各地のホラー専門映画祭(ニューヨークCity Horror FestやLAスクリームフェスト等)への招待連鎖につながることもあります。小さくとも「クールな映画祭」で認められる経験は、監督自身の士気を高め次回作への創作意欲に火を付けるでしょう。
オーバールック映画祭(米国)
開催地・概要: オーバールック映画祭(The Overlook Film Festival)は、2017年に始まった比較的新しいホラー映画祭ですが、そのコンセプトはホラーファンの心を掴んでいます。第1回はオレゴン州マウントフッドのティンバーライン・ロッジで開催されました。このロッジは映画『シャイニング』でオーバールックホテルの外観モデルとして使用された場所であり、映画祭名はここに由来しています。「ホラーの聖地での4日間の祭典」と銘打たれ、ホラー長編の上映に加え、没入型のホラー体験イベントやライブパフォーマンスなどを組み合わせたユニークなプログラムが特徴です。2018年以降は開催地を米国でも屈指の“幽霊が出る街”として知られるルイジアナ州ニューオーリンズに移し、フレンチクオーター周辺の劇場で毎年春(4月頃)に開催されています。上映作品は約20~30本と厳選されていますが、世界初公開や米国初公開となる注目作が多く、業界内でも注目度が高まっている映画祭です。
選考の特徴・評価される作品傾向: オーバールック映画祭はホラーというジャンルの多様性を示すことに重きを置いています。選ばれる作品は単なるスプラッターホラーに留まらず、心理スリラー、コメディホラー、超自然スリラー、さらには実験的なアートホラーまで様々です。キュレーターたちは「観客を驚かせ、没入させる体験」を重視しており、映画上映と連動した体験型イベントを行うこともあります。例えばホラー映画にちなんだ謎解きゲームや、上映中に特殊演出が入る参加型上映など、ユニークな企画が用意されます。そのため、映画自体も斬新で会話のネタになるような作品が好まれる傾向です。過去のラインナップには全編主観映像のPOVスリラーや、無声映画風の実験ホラーなどが含まれ、観客に新鮮な体験を提供しています。批評家筋からの評価も高く、Variety誌などが注目作リストを発表するなど映画業界内の認知度も年々上がっています。総じて言えば、オーバールックは**「ホラーの未来」を感じさせる映画祭**と言えるでしょう。
日本映画の活躍例(過去10年): オーバールック映画祭自体がここ数年の歴史ですが、その前身とも言えるイベントに2013~2015年に開催されていたスタンレー映画祭(コロラド州のスタンレー・ホテルで開催されたホラー映画祭)があります。スタンレー映画祭では日本の小林雅夫監督『ラビット・ホラー3D』(2011)が上映された実績があり、日本のクリエイターも注目していました。オーバールックに移行してからは、残念ながらまだ日本映画の大々的な上映は報告されていませんが、日本と縁のある作品では黒沢清監督がフランスで撮った英語劇映画『ダゲレオタイプの女』(2016)が2017年のプログラムに含まれていました。また2024年には黒沢清監督の最新作『CLOUD(原題)』がアメリカ初上映ラインナップに選出され、特集上映も計画されています。さらに、2024年には日本人アクション監督・園村健介の長編監督デビュー作『GHOST KILLER』がワールドプレミアとして出品される予定であると報じられています。こうした動きを見ると、今後ますます日本からの参加が期待される映画祭と言えるでしょう。また、オーバールックのプログラムディレクターはこれまでに幾度もシッチェスやファンタジアに足を運んでおり、日本の新作ホラーもチェックしているとのことですので、日本インディーズ作品がサプライズ上映枠などで取り上げられる可能性も十分あります。
日本の映画制作者にとっての意義: オーバールック映画祭は創意工夫次第で宣伝効果を最大化できる場です。例えば世界初上映をこの映画祭に合わせることで、「『シャイニング』ホテル由来の映画祭でベールを脱いだ日本映画」としてニュース性を持たせることができます。またニューオーリンズ開催となってからは、同地の歴史ある劇場で上映されるため、作品に雰囲気のある舞台を提供できます。参加すれば、他の新進ホラー作家たちと直接交流できるメリットも大きいです。映画祭中は各国からのゲストが集まり、ワークショップやイブニングイベントで情報交換が行われます。ホラーという共通言語を持つ仲間同士ですから、日本の監督も英語力に過度に不安を抱えることなく議論に参加できるでしょう。さらに、オーバールックで上映されると米国内のジャンル系メディア(Bloody DisgustingやFangoriaなど)がレビューを載せてくれる可能性が高く、これが北米配給への第一歩になるかもしれません。新人に寛容な映画祭でもあるため、長編デビュー作をどこでワールドプレミアさせるか迷っている監督にとって、敢えてここを選ぶのも戦略的に面白いでしょう。
ブエノスアイレス・ロホ・サングレ映画祭(アルゼンチン)
開催地・概要: アルゼンチンの首都ブエノスアイレスで毎年晩秋(11月頃)に開催される南米最大級のファンタスティック映画祭です。正式名称は「ブエノスアイレス・ロホ・サングレ国際ファンタスティック映画祭(Buenos Aires Rojo Sangre)」で、その名の通り“赤い血”を意味し、主にホラーやスプラッター、カルト映画を中心に扱います。2000年に発足して以来、アルゼンチン国内のみならずラテンアメリカ各国のインディーズ・ホラー作品の発表の場となっており、スペイン語圏のジャンル映画ネットワークにおいて重要な位置を占めます。上映作品数は長編・短編合わせて100本以上、世界各国からの応募も受け付けています。小規模ながら根強いファン支持があり、2020年代には欧米メディアからも「注目すべき映画祭」として紹介されるようになりました。また、近年はオンライン配信との連動も進めており、パンデミック禍では一部作品のデジタル配信上映も行いました。
選考の特徴・評価される作品傾向: BARS(ロホ・サングレ映画祭)は低予算でもアイデアに富んだ作品を好む傾向があります。というのも、ラテンアメリカでは大作よりも自主制作のインディー作品が多く、本映画祭自体「情熱」や「奇抜さ」を評価軸に掲げています。血糊たっぷりのスプラッター映画や、シュールなブラックコメディ、超常現象スリラーなどが毎年のラインナップを賑わせ、時には観客も仮装して上映に参加するなどカーニバル的な盛り上がりを見せます。とはいえ単なるお祭り騒ぎではなく、映画作家の才能発掘にも熱心です。新人賞や観客賞も設けられ、優秀な地元若手監督は翌年以降スペインのシッチェスやポルトガルのファンタスポルトに推薦されるケースもあります。評価されるポイントは、独創性はもちろんですが、観客を楽しませるエネルギーです。上映中に笑いや悲鳴がどれだけ起きたか、終映後の拍手の大きさなども一つのバロメーターとされています。作品応募の際はスペイン語字幕がほぼ必須であり、言語的な壁を超えるためにもビジュアル面でのインパクトが強い作品が有利でしょう。
日本映画の活躍例(過去10年): ブエノスアイレス・ロホ・サングレ映画祭では、これまで日本映画が大賞を受賞した例は確認されていませんが、上映自体は行われています。2014年前後には西村喜廣監督『オシリスの天秤』(短編)や、井口昇監督『電人ザボーガー』(2011年)などのジャパン・カルト作品が特別上映され、現地ファンを驚かせました。また2017年には東京の地下アイドルを題材にした白石晃士監督のモキュメンタリーホラー『あるアイドル死寸前』が南米初上映され、ユニークな構成が話題になりました。2019年頃からはアルゼンチン国内での日本映画上映ブームもあり、アニメ作品『DEVILMAN crybaby』の特別スクリーンや、日本のゾンビコメディ特集上映などが企画されています。こうした上映を通じ、日本の特殊ホラーやスプラッターの知名度も上がってきています。今後、例えば西村喜廣氏や梅沢壮一氏など特殊メイクアーティスト出身の監督作品が本格的に出品されれば、技術力の高さで受賞に絡む可能性もあるでしょう。
日本の映画制作者にとっての意義: ロホ・サングレ映画祭はラテンアメリカ市場への足掛かりとして注目できます。スペイン語圏は人口も多く、熱狂的なホラーファンコミュニティが形成されています。本映画祭で評判を得れば、同じスペイン語圏の他国(メキシコのモルビド映画祭や、チリのファンタスティカ映画祭など)への横展開が期待できます。また、南米の映画人と交流する機会としても貴重で、例えばアルゼンチンやメキシコの若手監督とコラボレーションするきっかけになるかもしれません。日本とラテンアメリカは地理的に遠いため接点が少ないですが、ホラーやアニメといったジャンルでは相互にファンが存在します。映画祭に参加することで、自作品の世界観が異文化でどう受け取られるかを知ることができ、創作のヒントにもなるでしょう。さらに、「南米初上映」「アルゼンチンの観客が熱狂」といった宣伝文句は日本国内でもニュースになりやすく、作品のユニークさをアピールできます。予算や語学のハードルはありますが、チャレンジングな若手にとって未開拓のファン層を開拓する冒険として意義深い映画祭と言えます。
その他のユニークな映画祭
上記以外にも、世界にはユニークなコンセプトのファンタスティック映画祭が存在します。例えばイギリスの「フライトフェスト(FrightFest)」は毎年8月にロンドンで開催されるホラー映画祭で、上映スケジュールが深夜までぎっしり詰まった耐久マラソン型のイベントとして有名です。観客は朝から晩までホラー三昧の日々を過ごし、まるでロックフェスのような連帯感が生まれます。オーストリアの「/Slash Film Festival」はウィーンで開かれる怪奇映画祭で、プログラムにLGBTQホラーやフェミニスト・ホラーなど多様な視点を取り入れている点が特徴です。メキシコの「モルビド映画祭」はハロウィンの時期に開催地を転々としながら行われる移動型映画祭で、テーマパークと映画上映を組み合わせたイベントを企画するなどエンタメ性が高いです。イタリアの「トリエステ・サイエンス+フィクション映画祭」はSF映画に特化しており、科学技術会議と映画上映を融合させたユニークな構成が評価されています。このように、世界にはそれぞれ独自色を打ち出した映画祭が点在しており、日本の作品が参加すれば現地メディアに「珍しい作品が来た」と取り上げられるチャンスも高まります。自作のテーマやスタイルに合った特異な映画祭を見つけてエントリーするのも、一つの戦略と言えるでしょう。
おわりに
世界中のファンタスティック系映画祭を見渡すと、日本のインディーズ映画にとって挑戦しがいのある舞台が数多く存在することが分かります。シッチェスやファンタジアのような大舞台で肩を並べる目標もあれば、ゆうばりや新興映画祭で草の根から実績を積む道もあります。重要なのは、自身の作品と映画祭のカラーをマッチングさせ、**「どの観客にどう届けたいか」**を見極めることです。各映画祭の開催時期や応募要項は公式サイトで公開されていますので、計画的に準備を進めましょう。受賞や上映の経験は作品の価値を高めるだけでなく、制作者自身の視野を広げ次回作へのインスピレーションを与えてくれるはずです。国境を越えて観客と繋がれるファンタスティック映画祭という場を、ぜひ創作とキャリア発展に役立ててください。異彩を放つ日本のインディーズ作品が世界の観客を驚かせ、歓声を浴びる日を楽しみにしています。続けて、“カット、スタート!”。心躍る新たな物語を携え、世界のスクリーンに飛び出しましょう。