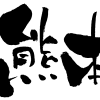Contents
はじめに
九州は、日本を構成する主要な島の一つであり、本州・四国・北海道とともに「四島」の中でも歴史的・文化的に特にユニークな位置づけを有しています。古代から外国との交流の窓口として重要な役割を果たし、また国内各地へ多様な文化を広めた起点としても知られています。さらに、豊富な温泉資源を擁することで全国屈指の温泉地帯として愛されてきました。このような九州の地理と歴史、そして温泉文化は、それ自体がドキュメンタリーや時代劇、あるいは現代的なフィクション作品の舞台として映像制作において大いに活かされるテーマであり、多くの監督や映像クリエイターを惹きつけてやみません。
本記事では、映画考察や映像制作という切り口も交えながら、九州の歴史的な位置づけと、その豊かな地理的特徴である温泉を軸に考察していきます。具体的には、九州が日本史の中でどのような位置を占めてきたのか、そして温泉地を取り巻く文化や歴史がどのように形成され、現在どのように活かされているのかを俯瞰してみたいと思います。映画や映像作品において九州はロケ地や時代劇の舞台としても非常に魅力的ですので、そこに注目してみると、歴史を表現する上での可能性や課題が浮き彫りになります。特に近年は、ドローンや高性能カメラなど映像制作の技術が進歩し、自然景観や歴史的建築をより美しく、より臨場感豊かに切り取れるようになってきました。九州はまさに、そのような映像表現の可能性が広がる地域なのです。
第1章:九州の地理的特徴と歴史的背景
1-1. 九州の地理的概観
九州は日本列島の南西に位置し、福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県の7県を含みます。沖縄本島や周辺の島嶼部も九州地方に含められることがありますが、狭義の九州と広義の九州ではやや定義が異なります。九州本島だけでも面積は約3万6千平方キロメートルほどあり、北海道、本州に次いで3番目に大きな島です。
九州の中央部には火山帯が連なり、阿蘇山や霧島連山など世界的にも有名な火山群を擁しています。また、南部の鹿児島県には桜島、北部の大分県や熊本県にも活発な火山が数多く存在し、九州全域が火山や温泉の宝庫となっています。これはプレートの活動が活発な日本列島の中でも特に地殻変動の恩恵を受けやすい地域であることが大きく関係しています。
九州は四方を海に囲まれており、中国や朝鮮半島に近いという地理的条件から、古代より海外との文化交流の窓口として機能してきました。古墳時代や飛鳥時代からすでに、朝鮮半島や中国大陸からの渡来人が九州に上陸し、仏教、金属加工技術、製陶技術などを広めたと考えられています。九州の港湾は、貿易・外交の重要な拠点として機能し、後の日本史に多大なる影響を及ぼすことになります。
1-2. 外部交流の起点としての九州
日本史において九州は「外からの入口」とも呼ばれます。古来より中国大陸や朝鮮半島との架け橋として、絶えず大陸の文化がまず九州に入ってきて、そこから全国へ伝播していった歴史がありました。例えば、稲作文化はもともと中国大陸や朝鮮半島から九州北部を通って徐々に本州へ広がっていったとされています。また、6世紀前後に伝来した仏教やその関連技術(寺院建築や仏像製作など)も、まずは九州北部に上陸した可能性が高いと見られています。
さらに平安時代から鎌倉時代にかけては、大宰府(現在の福岡県太宰府市)を中心として外交・貿易・防衛の拠点が置かれました。大宰府は「遠の朝廷(とおのみかど)」とも呼ばれ、九州と朝廷をつなぐ重要な行政機関でした。大宰府政庁の跡地は今でも史跡として残り、多くの観光客や歴史好きの人々が訪れています。この場所は映像作品の時代考証でもしばしば参考にされ、太宰府を舞台にしたドラマや映画のロケ地にもなっています。
1-3. 鎌倉時代から室町時代:元寇と九州
九州の歴史の中でも特に大きな事件の一つが、鎌倉時代末期に起きた「元寇(げんこう)」です。1274年(文永11年)の文永の役、1281年(弘安4年)の弘安の役の2回にわたり、モンゴル帝国(元)が朝鮮半島を経由して九州北部に侵攻を試みました。博多湾沿岸に防塁が築かれ、鎌倉武士団が集結してこれを迎え撃ちましたが、元の艦隊は暴風雨(いわゆる「神風」)によって大損害を受け、最終的に侵攻は失敗に終わります。
この元寇によって九州は、外国勢力からの侵略に対して最前線として戦いの舞台になりました。九州の人々は海を通じて迫ってくる敵に対峙しなければならず、大きな危機感とともに団結力を高めました。これによって鎌倉幕府の権威はある程度維持されましたが、同時に戦費や恩賞問題によって国内の不満も高まり、その後の南北朝時代や室町時代の混迷へとつながっていきます。元寇にまつわる合戦や博多湾の風景は、近年の時代劇や歴史ドキュメンタリーでもしばしば取り上げられ、その映像化にあたっては九州のリアルな自然景観が注目されています。
第2章:戦国時代と九州各地の動乱
2-1. 九州の戦国大名
戦国時代(15世紀末~16世紀末)においても九州は重要な舞台の一つでした。南九州(薩摩・大隅・日向)では島津氏が勢力を伸ばし、北九州(豊前・筑前・筑後・肥前)では大友氏、少弐氏、龍造寺氏などが台頭して覇権を争いました。特に大友宗麟(大友氏)はキリスト教布教を積極的に受け入れ、ポルトガルやスペインとの貿易や南蛮文化を取り入れるなど、一時期は大大名として九州北部一帯を支配下に置きました。島津氏は薩摩から勢力を拡大し、最終的にほぼ九州全土を掌握するに至るほどの実力を蓄え、豊臣秀吉による「九州征伐」まで拡大を続けました。
九州戦国史は、本州や関東・東北地方の戦国史とはまた異なるダイナミックさを持っています。海を隔てた海外勢力の影響もあり、南蛮貿易の利益や武器輸入などが絡んで戦乱が激化したことが特徴です。各地の大名が南蛮船を呼び込み、大砲や鉄砲といった新兵器を手に入れることで、戦のあり方や戦略が一変しました。これらの史実は、戦国時代を題材にした歴史映画や大河ドラマなどで題材にされることが少なくありません。映像クリエイターは、海外からの要素が加わった独特の戦国像を表現しやすい点に着目し、九州を舞台とした作品を制作することもあります。
2-2. 豊臣秀吉の「九州征伐」
豊臣秀吉は中国地方の毛利氏を平定した後、1587年(天正15年)に九州へ遠征を行い、島津氏を中心とする九州勢力を服属させました。これが「九州征伐」です。島津氏は当時、他の九州大名を次々に破り、ほぼ九州全域を掌握するほどの力を持っていましたが、秀吉の大軍勢と戦うには至らず、最終的に降伏。九州は豊臣政権の支配下に組み込まれました。
この「九州征伐」は日本の統一事業の中でも最終局面に近い重要な出来事であり、豊臣政権の基盤が全国へと拡大していく過程の一つの転機になったといえます。九州征伐の合戦場や史跡は、現在でも熊本県、宮崎県、鹿児島県など各地に点在しており、観光地化されている場所も多いです。映像制作においては、大規模な合戦シーンや秀吉と島津の外交交渉の描写にリアリティを持たせるため、地元のボランティアエキストラを募ったり、地形をそのまま活用したりと、地域協力のもと撮影が行われることもしばしばあります。
第3章:近世~近代にかけての九州
3-1. 江戸時代と鎖国下の長崎
江戸時代(1603年~1868年)には、徳川幕府による鎖国体制が確立し、日本は限られた場所を除いて海外との交流を大きく制限しました。その中で唯一、長崎の出島は海外との窓口として存続し、西洋の文物や学問がここを介して国内に伝えられました。オランダ人や清国人などが出入りする出島は、江戸幕府の厳格な監視下にありながらも、西洋の科学技術や医学、天文学などが輸入され、蘭学が広まる大きな契機になりました。
長崎の町並みは、和と洋が混在する異国情緒あふれる場所として知られ、幕末から明治維新期にかけて志士たちや海援隊などが海外とのパイプを探る場としても機能しました。現在の長崎市内には、当時の建築や教会、グラバー園など歴史的遺産が多く残り、ドラマや映画でもたびたび撮影の舞台となっています。鎖国下にありながら海外文化が流入し続けた特殊な雰囲気は、映像作品でもドラマチックに表現されることが多く、独特のロマンが感じられる地域です。
3-2. 近代化の始まりと薩長土肥
幕末から明治維新期にかけて、九州の薩摩(鹿児島)や長州(山口県、厳密には九州ではありませんが西日本の拠点)が倒幕・維新の中心勢力として大きな役割を果たしました。特に薩摩藩は西洋の軍事力と最新技術を積極的に導入し、雄藩として成長を遂げます。薩長同盟の成立(1866年)は徳川幕府を倒すための大きなステップとなり、明治政府樹立への道を開きました。さらに九州の肥前藩(佐賀)も近代工業の発祥地として知られ、反射炉や近代製鉄所などをいち早く導入したことでも有名です。
明治維新後は、九州各地でも大規模な近代化が進められました。長崎は造船所や軍港としての機能を強化し、世界に向けた日本の近代化のショーケースともいえる場所になりました。また、福岡や熊本、大分なども工業化や交通網の整備が進み、外国船や新幹線による人の往来が増加していきます。このような近代化のプロセスは、多くの歴史映画やドラマ、ドキュメンタリーの題材となっており、特に薩摩の西郷隆盛、大久保利通などを軸にした幕末ドラマや、肥前の佐賀藩での先進的な技術導入を描く作品などが作られてきました。
第4章:九州の温泉文化
4-1. 火山活動と豊富な温泉資源
九州は日本有数の火山地帯であり、桜島(鹿児島県)、阿蘇山(熊本県)、霧島連山(鹿児島・宮崎県境)、雲仙岳(長崎県)、由布岳(大分県)など、数多くの火山が点在しています。このように活発な火山活動を背景として、九州には豊富な温泉が湧き出しています。温泉は火山由来の熱エネルギーや地下水が温められることで生成され、多様な泉質を持つことが特徴です。硫黄泉や炭酸水素塩泉、塩化物泉、酸性泉など、それぞれ効能や色、においなどが異なり、人々を魅了してきました。
映像制作の観点から見ると、この温泉地特有の湯けむりや自然環境は、映画やドラマにおいて非常に印象的なシーンを作り出せます。湯治場のレトロな雰囲気や、自然豊かな渓谷に設けられた露天風呂などは、時代劇から現代ドラマ、さらには観光プロモーション映像まで幅広く使われるロケ地となっています。九州各地に広がる温泉街は、それぞれ独自の風情と歴史を持ち、全国からの観光客を惹きつけ続けています。
4-2. 九州を代表する温泉地
1. 別府温泉郷(大分県)
大分県別府市に位置する別府温泉郷は、源泉数・湧出量ともに日本有数の規模を誇ります。別府八湯(べっぷはっとう)とも呼ばれ、浜脇温泉、別府温泉、鉄輪温泉、観海寺温泉、堀田温泉、柴石温泉、亀川温泉、明礬温泉など、性質の異なる温泉群が集まっています。各温泉地には共同浴場が点在し、昔ながらの湯治文化を残す地域としても有名です。別府ならではの地獄めぐり(「海地獄」「血の池地獄」など)も観光客に人気で、湯けむりの立ち上る風景は映像としても非常にインパクトがあり、旅行番組や映画のロケ地としてたびたび使用されます。
2. 由布院温泉(大分県)
由布院温泉は、由布岳の麓に広がる自然豊かな温泉地で、ゆったりとした雰囲気の中でリゾート感を味わえるのが特徴です。近年は観光地として急速に人気が高まり、おしゃれなカフェやギャラリー、美術館などが立ち並ぶようになりました。映像作品においては、自然の風景と洗練された街並みを同時に描きたいときに選ばれることも多く、ロマンス映画やヒューマンドラマの舞台としても映えます。
3. 黒川温泉(熊本県)
熊本県阿蘇郡南小国町にある黒川温泉は、木造の旅館が立ち並ぶ情緒豊かな温泉地として人気が高いです。温泉手形を使って複数の旅館の露天風呂を巡る「入湯手形」制度が観光客に好評で、湯巡り文化を体感できるのが魅力です。山あいの静かな雰囲気が特徴で、秘湯感を味わえるため、多くのドラマや映画のロケ地として検討されることがあります。特に和風の情景を活かした時代劇や、温泉街を舞台にした人情ドラマなどには最適のロケーションです。
4. 雲仙温泉(長崎県)
長崎県雲仙市にある雲仙温泉は、活発な噴気活動が見られる「雲仙地獄」が名物です。火山ガスや蒸気が白く立ち昇る光景は独特で、地獄のような荒涼とした雰囲気が広がっています。雲仙岳の自然美も相まって、観光客だけでなく映像制作者にも魅力的な場所となっています。明治期には外国人避暑地としても知られ、西洋風の建築や歴史的建造物が点在し、異国情緒を活かした撮影も可能です。
5. 指宿温泉(鹿児島県)
鹿児島県南部にある指宿温泉は、砂むし温泉が特に有名です。海岸の砂浜で、地下から湧き出す温泉で熱せられた砂をかぶって温まる独特の入浴法は、世界でも珍しいと言われています。大河ドラマや時代劇の中でも、薩摩藩の舞台として指宿周辺が登場することがあり、その際に砂むし温泉も興味深い描写として取り上げられることがあります。
4-3. 温泉と地域文化の融合
九州における温泉文化は、単なる観光資源としてだけではなく、地域住民のコミュニティ形成や健康維持、さらには宗教的・霊的な意味合いをも包含しています。古来より「湯治場」として発展してきた温泉地では、長期滞在型の養生文化が根付いており、旅館や共同浴場を中心に人々が交流する風習が続いてきました。また、神社仏閣と結びついた温泉地もあり、霊場巡りの一環で温泉に浸かることが信仰や信心と結びつく例も見られます。
現代の映像制作においては、これら温泉地の文化的側面をより深く描く作品が注目を集めています。たとえば、温泉街の共同浴場で繰り広げられる人間模様や、古くから続く祭りや伝統行事、温泉にまつわる伝説や民話などは、ドキュメンタリーやドラマの題材として非常に豊かな素材を提供します。温泉独特の「湯煙」や「地獄めぐり」のような劇的な景観は、スクリーンに映し出すと強い印象を与えやすい要素です。海外の視聴者にも日本の温泉文化はエキゾチックで興味深い存在であり、インバウンド観光促進の映像作品などでも積極的に取り上げられています。
第5章:九州の歴史と映像制作
5-1. 歴史映画・時代劇の舞台としての九州
九州は、日本の歴史のさまざまな局面で中心的な役割を担ってきたため、時代劇や歴史映画の舞台としても魅力的な土地です。古代の大宰府を舞台にした作品、元寇を描く合戦シーン、戦国時代の島津家や大友家の物語、江戸時代の鎖国下の長崎、幕末の薩摩藩、明治維新に至る激動の時代――これらはすべて九州を中心にドラマが展開されており、それぞれ個性豊かな史実が存在します。映像制作におけるロケーション探しでも、九州は自然、都市、歴史的建造物がコンパクトにまとまっているため、大規模なセットを作らなくてもリアリティのある撮影が可能なケースが多いのです。
さらに、九州各地には郷土史研究を行っている団体や、歴史を活かした観光PRを積極的に行っている地方自治体が多く、地域と協力して作品づくりを進めることも容易です。時代劇の撮影には多くのエキストラが必要ですが、九州では地元住民が協力を惜しまず参加する文化が根付いている地域も少なくありません。祭りや郷土芸能と絡めた大規模撮影など、地域が一体となった映像制作がしやすいのも大きな魅力です。
5-2. 現代ドラマや観光映像における九州の活用
九州は、歴史映画や時代劇だけでなく、現代ドラマや観光映像の撮影地としても注目されています。例えば福岡市は九州最大の都市でありながら、古くからの文化と最先端の街並みが混在する独特の雰囲気を持っています。海岸線や河川、公園など自然豊かなスポットも多く、街中での撮影から自然風景の撮影まで幅広く対応できるのが強みです。また、港町として発展してきた北九州市のレトロな門司港エリア、工業都市としての歴史を感じさせるスペースワールド跡地周辺なども、異なる表情を見せており、作品のジャンルに応じて多彩なロケ地が選べます。
観光映像としては、やはり温泉や火山、海沿いのリゾートなどのイメージが強いですが、神社仏閣や祭り、グルメ(とんこつラーメン、鳥の炭火焼き、明太子、馬刺し、焼酎など)を組み合わせることで、九州全体の多彩な魅力をアピールすることが可能です。最近ではドローンを活用した空撮映像が主流となり、阿蘇山や桜島の上空からのダイナミックな俯瞰映像、湯煙が上がる温泉街の全景など、圧巻の映像が国内外の視聴者を惹きつけています。
5-3. 九州の歴史を再現する際の課題
九州の歴史を映像作品で再現する際には、いくつかの課題があります。一つは史跡の保全と撮影のバランスです。特に世界遺産や国宝・重要文化財に指定されている史跡の場合、大規模な撮影やセットの設営が厳しく制限されることが少なくありません。文化財を損傷しないよう万全の配慮が必要で、場合によっては撮影を断念せざるを得ないこともあります。
もう一つは、九州独特の方言や文化をどの程度反映するかという問題です。時代劇などでは標準語ベースで演じられることが多いですが、史実を忠実に再現したい場合、薩摩ことばや肥後ことば、博多弁など、地方ごとに全く異なる言語体系が存在します。これをどこまで取り入れるかで、作品のリアリティと視聴者の理解度のバランスが変わってきます。近年はNHK大河ドラマや歴史ドラマでも積極的に方言指導を行い、ローカル感を生かした演出が増えてきましたが、全国放送として配慮しつつ現地の方言を活かすという工夫が求められます。
第6章:映画考察と映像制作の可能性
6-1. 九州を舞台にした映画の事例
九州を舞台にした映画としては、地域色を活かしたヒューマンドラマや青春映画、さらには海外とのかかわりを描く歴史映画など多岐にわたります。近年では、大分県の温泉地を舞台にしたヒューマンドラマや、福岡の博多での都会的なシーンと田舎の風景を対比させる作品など、幅広いジャンルで九州ロケが行われています。過去には長崎の原爆や戦争の記憶をテーマにした映画、炭鉱の町として栄えた筑豊地域を描く作品なども制作されてきました。
また、海外との合作映画で九州がロケ地として選ばれることもあり、韓国や台湾、中国など近隣アジア諸国の映画スタッフや俳優が訪れるケースも見られます。これは九州が地理的にも文化的にもアジアに近いという特性が活きていると言えます。映画業界にとって、異文化交流を描く上で九州は理想的な舞台となり得るのです。
6-2. デジタル技術と映像表現の進化
近年、映画やドラマ制作ではCG(コンピューターグラフィックス)やVFX(ビジュアルエフェクツ)の活用が主流になり、撮影ロケーションの制限がある程度緩和されました。しかし、やはり実際の歴史的建造物や自然景観を使うロケ撮影が生むリアリティは大切にされています。特に九州のように、火山や温泉といった特殊な地形や情景がある場所では、実際に現地で撮影することでしか得られない迫力や説得力があります。
ドローンを活用した空撮や4K・8Kといった高解像度映像技術の進歩により、山岳地帯や海岸線、活火山の噴煙などを大スケールで撮影できるようになったのは大きなメリットです。従来であればヘリコプター撮影や非常に高額な機材が必要だった映像が、今では比較的低コストで実現しやすくなりました。これによって、九州の自然美や歴史的スポットを映像化する機会が増え、さらに高品質の作品を生み出す土台が整ってきています。
6-3. 地域活性化と映像制作
九州各地の地方自治体は、ロケ誘致やフィルムコミッション活動に熱心です。映画やドラマの撮影が行われれば、その地域の知名度向上や観光客の増加が見込まれ、地域経済の活性化につながるからです。特に温泉地を有する自治体では、宿泊施設や交通インフラが整っており、長期ロケにも対応しやすいという利点があります。撮影期間中のキャストやスタッフの滞在費、撮影に協力する地元企業や人材の雇用など、地域に直接的な経済効果が生まれます。
また、映像作品が公開・放送された後も、ロケ地巡りの観光が盛り上がることで長期的な利益が期待できます。温泉地が舞台となった作品の場合は、ファンが作品中のシーンを再現しようと同じ宿や露天風呂を訪れるなど、いわゆる「聖地巡礼」が行われることが多々あります。これをきっかけに、地元に根付いた文化や歴史にも興味を持つ人が増え、結果として地域全体の文化継承にも良い影響を与えるのです。
第7章:九州の未来と映像文化
7-1. 世界に向けた発信力
九州は地理的にも文化的にも、日本とアジアの架け橋としての役割を担ってきました。現代においてもそのポテンシャルは衰えておらず、むしろ交通インフラの発展やインターネットを介した情報発信の容易化により、世界へ向けて九州の魅力をアピールする機会が拡大しています。映画やドラマ、ドキュメンタリー、さらにはYouTubeなどのオンライン動画プラットフォームを通じた個人発信など、多様な映像メディアが存在する今だからこそ、九州の歴史や文化、温泉資源などを国際的に伝えることが可能になっています。
外国人観光客にとっては、九州は東京や京都、大阪に比べるとまだ知名度が低い部分もありますが、「隠れた宝庫」として潜在的な人気を博しており、特に温泉や自然、独特の食文化に魅力を感じる人が増えています。映画祭や映像フェスティバルを九州で開催し、海外のクリエイターと交流を深める動きも活発化してきており、国際共同制作の機運も高まっています。
7-2. ディスカバー・九州の歴史
一方、国内向けにも、まだまだ九州の歴史や温泉文化は掘り起こされていない話題が多く存在します。時代劇や歴史番組では本州中心のストーリーが展開される傾向が強い中、九州の視点から日本史を捉え直すことは、新たな発見や斬新な映像表現をもたらす可能性があります。例えば、古代から近代に至るまでの対外関係史を「九州目線」で描いた作品や、温泉文化を中心に据えた歴史ドラマ、あるいは九州が舞台のSF作品など、アイデアは尽きません。
さらに、温泉と関係する伝統医療や養生文化なども映像化の余地が大いにあります。たとえば、数百年の歴史を持つ老舗旅館や、その周辺で伝承される民話・伝説を背景にした物語を描けば、観光客にも地元民にも刺さる作品が期待できるでしょう。近年のスローライフやウェルビーイング志向の高まりともリンクし、地域の健康増進や持続可能な観光スタイルの提案にもつながります。
7-3. 映画・映像制作を通じた九州ブランドの向上
映画や映像制作は、地域ブランディングの非常に強力な手段です。成功した作品には長年にわたって価値が残り、観光地やロケ地への関心を喚起し続けます。九州が舞台となる映画やドラマ、ドキュメンタリーをさらに増やしていくことで、国際社会における九州の認知度とブランド力を高めることが可能です。各自治体や企業、地域住民が協力して映像制作を支援し、文化遺産や自然資源を保護しながら魅力的な作品を生み出すことで、九州に新たな付加価値をもたらすでしょう。
また、九州出身のクリエイターや俳優、音楽家などが地元にルーツを持つ作品を作り上げることも、地域活性化の大きな追い風になります。地元の人々が誇りを持ち、外部の人々が魅力を再発見することで、「九州ブランド」はより強固なものとなり、日本列島全体における九州の存在意義が再評価されるきっかけにもなります。
まとめ
本記事では、日本史の中で九州が担ってきた役割と、その豊かな地理的特徴である温泉文化を軸に、映画考察・映像制作の視点を交えて総合的に考察してきました。古代から海外との窓口として機能し、元寇や戦国時代、江戸時代の鎖国下においても国内外の文化交流の第一線にあった九州は、歴史的ドラマの宝庫です。また、温泉をはじめとした豊かな地形・資源は、観光資源であると同時に映像表現の格好の舞台でもあります。
映像制作において、実際の歴史舞台や自然環境を活用できることはクリエイティブな表現に大きな強みを与えます。九州の火山や温泉地を撮影すれば、他地域では得られない迫力や独自性が作品にもたらされるでしょう。さらに、地域の協力体制やフィルムコミッションの存在によって、大掛かりな時代劇や歴史ドキュメンタリーの撮影が可能になるのは、九州が持つ地域力の表れでもあります。
温泉文化は健康・癒やしの側面だけでなく、コミュニティや伝承、そして宗教的・精神的な文脈とも結びついており、その多彩な要素は映像に取り上げる際の新しい角度を提供してくれます。国内外の視聴者にとっても、日本の温泉文化は大変魅力的でエキゾチックなもの。九州の温泉地を舞台にした映像作品は、まだまだ多くの可能性を秘めています。
これからの時代、デジタル技術や国際交流の進展によって、九州の歴史や温泉文化を世界に発信するハードルは下がりつつあります。ローカルからグローバルへと発信される映像作品が、九州の新たな魅力を掘り起こし、多くの人々を惹きつけることでしょう。国内外の映画制作者が九州に注目し、ここを舞台に歴史の魅力と温泉文化の奥深さを表現してくれれば、九州はさらにその存在感を高め、日本の映画産業や地域振興に大きく貢献するに違いありません。
九州は、日本史における地理的・歴史的立ち位置、そして世界有数の温泉地帯としての魅力を兼ね備えた「多層的な魅力の宝庫」です。映像制作の観点から見ても、これほどバリエーション豊富なロケーションや題材が揃う地域はそう多くありません。歴史と文化が層をなして重なり合い、自然が生み出すダイナミックな景観との融合によって、観る者を魅了する映像世界がいくらでも広がっていくはずです。今後も九州を題材とした作品が増え、日本や世界の人々がこの地の奥深い歴史や美しい自然、そして豊かな温泉文化を改めて認識する機会が増えることを、心から期待したいと思います。