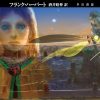Contents
熱海の魅力と熱海駅100周年
2025年、熱海駅は開業からちょうど100周年を迎えます。静岡県東部に位置し、東京からのアクセスも非常に良好な熱海は、温泉地として全国的に広く知られているだけでなく、海と山に囲まれた豊かな自然や歴史的建造物、神社仏閣など、多彩な観光資源を有しています。昭和から平成、そして令和へと時代が移るなか、熱海駅は観光客だけでなく地元の人々にとっても重要な拠点として機能し、街の玄関口として成長を支えてきました。開業当時から続く路線や車両の変遷はもちろん、熱海温泉が紡いできた伝統的な文化との結び付きも含めて、今日に至るまで数多くの歴史と物語を生み出してきたのです。
熱海駅100周年を記念して、古代から中世・近世・近代までの日本史の流れと熱海の歴史を大きく俯瞰し、その上で現在の熱海が持つ魅力や今後の展望について考えてみたいと思います。温泉の湧出地として古くより親しまれてきた熱海は、海岸線が美しく、さらに伊豆半島という地形上の恩恵から四季を通じて安定した気候にも恵まれました。それらの歴史を踏まえて、現在まで熱海がどのように発展してきたのかを、できるだけ詳しく掘り下げていきます。
1.熱海の起源と古代日本の時代背景
1-1. 古代日本の成立と熱海周辺地域
日本列島における人々の生活は、旧石器時代から続いていると考えられていますが、文字史料による確かな記録が表れるのは『古事記』や『日本書紀』に至ってからです。熱海が位置する伊豆半島周辺にも先史時代の遺跡が見られ、太古より人が定住してきた証拠が少しずつ発掘調査によって明らかになっています。たとえば縄文時代の遺跡が近隣で見つかっており、この地に豊富な漁場や温暖な気候がもたらされてきたことが、先住民にとって魅力的だった可能性があります。
一方、「熱海」という地名の由来については諸説あります。よく言われるのは、「海が熱い」と書くとおり、海辺で自然湧出する温泉や潮の満ち引きによって海中から温泉が湧く様子から名付けられた、という説です。古い時代から湯煙が立ち昇る光景が認められており、そこに“熱い海”という発想が加わって定着した可能性が高いとされています。
1-2. 律令制下における伊豆と熱海の位置付け
7世紀後半から8世紀にかけて、大化の改新以降整えられた律令体制は日本列島全体を行政区分として整備していきました。駿河国や伊豆国などもそうした中で位置付けられ、現在の静岡県東部を含む伊豆半島は「伊豆国」として政務が執り行われていました。熱海は海岸沿いにある温泉地として、古くから旅人や僧侶たちの間で“湯治”の名所とされていた可能性が指摘されます。
神社や仏閣の伝承には、伊豆国における霊場や霊験あらたかな場所についてしばしば言及されており、温泉の湯自体も神聖視されることがありました。実際、古文書には「熱海湯」への言及があり、朝廷に献上されたという伝承もみられるほどです。こうした敬意に支えられ、熱海の温泉は単なる養生の場であると同時に、信仰や祈りの対象としても位置付けられていったのです。
2.中世~戦国時代の動乱と熱海の変遷
2-1. 平安・鎌倉時代の熱海と伊豆
平安時代末期から鎌倉時代にかけて、伊豆は源氏ゆかりの地としても知られるようになりました。熱海は当時、政治の表舞台に出る地域ではありませんでしたが、相模国や駿河国へと続く海路の要衝であり、鎌倉幕府成立後は伊豆を経由して鎌倉へ向かうルート上にあったため、要所要所で人々が往来しました。温泉街が発達していたかどうかは記録が少なくはっきりとは分かりませんが、海や山の豊かな資源を背景に、多くの人が細々と暮らしていたと推定されています。
鎌倉時代には伊豆半島は伊東氏など地元の豪族が力を持ち、寺院や神社も独自に発展していきました。熱海にも古くから存在すると伝わる神社仏閣がいくつかあり、それらは漁業の守護や温泉の神霊との関連で崇敬を集めていました。たとえば伊豆山神社(伊豆山権現)は熱海のシンボル的な存在で、源頼朝と北条政子の逢瀬伝承が残るなど歴史浪漫に彩られた場所でもあります。
2-2. 戦国時代の動乱と交通路の変遷
室町時代後期から戦国時代にかけては、全国各地で群雄割拠の状態が続きました。伊豆も例外ではなく、北条氏や今川氏、武田氏などの勢力が拮抗し、駿河国・相模国・甲斐国をめぐる争いに巻き込まれていきます。熱海自体は軍事の拠点となったわけではありませんが、海上交通を抑えるための重要な地点である駿河湾・相模湾沿いの地域として、攻防上の目が向けられることもありました。
そうした中でも、熱海では温泉の湧出による湯治・休養の文化が完全に絶えてしまうことはなかったようです。これは海岸部の地形や豊かな温泉資源が護られていたこととも関係しています。人々が頻繁に通行する陸路とは少し外れた場所だったため、大規模な軍勢が押し寄せることは少なく、むしろ傷病兵が温泉治療に訪れることもあったとする伝承も残っています。
3.江戸時代と熱海の発展
3-1. 江戸幕府の成立と交通網の整備
徳川家康が江戸幕府を開いた17世紀以降、日本は大きな統一体制のもとで約260年の泰平の世を迎えます。江戸幕府は参勤交代制度を整え、主要街道の整備も進めました。その中でもっとも有名なのは東海道・中山道・甲州街道・奥州街道・日光街道など“五街道”ですが、伊豆半島の付け根を通る東海道筋が隆盛を極めるにつれ、熱海周辺にも街道を行き交う大名や旅人の一部が立ち寄るようになっていきます。
とはいえ、江戸時代の熱海は今のように鉄道や大きな国道が通っていたわけではないので、交通の便は決して良いとは言えませんでした。しかし、そこに温泉の魅力が加わることで、将軍家や大名家からも“湯治場”として知られるようになりました。実際、徳川家康自身も箱根や伊豆に出向いたとする逸話や、家康ゆかりの温泉に関する伝説は各地に残っています。また将軍や大名への献上湯として、熱海の湯が江戸に運ばれたとも伝わり、その効能が高く評価されていたことがうかがえます。
3-2. 旅籠と湯治場の整備
江戸時代は旅の文化が花開いた時代でもありました。伊勢参りや金毘羅参り、富士山詣などを目的に、庶民が旅をすることが増え、道中で温泉に立ち寄ることもひとつの楽しみになっていきます。熱海も江戸からの距離が適度であったこと、箱根を越えた先というロケーションが旅情を誘ったことなどから、次第に湯治客を迎える施設が整備され始めました。いわば「小さな温泉宿場町」としての機能が育まれ、その評判を耳にした人々が次々と訪れるようになります。
加えて、江戸後期には国学や和学の研究が進み、各地の名所や旧跡を踏破する旅人たちも数多く現れました。俳人や文人が旅中に熱海を訪れ、温泉の様子を俳句や随筆に綴った記録も散見されます。例えば松尾芭蕉や小林一茶ほど著名な俳人が訪れたという確証はないものの、近隣を旅していた文人の中には熱海の湯を詠んだ作品を残した例があるなど、文化的にも注目される地域だったのです。
4.明治維新から鉄道時代へ――熱海の近代化
4.1 明治維新と社会の大変化
19世紀半ばから幕末にかけて、日本はペリー来航や通商条約の締結によって開国を余儀なくされました。1868年の明治維新によって徳川幕府が崩壊し、新政府が成立すると、社会制度や文化は一気に欧化・近代化へと舵を切ります。これに伴い、交通・通信インフラも加速度的に整えられ、日本各地へ鉄道や電信が次々に敷かれました。こうした変革の中で、伊豆半島や熱海周辺にも波及効果が見られるようになります。
4-2. 東海道本線の開通と熱海への影響
明治期には、東海道の沿線を中心として東京と京都・大阪を結ぶ大動脈をつくるべく、鉄道建設が進められました。最初は神戸や京都を結ぶ路線が伸び、その後静岡方面へも路線網が拡大。東京と静岡を結ぶ主要区間として東海道本線が敷設され、やがて熱海にも鉄道が乗り入れる日が近づいていきます。鉄道敷設は当時の土木技術では困難な工事が多く、海沿いの断崖や山間部を貫くトンネルを建設する必要がありました。しかし、国の威信を懸けたインフラ整備計画であったため、幾多の難工事を克服しながら少しずつ線路が伸びていきます。
熱海への鉄道乗り入れが実現すると、これまで陸路と海路を併用してはるばる足を運んでいた観光客や湯治客が、短時間で移動できるようになりました。一躍全国的にも手軽に訪れられる温泉保養地となり、宿泊客の増加や温泉街の拡充が急速に進んでいったのです。
4-3. 外国人避暑客と近代旅館文化の成立
明治から大正期にかけて、日本へ訪れる外国人が増加しました。彼らは東京や横浜などに滞在するだけでなく、避暑・保養のため各地を巡ることも少なくありませんでした。箱根や日光と並び、熱海も温泉と海岸のリゾート地として徐々に知られるようになり、外国人向けの近代旅館や西洋式の設備を取り入れた宿泊施設が建てられます。こうした施設では洋食の提供や欧米流の応接も行われ、近代日本の新しい観光スタイルが芽生え始めました。
一方、日本人向けにも大規模旅館が誕生し始めます。電灯や水洗トイレ、洋室を一部取り入れた和洋折衷の旅館が登場し、多様なニーズに応える受け入れ体制が整っていきました。これらの旅館は、のちに熱海が「新婚旅行のメッカ」としてもてはやされる基盤をつくるうえで重要な役割を果たします。
5.1925年(大正14年)熱海駅誕生――100年の歴史
5-1. 熱海駅開業と大正末期の社会情勢
1925(大正14)年に熱海駅が正式に開業し、東京からの直通列車がますます便利になりました。大正時代は短い期間ではありましたが、民主主義的な風潮が高まり、都市文化が花開き、モダンな風俗が浸透していった時代です。そんな華やかな雰囲気のなか誕生した熱海駅は、観光地としての熱海の魅力をさらに押し上げる起爆剤となりました。
元々、熱海には「熱海鉄道」という軽便鉄道の計画もありましたが、最終的には官設鉄道による東海道本線の延伸ルートの一部として熱海駅が整備されることになりました。開業当時の駅舎は、今から見れば質素ではあるものの、海岸の景観とマッチした情緒ある建物で、当時の写真を見ると大正ロマンを感じさせます。
5-2. 昭和初期の熱海温泉ブーム
熱海駅の開業後、昭和初期にはさらに観光客が増え、熱海は日本屈指の温泉街として急速に発展しました。東京駅から熱海駅までの移動時間が格段に短縮され、日帰りや一泊旅行が可能になったことで、サラリーマン層を含む幅広い客層が熱海へ押し寄せるようになります。さらに「新婚旅行といえば熱海」という流行が戦後にかけて広がり、旅館やホテルが次々と増築・新設されていきました。
とりわけ昭和30年代以降の高度経済成長期には、ボーナスを得た会社員が団体旅行で熱海に行くことがステータスとして語られ、テレビドラマや映画の舞台にも度々登場します。熱海駅周辺の商店街は観光客向けのおみやげ店や飲食店が軒を連ね、常に賑わいを見せるようになりました。
6.戦中戦後の熱海と鉄道網の変遷
6-1. 戦中の熱海と駅周辺
第二次世界大戦が激化する中、全国的に観光どころではない状態が続き、熱海も例外ではありませんでした。旅館やホテルの多くは軍の施設に転用されたり、戦災を避けるために一部休業を余儀なくされたりもしました。ただし、熱海は大規模な空襲を免れた地域の一つであり、駅舎そのものの被害も比較的軽微でした。終戦後は、観光地として復興を図る下地が残っていたという点で、早期の再起動が可能だったといわれています。
6-2. 戦後復興と東海道新幹線の影響
戦後復興が進む中で、東海道本線は再び日本の大動脈として機能し始めます。やがて1964(昭和39)年に東海道新幹線が開通すると、東京~大阪間の移動が一気に高速化されました。その際、熱海に新幹線の駅が設置されたことは非常に大きな意味を持ちます。すでに温泉保養地として名高かった熱海は、これによって東京から1時間前後でアクセス可能となり、一気に“国民的な観光地”の地位を不動のものとしました。
もちろん新幹線停車駅となったことで、駅自体も大きく改装され、観光客の受け入れも拡大しました。昭和40年代~50年代にかけては、バブル期に向かう日本の高度経済成長の波に乗り、熱海駅周辺は多くの人々で溢れ、旅館・ホテルの建築ラッシュやリゾートマンションの開発が相次ぎました。
7.バブル崩壊後の苦境と再生への試み
7-1. 平成期における変化
1990年代以降のバブル崩壊により、日本各地の観光地は苦境に陥りました。熱海もその例外ではなく、バブル期に過剰投資された大型ホテルやリゾート施設の倒産、廃業などが相次ぎ、一時は「さびれた温泉街」というイメージが広がるほどの落ち込みを経験します。東京や大阪など大都市部とのアクセスが良い一方で、レジャーの多様化も進み、若い世代の観光客が海外旅行へ流出したり、他のテーマパーク型レジャーを選んだりする傾向が強まっていきました。
7-2. 再生に向けた取り組み
そんな中でも、熱海には古くからの温泉資源や豊かな海山の自然があります。駅周辺の商店街では地元食材を活用したグルメの発信や、新鮮な海鮮を売りにする飲食店のリニューアルなど、さまざまな試みが行われてきました。さらには、若いオーナーが経営するゲストハウスやデザイナーズ旅館が増え始め、古民家を再利用したカフェなども点在し、新旧が融合する魅力が再注目を浴びています。
近年では観光協会や市役所が連携して、熱海芸術祭などの文化イベントを開催したり、花火大会や海上でのマリンスポーツを積極的に発信したりと、多角的な集客策を実施。こうした努力によって、徐々に観光客数も回復していき、再び活気を取り戻しつつあると言えるでしょう。
8.熱海駅の現代的役割と「観光地駅」としての展望
8-1. 観光拠点としての熱海駅
現在の熱海駅は、在来線の東海道本線だけでなく、東海道新幹線が停車する主要駅のひとつとして多くの人が利用しています。駅ビルには土産物店や飲食店が並び、駅前広場にはタクシー乗り場やバスターミナルが整備されていて、市街地や近隣観光スポットへの移動がスムーズに行えるようになっています。JR東日本・JR東海の境界駅でもあるため、列車の運行管理上も重要な位置付けを持ち、運賃計算上の区切りでもある特殊な駅です。
駅周辺には商店街や旧来の旅館街が連なり、そこから坂道を上った山腹にはリゾートマンションやペンションが点在しています。さらに少し足を伸ばせば、十国峠や初島、伊豆半島の奥深くまで観光地が広がり、熱海を拠点に連泊することで、伊豆全体を楽しむことも可能です。こうした地理的優位性と交通アクセスの利便性こそが、熱海駅がもつ最大の強みと言えるでしょう。
8-2. 文化・芸術との結び付き
駅周辺の開発が進むなかでも、歴史ある伊豆山神社や来宮神社などの神社仏閣は変わらずに厳かな雰囲気を保ち、熱海の文化的アイデンティティを支えています。また、MOA美術館など芸術文化の発信拠点も存在し、駅からのアクセスが良いため気軽に立ち寄ることができます。こうした文化的施設をめぐる動線に、熱海駅が積極的に組み込まれていることは、街全体の活性化に大きく貢献しているといえるでしょう。
9.100周年の意義と今後の発展
9-1. 100年の歩みが示すもの
1925年(大正14年)に熱海駅が開業してから、2025年でちょうど100年。大正・昭和・平成・令和と激動の時代を経てなお、熱海駅は「温泉観光地としての玄関口」という不変の役割を担い続けています。この一世紀の間、社会情勢や経済状況、技術革新など数々の変化があったにもかかわらず、駅と街が一体となって成長してきた事実は、熱海の地がもともと持つ魅力と、人々の努力の結晶といえます。
駅自体のリニューアルやバリアフリー化、周辺道路の整備なども、随時行われてきました。特に近年は、高齢化社会に対応するためのエレベーターやエスカレーターの導入、外国人観光客が利用しやすい多言語表示の充実など、観光地ならではのサービス改善にも力が注がれています。
9-2. 未来への課題と展望
一方で、観光地としての熱海にはいくつかの課題も残されています。まずは、若年層やリピーターの獲得です。熱海は長らく「団体旅行」「新婚旅行」というイメージが強く、個人旅行や若者の観光トレンドとの間に隔たりがあった時期がありました。しかし近年はSNSで映えるスポットやおしゃれなカフェなどが増え、若年層の利用も徐々に増加傾向にあります。こうした動きをさらに後押ししていくためには、駅を中心とした街歩きマップの充実やデジタル技術を使った観光案内などが効果的でしょう。
また、温暖化や台風など自然災害への対応も不可避なテーマです。海沿いの地形ゆえに、高潮や暴風雨などで被害が出やすい地域でもあります。駅周辺や海岸線の防災インフラを強化し、持続可能な観光都市としての在り方を探っていく必要があります。
10.日本史と熱海駅が織りなす物語
ここまで述べてきたように、熱海の歴史は古代から現代に至るまで、温泉を中心にさまざまな要素が織り重なって形成されてきました。律令制度下での伊豆国としての位置付け、中世や戦国時代の動乱、江戸時代の湯治文化の隆盛、明治以降の近代化と鉄道開通、そして大正14年の熱海駅開業から始まる100年の物語――。それらは日本史の大きな流れの中で繋がっており、熱海駅がその節目節目に重要な役割を果たしてきたことが理解できます。
熱海駅100周年は、単に鉄道インフラとしての歴史が100年続いたというだけでなく、この土地の文化や人々の暮らしと深く結び付いて発展してきた証左でもあるのです。地域住民が支え、観光客が愛し、行政や各種団体が協力し合ってきたからこそ、今の熱海が存在しているといえます。
100周年からさらに先へ
熱海駅が100周年を迎えた2025年という年は、単なる「区切り」以上の意味を持つかもしれません。これまでの栄光と衰退、そして再生への歩みを再確認し、新たな一歩を踏み出すきっかけになるでしょう。鉄道の利便性と豊富な温泉資源、さらに海と山が織りなす自然美と歴史的・文化的な遺産を活かしながら、次の100年に向けてどのような街づくりを行っていくのか――それは熱海にとって大きなテーマでもあり、全国の温泉地・観光地にとっても貴重な示唆となるはずです。
観光というのは、ただ人が集まればよいわけではありません。街の文化や自然環境を維持しつつ、訪れる人々に心地よさや楽しさを提供し、地域経済を持続的に活性化させていく仕組みが求められます。熱海駅が持つポテンシャルは、鉄道という大きな移動手段が結節する場所であると同時に、街を歩けば神社仏閣や芸術文化、海の幸、山のレジャーなど、多彩な魅力へと誘ってくれる“ゲートウェイ”としての力です。
これからの時代、テレワークやワーケーションといった働き方が普及していくなかで、熱海は首都圏からの距離の近さを生かし、新しいライフスタイルの場としても注目されるでしょう。リモートワークをしながら、空き時間に温泉につかってリフレッシュし、地元のグルメを味わう。あるいは週末にふらりと電車に乗って、一泊だけして帰る。そんな柔軟な旅や滞在を受け入れる体制を整えることは、今後の観光振興にも大きく貢献するはずです。
100年の歴史を誇る熱海駅。これから先の100年でも、時代に即した変化を柔軟に取り込み、人々の思い出を温かく迎えてくれる駅であり続けてほしいものです。日本史の大きなうねりの中で揺るぎない存在感を示し、今もなお多くの人々を惹きつける熱海。その象徴としての熱海駅に、今後ますます期待が寄せられるのは間違いありません。もしこの機会に熱海を訪れるなら、ぜひ駅周辺をじっくり巡り、街が育んできた歴史の香りと、温泉地としての柔らかな雰囲気を体感してみてください。新たな発見と、これまでとは異なる視点で熱海を楽しむきっかけになることでしょう。